株式会社の設立を決意したものの、法務局での複雑な手続きを前に、何から手をつければよいかお困りではないでしょうか。
登記申請は専門的で難しそうに感じられますが、実は正しい手順と準備さえすれば、ご自身で完結させることも十分に可能です。
この記事では、株式会社設立における法務局での手続きの全手順を5つのステップで徹底解説します。
登記申請の流れはもちろん、必要書類の完全リスト、登録免許税などの費用、設立完了後に行うべきことまで、あなたが知りたい情報をすべて詰め込みました。
この記事を読めば、法務局での手続きに関する不安が解消され、自信を持って会社設立の第一歩を踏み出せるようになります。
株式会社設立における法務局の役割と基礎知識
株式会社を設立しようと考えたとき、必ず関わることになるのが「法務局」です。
しかし、具体的に法務局がどのような役割を担い、設立手続きにおいてどういった存在なのか、正確に理解している方は少ないかもしれません。
この章では、株式会社設立の第一歩として、法務局の役割と手続きに関する基本的な知識を分かりやすく解説します。
スムーズな会社設立を実現するために、まずはここから理解を深めていきましょう。
法務局は会社の情報を登録し公開する場所
法務局の最も重要な役割は、会社の基本情報を「商業登記」という制度によって公式に登録(登記)し、その情報を一般に公開(公示)することです。
会社を設立するということは、この商業登記簿に新しい会社の情報を記録してもらう手続きに他なりません。
商業登記には、主に2つの大きな目的があります。
- 会社の法人格の取得と信用の担保
法務局で設立登記が完了して初めて、会社は法律上の「法人」として認められます。登記された情報は、商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金の額、役員の氏名など、会社の根幹をなす重要事項です。これらの情報が公的な帳簿である登記簿に記録されることで、会社の存在が社会的に証明され、取引先や金融機関からの信用を得るための基礎となります。 - 取引の安全性の確保
誰でも手数料を支払えば、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、登記された会社の情報を確認できます。これにより、取引相手がどのような会社なのかを事前に調査できるため、安全で円滑な経済活動が促進されます。つまり法務局は、会社の情報を社会に広く公開することで、ビジネスにおける信頼性の基盤を支えているのです。
株式会社設立は本店所在地の管轄法務局で行う
株式会社の設立登記は、どの法務局でも申請できるわけではありません。
設立する会社の本店所在地をどこに置くかによって、申請先となる法務局が定められています。
この定められた法務局を「管轄(かんかつ)法務局」と呼びます。
例えば、東京都千代田区に本店を置く会社を設立する場合は「東京法務局(本局)」が管轄となり、大阪府大阪市中央区に本店を置く場合は「大阪法務局(本局)」が管轄となります。
市区町村によって管轄が細かく分かれているため、申請前には必ず自社の本店所在地がどの法務局の管轄区域に含まれるかを確認する必要があります。
管轄は、法務局のウェブサイトにある「管轄のご案内」ページで簡単に調べることができます。
もし管轄を間違えて申請書を提出してしまうと、受理されずに返却されてしまい、設立スケジュールに遅れが生じる原因となります。
登記申請の準備を進める最初の段階で、必ず管轄法務局を正確に把握しておきましょう。
法務局の開庁時間と相談窓口について
法務局へ直接訪問して手続きや相談を行う際には、開庁時間を事前に確認しておくことが重要です。
一般的な開庁時間や相談窓口の利用方法は以下の通りです。
| 項目 | 内容・注意事項 |
|---|---|
| 開庁時間 | 平日の午前8時30分から午後5時15分までです。 |
| 登記申請の受付時間 | 窓口での登記申請は、開庁時間と同じく午後5時15分までとなります。 時間ギリギリだと混雑する可能性があるため、余裕を持って訪問しましょう。 |
| 閉庁日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は業務を行っていません。 |
| 登記相談窓口 | 多くの法務局では、登記手続きに関する無料の相談窓口(登記手続案内)を設けています。 書類の書き方や手続きの流れについて質問できますが、あくまで一般的な案内に留まり、定款内容の是非といった個別具体的な法的判断は行いません。 相談は予約制の場合が多いため、訪問前に管轄法務局のウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせることを強くお勧めします。 |
オンライン申請や郵送申請も可能ですが、書類の不備について直接相談したい場合や、窓口で確実に申請を済ませたい場合は、上記の開庁時間を参考に来庁計画を立ててください。
【5ステップで解説】法務局での株式会社設立手続きの全手順

株式会社の設立は、一見すると複雑で難しそうに感じるかもしれません。
しかし、事前に全体の流れを把握し、一つひとつのステップを着実に進めていけば、誰でも手続きを完了させることができます。
ここでは、会社の基本事項の決定から法務局での登記完了まで、設立手続きの全手順を5つの具体的なステップに分けて詳しく解説します。
ステップ1 会社の概要決定から定款認証まで
法務局へ登記申請を行う前の、最も重要な準備段階です。
ここで決める会社の基本事項が、今後の事業の土台となります。慎重に検討を進めましょう。
会社の基本事項の決定
まず、設立する株式会社の骨格となる基本事項を決定します。
これらはすべて、後に作成する「定款(ていかん)」に記載する重要な情報です。
| 決定事項 | 主な内容と注意点 |
|---|---|
| 商号 | 会社の名前です。同一本店所在地での同一商号は登記できません。 法務局のオンラインシステムや国税庁の法人番号公表サイトで類似商号がないか事前に調査しましょう。 |
| 事業目的 | 会社がどのような事業を行うかを具体的に記載します。 適法性・営利性・明確性が求められ、将来行う可能性のある事業も記載しておくのが一般的です。 |
| 本店所在地 | 会社の住所です。最小行政区画(例:東京都新宿区)までの決定でも定款認証は可能ですが、登記申請までには地番まで確定させる必要があります。 |
| 資本金の額 | 会社設立時の元手となる資金です。 現在は1円から設立可能ですが、事業の運転資金や社会的信用を考慮して適切な額を設定することが重要です。 |
| 発起人 | 会社設立の企画者であり、資本金を払い込む人です。 1名以上いれば設立可能です。 |
| 役員構成 | 取締役、代表取締役などを決めます。 取締役会を設置するかどうかなど、会社の機関設計もこの段階で決定します。 |
| 事業年度 | 会社の会計期間(決算期)を決定します。 繁忙期を避ける、消費税の免税期間を考慮するなど、戦略的に設定することをおすすめします。 |
会社の実印(代表者印)の作成
基本事項が固まったら、法務局に届け出る会社の実印(代表者印)を作成します。
この印鑑は、登記申請書や印鑑届書など、重要な書類への押印に必要不可欠です。
一般的には、辺の長さが1cmを超え3cm以内の正方形に収まるサイズという規定があります。
今後の事業運営で必要になる銀行印や角印も、このタイミングでまとめて作成しておくと効率的です。
定款の作成と公証役場での認証
定款は「会社の憲法」とも呼ばれる最も重要な書類で、決定した会社の基本事項を記載したものです。
作成した定款は、法務局へ提出する前に、本店所在地と同じ都道府県内にある公証役場で認証を受ける必要があります。
紙の定款で認証を受ける場合は4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款で認証を受ければこの印紙代は不要になります。
ステップ2 資本金の払込みと証明書の作成
定款の認証が完了したら、次に発起人が定めた資本金を実際に払い込む手続きに進みます。
この払込みを証明する書類が、登記申請時の必須書類となります。
資本金の払込み
定款認証日以降に、発起人全員が、それぞれの出資額を一つの口座に振り込みます。
この際、まだ会社名義の銀行口座は存在しないため、発起人の代表者個人の銀行口座を使用します。
通帳のコピーが必要になるため、残高がある口座に自己資金を移動させるのではなく、必ず各発起人の名前で「振込」手続きを行うことが重要です。
払込証明書の作成
資本金が正しく払い込まれたことを証明するために「払込証明書」を作成します。
この書類には、以下の情報を記載します。
- 払込みがあった金額の総額
- 払込みがあった株数
- 1株の払込金額
- 払込年月日
- 本店所在地、商号
- 代表取締役の氏名
作成した払込証明書に、資本金の払込みが確認できる通帳のコピー(表紙、支店名や口座名義人が記載されたページ、実際の振込が記帳されたページ)を合綴し、会社の実印で契印します。
これで登記申請用の払込証明書が完成です。
ステップ3 法務局へ提出する登記申請書類の準備
いよいよ法務局へ提出する書類一式を準備する段階です。
書類に不備があると、修正のために時間がかかってしまいます。
抜け漏れがないか、入念にチェックしながら進めましょう。
登記申請書類一式の準備と確認
法務局へ提出する書類は、会社の形態によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。
法務局のウェブサイトで書式(テンプレート)が公開されているものも多いため、活用すると良いでしょう。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙(収入印紙を貼付)
- 定款(公証役場で認証済みのもの)
- 発起人の決定書(定款で本店所在地を市区町村までしか定めていない場合など)
- 役員の就任承諾書
- 役員の印鑑証明書
- 払込証明書
- 印鑑届書
- 本人確認証明書(場合によって)
書類の製本と押印
集めた書類は、定められた順番通りに重ねてホチキスで綴じます。
一般的には、登記申請書、登録免許税納付用台紙、その他の添付書類の順にまとめます。
書類の差し替えや抜き取りを防ぐため、ページのつなぎ目すべてに会社の実印で契印(割印)をします。
このとき、印鑑届書は他の書類とは一緒に綴じずに提出します。
ステップ4 管轄法務局への登記申請(窓口・郵送・オンライン)
準備した書類を、本店所在地を管轄する法務局へ提出します。
申請方法には「窓口」「郵送」「オンライン」の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
| 申請方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 窓口申請 | その場で書類の形式的なチェックを受けられる可能性があり、安心感が高い。 不明点を質問できる。 | 法務局の開庁時間(平日8:30~17:15)に行く必要がある。 混雑している場合、待ち時間が発生する。 |
| 郵送申請 | 法務局へ出向く時間と手間が省ける。 遠方からでも申請可能。 | 書類が法務局に到着した日が申請日となる。 軽微な不備でも修正に時間がかかる。 必ず書留郵便または簡易書留で送付し、封筒に「商業登記申請書在中」と朱書きする。 |
| オンライン申請 | 24時間いつでも申請可能。法務局へ行く必要がない。 添付書類をPDFで提出できる。 | マイナンバーカードやICカードリーダライタ、専用ソフトのインストールなど事前の準備が必要。 操作に慣れが必要。 |
なお、登記申請書を法務局に提出した日が「会社設立日」となります。
特定の日を設立日にしたい場合は、その日に合わせて申請を行いましょう。
ステップ5 登記完了と登記事項証明書・印鑑カードの受領
登記申請後、法務局での審査が完了すれば、晴れて株式会社の設立となります。
完了後は、今後の事業運営に不可欠な証明書等を取得します。
登記完了予定日の確認と登記完了
登記申請を行うと、法務局の窓口やウェブサイトで登記完了予定日を確認できます。
審査にかかる期間は法務局の混雑状況によって異なりますが、申請からおおむね1週間から2週間程度が目安です。
補正(書類の修正)が必要になった場合は、さらに時間がかかることもあります。
登記事項証明書と印鑑カードの取得
登記完了予定日を過ぎたら、法務局へ行き、会社設立後の手続きに必要な書類を取得します。
- 印鑑カードの交付申請: まず「印鑑カード交付申請書」を提出し、会社の印鑑カードを受け取ります。このカードは、今後、会社の印鑑証明書を取得する際に必ず必要になります。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得: 会社の存在を公的に証明する書類です。銀行口座の開設、融資の申込、税務署や自治体への届出など、あらゆる場面で提出を求められます。手数料はかかりますが、今後の手続きのために3~5通ほどまとめて取得しておくとスムーズです。
- 印鑑証明書の取得: 交付された印鑑カードを使って、会社の印鑑証明書を取得します。こちらも登記事項証明書と同様に、様々な手続きで必要となる重要な書類です。
これらの書類を無事に取得できれば、法務局で行う株式会社設立の一連の手続きは完了です。
【完全網羅】株式会社設立で法務局へ提出する書類リスト
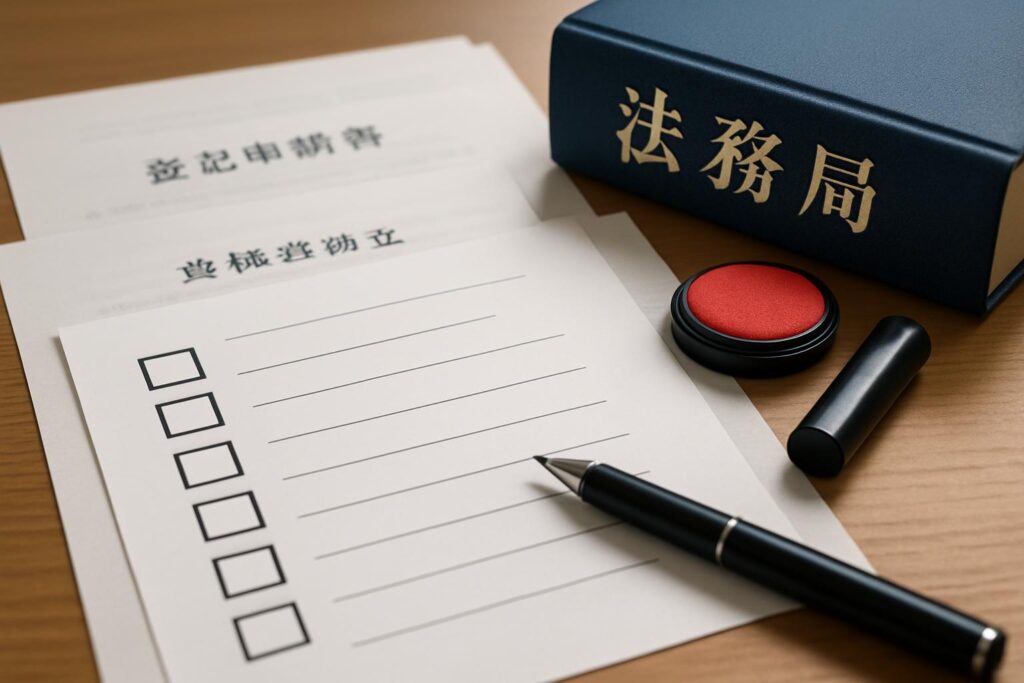
株式会社設立の登記申請では、多くの書類を法務局へ提出する必要があります。
書類に不備があると、補正(修正)を求められたり、最悪の場合、申請が却下されたりすることもあります。
スムーズに手続きを進めるためにも、どの書類がなぜ必要なのかを正確に理解し、チェックリストとして活用しながら準備を進めましょう。
提出書類は、設立する会社の形態(機関設計)によって異なります。
ここでは、どのような会社でも必要になる「必須書類」と、会社の機関設計に応じて必要になる「追加書類」に分けて、それぞれを詳しく解説します。
必ず必要になる書類
ここでは、発起人が1名以上で、取締役会を設置しない小規模な株式会社の設立を例に、原則として必ず提出が必要となる書類を解説します。
これらの書類は株式会社設立の根幹をなすものであり、一つでも欠けると登記申請は受理されません。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 登記申請書 | 会社の基本情報を記載し、登記を申請するためのメインの書類 |
| 登録免許税納付用台紙 | 登録免許税分の収入印紙を貼り付けるための台紙 |
| 定款 | 会社の根本規則を定めた書類(公証人の認証を受けたもの) |
| 就任承諾書 | 設立時役員が就任を承諾したことを証明する書類 |
| 印鑑証明書 | 設立時取締役の印鑑が本人のものであることを証明する公的な書類 |
| 払込証明書 | 資本金が正しく払い込まれたことを証明する書類 |
| 印鑑届書 | 会社の実印(代表印)を法務局に登録するための書類 |
登記申請書
登記申請書は、設立する会社の商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、役員の氏名といった基本情報を記載する、登記申請手続きの中心となる最も重要な書類です。
記載内容に誤りがないよう、定款や他の添付書類と整合性が取れていることを何度も確認しましょう。
申請書様式(テンプレート)は、法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
作成後は、会社の代表者となる人が会社実印(代表印)を押印します。
登録免許税納付用台紙
登録免許税は、株式会社設立登記の際に国へ納める税金です。
この税金を納付するために、税額分の収入印紙を貼り付けた台紙を提出します。
台紙はA4サイズの白紙であれば問題ありません。収入印紙は郵便局や法務局内の印紙売場で購入できます。
登録免許税の額は「資本金の額 × 0.7%」で計算されますが、この計算額が15万円に満たない場合は、最低額である15万円を納付します。
収入印紙を貼り付けた台紙は、登記申請書と合わせてホチキスで綴じ、契印(割り印)を押します。
定款
定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、会社の商号、事業目的、本店所在地、資本金、株式、役員など、会社の組織運営に関する根本規則を定めた書類です。
株式会社を設立するには、作成した定款を公証役場に持ち込み、公証人による「認証」を受ける必要があります。
法務局へは、この認証を受けた定款の謄本を提出します。
なお、紙の定款ではなく電子定款で認証を受けた場合は、認証済みのPDFデータをCD-Rなどの電磁的記録媒体に保存して提出します。
就任承諾書
設立時取締役や設立時代表取締役、設立時監査役などの役員が、その役職に就任することを承諾した意思を証明するための書類です。
役員に就任する人全員分が必要となります。
就任承諾書には、就任する役員の氏名と住所を記載し、本人が署名または記名押印します。
取締役会を設置しない会社の場合、設立時取締役の就任承諾書には個人の実印を押印する必要があります。
印鑑証明書
就任承諾書に押印された実印が本人のものであることを証明するために、印鑑証明書を添付します。取締役会を設置しない会社では、設立時取締役全員の印鑑証明書が必要です。
この印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものでなければならないため、取得時期には十分注意してください。
印鑑証明書は、個人の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。
払込証明書
「払込みがあったことを証する書面」とも呼ばれ、発起人が定款で定めた資本金を、指定された金融機関の口座に確かに払い込んだことを証明するための書類です。
この書類は、以下の2つのパーツを合わせて作成します。
- 払込証明書本体:払込総額や払込があった日付などを記載し、設立時代表取締役が会社実印を押印したもの。
- 金融機関の通帳のコピー:発起人代表の個人口座の通帳のコピー。表紙、支店名や口座番号が記載されている見開きページ、そして資本金の振込が記帳されたページの3点が必要です。
これらをホチキスで綴じ、各ページのつなぎ目に会社実印で契印(割り印)を押します。
印鑑届書
設立する会社の代表印(会社実印)を法務局に登録するための書類です。
この届出を行うことで、会社の印鑑証明書を発行できるようになります。
会社の重要な契約や手続きには印鑑証明書が不可欠となるため、登記申請と同時に必ず提出しましょう。
印鑑届書には、届出を行う代表取締役個人の実印を押印し、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。
会社の機関設計によって必要になる書類
会社の組織構造、例えば取締役会を設置するかどうか、現物出資があるかなど、定款で定めた機関設計によって追加で必要となる書類があります。
ここでは、代表的なものをいくつかご紹介します。
発起人の決定書
定款で本店所在地を「東京都千代田区」のように最小行政区画までしか定めていない場合に必要となる書類です。「本店所在地決定書」とも呼ばれます。この場合、発起人全員の同意によって、具体的な地番(例:東京都千代田区丸の内一丁目1番1号)を決定したことを証明するために、この決定書を作成します。発起人全員が署名または記名し、実印を押印する必要があります。
本人確認証明書
設立時取締役に就任する人のうち、印鑑証明書を提出しない人がいる場合に、その人の本人確認書類として必要になります。
具体的には、取締役会設置会社で、代表取締役に選定されなかった平取締役などが該当します。
本人確認証明書として認められるのは、運転免許証(両面のコピー)、マイナンバーカード(表面のみのコピー)、住民票の写しなどです。
コピーを提出する際は、余白に「原本と相違ありません。」と記載し、本人が署名または記名押印します。
【費用別】法務局での株式会社設立にかかるお金

株式会社の設立には、避けて通れない「費用」の問題があります。
一体、総額でいくらくらい準備すれば良いのでしょうか。
この章では、法務局へ支払う登録免許税をはじめ、設立手続き全体で発生する費用を項目別に詳しく解説します。
自分で設立する場合と専門家に依頼する場合のコストパフォーマンスについても比較検討し、あなたの状況に最適な選択ができるようサポートします。
法務局へ支払う登録免許税
登録免許税とは、株式会社の設立登記を法務局に申請する際に、国へ納める税金のことです。
これは設立手続きにおける法定費用の中でも最も大きな割合を占める費用となります。
登録免許税の金額は、以下の計算式で算出されます。
登録免許税 = 資本金の額 × 0.7%
ただし、この計算式で算出した金額が15万円に満たない場合は、一律で15万円を納付する必要があります。
例えば、資本金が100万円の場合、計算上は7,000円(100万円 × 0.7%)となりますが、最低税額が適用されるため、納める登録免許税は15万円です。
資本金が約2,143万円を超えるまでは、登録免許税は15万円と考えておけば問題ありません。
この登録免許税は、登記申請書に収入印紙を貼付して納付するのが一般的です。
法務局内や郵便局で収入印紙を購入し、登録免許税納付用台紙に貼り付けて提出します。
オンライン申請(GビズIDを利用した申請など)の場合は、インターネットバンキング等を利用した電子納付も可能です。
公証役場で支払う定款関連費用
法務局での手続きではありませんが、設立登記の前提として必ず必要になるのが「定款の認証」です。
これは、会社の根本規則である定款を、公証役場の公証人に認証してもらう手続きで、以下の費用が発生します。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 認証手数料 | 50,000円 | 資本金の額に関わらず一律です。 |
| 定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 定款1ページあたり250円で計算されます。 通常、8ページ前後になることが多いです。 |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 紙の定款で認証を受ける場合に必要です。 |
ここで注目すべきは「収入印紙代」です。
実は、「電子定款」という形式で認証を受ければ、この4万円の収入印紙代が不要になります。
電子定款とは、Wordなどで作成した定款をPDF化し、作成者が電子署名を付与したものです。
コストを少しでも抑えたい創業者にとって、非常に大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、電子定款の作成には専用のソフトウェアやICカードリーダーライタなどが必要になるため、環境を整える手間と初期費用がかかる点には注意が必要です。
自分で設立する場合と専門家に依頼する場合の費用比較
株式会社の設立は、自分自身で全ての書類を作成して手続きを進めることも、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
それぞれにメリット・デメリットがあり、費用も異なります。
ここでは、具体的な費用を比較してみましょう。
| 費用項目 | 自分で設立(紙の定款) | 自分で設立(電子定款) | 専門家に依頼 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 150,000円~ | 150,000円~ | 150,000円~ |
| 定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 定款謄本手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 | 約2,000円 |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | 0円 |
| その他実費 | 約3,000円 | 約8,000円~ | 約3,000円 |
| 専門家への報酬 | 0円 | 0円 | 50,000円~100,000円 |
| 合計費用の目安 | 約245,000円~ | 約210,000円~ | 約255,000円~ |
※その他実費には、発起人の印鑑証明書取得費用や会社実印の作成費用、ICカードリーダーライタの購入費用などが含まれます。
表を見ると、総費用を最も安く抑えられるのは「自分で電子定款を利用して設立する場合」です。
しかし、前述の通り、専用機器の準備や複雑な手続きをすべて自分で行う必要があります。
膨大な時間と手間がかかり、書類に不備があれば法務局へ何度も足を運ぶことになるリスクも考慮しなければなりません。
一方、専門家に依頼すると報酬が発生しますが、多くの専門家は電子定款に対応しているため、自分で紙の定款で設立する場合と比較して、報酬額の一部が相殺される形になります。
何よりも、時間と手間を大幅に削減でき、専門家の知識によって書類の不備なくスムーズに設立できるという大きなメリットがあります。
本業の準備に集中したい方や、手続きに不安がある方にとっては、専門家への依頼は非常に価値のある選択肢と言えるでしょう。
株式会社設立の登記完了後に法務局で行うこと

株式会社の設立登記申請が無事に完了すると、法務局から登記完了の連絡があります。
しかし、これで全ての手続きが終わったわけではありません。
会社として事業活動を本格的に開始するためには、登記完了後に法務局で取得すべき重要な証明書がいくつかあります。
これらは、銀行口座の開設や税務署への届出など、様々な場面で会社の存在を公的に証明するために不可欠です。
ここでは、登記完了後に法務局で行うべき2つの重要な手続きについて、詳しく解説します。
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得
登記事項証明書は、一般的に「登記簿謄本」とも呼ばれ、会社の商号、本店所在地、役員、資本金などの登記情報が記載された、会社の公式な身分証明書です。
この書類は、会社の信用を証明するために、以下のような様々な場面で提出を求められます。
- 金融機関での法人口座開設
- 税務署、都道府県税事務所、市町村役場への法人設立届の提出
- 年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署への社会保険・労働保険関係の届出
- 融資の申し込み
- 不動産の契約
- 許認可の申請
- 重要な取引先との契約
設立直後は特に多くの届出が必要になるため、最低でも3通から5通程度は取得しておくとスムーズです。
取得方法は、主に「窓口」「郵送」「オンライン」の3つがあります。
法務局の窓口で請求する方法
管轄法務局または最寄りの法務局の窓口に「登記事項証明書交付申請書」を提出して取得する方法です。
申請書は法務局に備え付けられています。
最も早く、その日のうちに証明書を受け取れるのがメリットです。
会社の商号と本店所在地を正確に記入できれば、誰でも申請できます。
郵送で請求する方法
法務局へ行く時間がない場合に便利な方法です。
「登記事項証明書交付申請書」と、手数料分の収入印紙、切手を貼った返信用封筒を同封して、管轄の法務局へ郵送します。申請書は法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
手元に届くまで数日かかる点に注意が必要です。
オンラインで請求する方法
「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、インターネット経由で請求する方法です。
手数料が窓口や郵送よりも安く、最もおすすめの方法です。
請求した証明書は、郵送で受け取るか、指定した法務局の窓口で受け取ることができます。
平日の21時まで請求可能なため、日中忙しい方でも利用しやすいのが特徴です。
| 請求方法 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 法務局の窓口で請求 | 600円 | 収入印紙で納付。 即日交付が可能。 |
| 郵送で請求 | 600円 | 収入印紙で納付。 返信用の郵便切手が別途必要。 |
| オンラインで請求(郵送で受取) | 500円 | インターネットバンキング等で納付。 |
| オンラインで請求(窓口で受取) | 480円 | インターネットバンキング等で納付。最も安価。 |
印鑑カードの交付申請と印鑑証明書の取得
法務局に届け出た会社の実印(代表者印)が本物であることを証明するのが「印鑑証明書」です。
重要な契約の締結や不動産登記、金融機関からの融資を受ける際などに必要となります。
そして、この印鑑証明書を取得するために、まず「印鑑カード」の交付を受ける必要があります。
設立登記が完了したら、登記事項証明書とあわせて印鑑カードの交付申請も行いましょう。
印鑑カードの交付申請
印鑑カードは、法務局の窓口で印鑑証明書を発行してもらうための磁気カードです。
一度発行すれば、以降は全国どの法務局でもこのカードを使って印鑑証明書を取得できます。
申請は、管轄法務局の窓口で行います。申請書に必要事項を記入し、法務局に届け出た会社の実印を押印して提出します。
代表取締役本人が申請に行く場合は、会社実印を持参すれば手続きできます。
代理人が申請する場合は、委任状が必要になるため注意しましょう。
交付手数料は無料です。
| 申請者 | 必要なもの |
|---|---|
| 代表取締役本人 | 印鑑カード交付申請書法務局に届け出た会社の実印 |
| 代理人 | 印鑑カード交付申請書(代理人の記名・押印欄も記入)法務局に届け出た会社の実印代理人の権限を証する書面(委任状) |
印鑑証明書の取得
印鑑カードの交付を受けたら、すぐに印鑑証明書を取得できます。法務局の窓口に備え付けられている「印鑑証明書交付申請書」に、会社の商号、本店所在地、印鑑カードの番号、代表者の氏名・生年月日などを記入し、印鑑カードを添えて提出します。
申請の際に会社の実印は不要で、印鑑カードさえあれば手続きが可能です。
手数料は1通あたり450円で、収入印紙で納付します。
登記事項証明書と同様に、今後の手続きで必要になる枚数をあらかじめ確認し、まとめて取得しておくと効率的です。
まとめ
本記事では、株式会社設立における法務局での手続きについて、具体的な5つのステップ、必要書類リスト、そしてかかる費用まで網羅的に解説しました。
株式会社の設立登記は、会社の基本情報を法的に登録し、社会的な信用を得るための重要な第一歩です。
手続きの流れは、「会社の概要決定」「資本金の払込み」「登記書類の準備」「法務局への申請」「登記完了後の手続き」と明確です。
特に登記申請書類は多岐にわたりますが、一つひとつ着実に準備を進めれば、ご自身で手続きを完了させることも十分に可能です。
費用を抑えたい場合、紙の定款で必要となる収入印紙代4万円が不要になる「電子定款」の活用が有効な手段となります。
法務局への申請方法は、窓口持参、郵送、そして「登記・供託オンライン申請システム」を利用したオンライン申請があります。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択しましょう。
もし手続きに不安があったり、時間を節約したい場合は、司法書士などの専門家に依頼することも賢明な選択です。
この記事が、あなたの会社の設立をスムーズに進めるための一助となれば幸いです。
法務局での手続きを正確に行い、円滑な事業スタートを切りましょう。



