株式会社設立時の資本金は、会社の体力と信用を示す重要なお金です。
安易に決めると融資や税金で損をする可能性も。
この記事を読めば、日本政策金融公庫の創業融資を有利に進め、消費税が最大2年間免除されるなど、あなたの会社にとって最適な資本金額を決める3つのポイントがわかります。
金額別のメリットから設立手続きの注意点まで網羅的に解説し、資本金に関するあなたの疑問をすべて解消します。
株式会社設立における資本金の基本知識
株式会社の設立を考えたとき、多くの人が最初に悩むのが「資本金」をいくらにするか、という問題です。
資本金は、単なる設立手続き上の数字ではありません。
会社の未来を左右する重要な要素であり、その金額設定には明確な戦略が必要です。
この章では、まず資本金とは何かという基本的な知識から、法律上のルール、そして一般的な相場観までを分かりやすく解説します。
正しい知識を身につけることが、最適な資本金額を決めるための第一歩です。
そもそも資本金とは会社の体力と信用を示すお金
資本金とは、会社を設立し、事業を運営していくための元手となる資金のことです。
創業者(発起人)が会社に払い込んだお金であり、会社の財産として事業活動に使われます。
金融機関からの借入金とは異なり、返済する必要がない「自己資本」である点が大きな特徴です。
資本金には、大きく分けて2つの重要な役割があります。
- 会社の体力(運転資金)
設立直後の会社は、すぐに売上が立つとは限りません。しかし、事務所の家賃、従業員の給与、仕入れ費用など、事業を続けるためには様々な経費が発生します。資本金は、こうした当面の運転資金となり、事業が軌道に乗るまでの会社を支える「体力」そのものになります。資本金が潤沢であれば、資金繰りに余裕が生まれ、安定した経営が可能になります。 - 会社の信用力
資本金の額は、法務局で登記され「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載されるため、誰でも閲覧できます。そのため、取引先や金融機関がその会社と取引をするか、融資をするかを判断する際に、会社の規模や財務的な安定性を測るための客観的な指標となります。資本金の額が大きいほど、「この会社にはしっかりとした事業基盤がある」という信頼につながりやすくなります。
このように、資本金は会社の内部的な「体力」と、外部に対する「信用力」の両方を表す、非常に重要な意味を持つお金なのです。
会社法改正で資本金1円での株式会社設立が可能に
「株式会社の設立には、最低でも1,000万円の資本金が必要だった」という話を聞いたことがあるかもしれません。
これは、2006年に施行された「会社法」以前の旧商法のルールです。
当時は「最低資本金制度」があり、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円以上の資本金がなければ設立できませんでした。
この制度が、起業を目指す人にとって大きなハードルとなっていました。
しかし、2006年の会社法改正によって最低資本金制度は撤廃され、現在では理論上、資本金1円でも株式会社を設立できるようになりました。
これにより、資金的な制約が少なくなり、誰でもチャレンジしやすくなったことは間違いありません。
ただし、「法律上可能」であることと、「事業運営上、現実的か」は別の問題です。資本金1円で設立した場合、会社の「体力」がほぼゼロであるため、設立登記にかかる費用(約20万円~)を支払った時点で、いきなり資金ショート(債務超過)に陥る可能性があります。
また、対外的な信用力も極めて低く見られ、金融機関からの融資や取引先との契約が困難になるなど、多くのデメリットが存在します。
そのため、資本金1円での設立は、特別な事情がない限り避けるべきと言えるでしょう。
資本金の全国平均や相場はどのくらい?
では、実際に株式会社を設立する際、資本金はいくらくらいに設定されているのでしょうか。
公的なデータや一般的な傾向から、その相場観を見ていきましょう。
日本政策金融公庫が発表した「2023年度新規開業実態調査」によると、開業時の資金調達額における自己資金の平均は288万円でした。
多くの起業家が自己資金を元に資本金を設定することを考えると、約300万円前後が一つの目安になると言えます。
また、設立される会社の資本金で最も多いボリュームゾーンは「100万円以上500万円未満」とされています。
もちろん、これはあくまで平均的なデータであり、最適な資本金額は事業内容や規模によって大きく異なります。
以下の表は、資本金の金額別に見た一般的な特徴や印象をまとめたものです。
自社の状況と照らし合わせながら、金額設定の参考にしてください。
| 資本金の金額 | 一般的な特徴・印象 |
|---|---|
| 100万円未満 | 個人事業主からの法人成りや、初期投資がほとんどかからないスモールビジネスで選択されるケース。対外的な信用力は低く見られがちで、融資を受ける際のハードルは高くなります。 |
| 100万円~300万円 | 多くのスタートアップ企業が設定する一般的な金額帯。事業開始から数ヶ月分の運転資金を確保できる目安であり、一定の事業基盤があることを示せます。 |
| 300万円~1,000万円未満 | 対外的な信用度が高まり、金融機関からの融資や大手企業との取引において有利に働く可能性が出てきます。事業計画に説得力を持たせやすい金額帯です。 |
これらの相場はあくまで参考値です。重要なのは、平均に合わせることではなく、これから始める自社の事業計画(運転資金、設備投資、融資、税金など)を総合的に考慮して、戦略的に資本金額を決定することです。
次の章からは、そのための具体的なポイントを詳しく解説していきます。
株式会社設立の資本金の決め方 3つの重要ポイント

株式会社を設立する際、多くの起業家が悩むのが「資本金をいくらに設定するか」という問題です。
会社法改正により1円からでも設立は可能になりましたが、安易に金額を決めてしまうと、後々の資金繰りや税金の支払いで思わぬ不利益を被る可能性があります。
ここでは、会社の未来を左右する資本金の決め方について、「融資」「税金」「事業の安定と信用」という3つの重要なポイントから徹底的に解説します。
ポイント1 創業融資を有利に進めるための資本金額
事業をスムーズに軌道に乗せるため、多くの起業家が日本政策金融公庫などの金融機関からの「創業融資」を活用します。
この融資審査において、資本金の額はあなたの事業への本気度と計画性を示す極めて重要な指標となります。
自己資金として見られる資本金の重要性
金融機関が融資を審査する際、最も重視する項目の一つが「自己資金」です。
自己資金とは、事業のためにコツコツと準備してきたお金のことで、創業者自身の事業への熱意や返済能力を客観的に示すものと見なされます。
そして、株式会社の資本金は、その最も明確で信頼性の高い自己資金の証明となります。
自己資金が少ないと、「計画性が乏しい」「事業への本気度が低い」と判断され、融資審査で不利になる可能性が高まります。
逆に、十分な自己資金(資本金)を用意できれば、金融機関からの信頼を得やすくなり、希望額の融資を引き出せる可能性が格段に上がります。
日本政策金融公庫の融資制度と資本金の関係
創業者にとって心強い味方である日本政策金融公庫の「新創業融資制度」では、自己資金要件が設けられています。
具体的には「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」という要件があります。
しかし、これはあくまで最低ラインです。
例えば300万円の融資を受けたい場合、自己資金は30万円あれば要件を満たしますが、審査を有利に進めるためには十分とは言えません。
一般的に、融資希望額の3分の1から2分の1程度の自己資金(資本金)を用意することが、審査通過の確度を高める目安とされています。
融資を検討している場合は、希望する融資額から逆算して資本金額を決めるというアプローチが非常に有効です。
ポイント2 税金の負担を軽くするための資本金額
資本金の額は、設立後の税負担、特に設立初年度と2年目のキャッシュフローに直接的な影響を与えます。
知っているか知らないかで手元に残る資金が大きく変わるため、節税の観点から資本金額を戦略的に設定することが重要です。
特に「消費税」と「法人住民税」の2つが大きなポイントになります。
資本金1,000万円未満で消費税が最大2年間免除に
設立時の資本金額を考える上で、最もインパクトの大きい節税メリットが消費税の免税です。
原則として、資本金を1,000万円未満に設定して会社を設立すると、設立第1期と第2期の2事業年度にわたり、消費税の納税義務が免除されます。
売上にかかる消費税を納める必要がなくなるため、設立初期の資金繰りが厳しい時期において、これは非常に大きなメリットとなります。
ただし、以下の例外ケースに該当すると免税が適用されない場合があるため注意が必要です。
- 第1期の事業年度開始日から6ヶ月間の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えた場合、第2期から課税事業者となります。
- インボイス制度(適格請求書発行事業者)の登録申請を行った場合、資本金の額にかかわらず課税事業者となります。
特別な理由がない限り、このメリットを最大限に活用するため、資本金は999万円以下に設定するのが賢明な選択と言えるでしょう。
法人住民税の均等割を意識した資本金の決め方
法人が納める税金の一つに「法人住民税」があります。
法人住民税は、利益に応じて課税される「法人税割」と、会社の規模に応じて定額で課税される「均等割」で構成されています。
この「均等割」は、たとえ事業が赤字であっても必ず支払わなければならない税金です。
そして、均等割の税額は「資本金等の額」と「従業員数」によって区分されています。
以下の表(東京都の場合)を見てわかる通り、資本金が1,000万円を境に税額が大きく変わります。
| 資本金等の額 | 都内の従業者数 | 法人都民税 均等割額(年額) |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 50人以下 | 7万円 |
| 1,000万円以下 | 50人超 | 14万円 |
| 1,000万円超 1億円以下 | 50人以下 | 18万円 |
| 1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 20万円 |
このように、資本金が1,000万円を超えた瞬間に、均等割の最低額が7万円から18万円へと11万円も増加します。
消費税の免税メリットと合わせても、資本金を1,000万円未満に抑えることが、設立初期の税負担を軽減する上で非常に合理的な判断となります。
ポイント3 事業の安定と信用に関わる資本金額
資本金は、金融機関や税務署だけが見るものではありません。
取引先や顧客、そして自社の経営そのものに関わる「会社の体力」と「社会的信用」を示す重要な指標でもあります。
設立直後の事業を安定させ、円滑な取引を行うための資本金額を設定しましょう。
当面の運転資金から考える資本金の目安
設立したばかりの会社は、すぐに売上が立つとは限りません。
売上が入金されるまでの間も、オフィスの家賃や人件費、広告費、仕入れ代金といった支払いは待ってくれません。
資本金は、こうした設立直後の運転資金として非常に重要な役割を担います。
資本金が少なすぎると、売上が立つ前に資金が底をつき、事業継続が困難になる「資金ショート」のリスクが高まります。
そうした事態を避けるため、少なくとも3ヶ月分、できれば6ヶ月分の運転資金(固定費+変動費)を資本金の目安とするのが一般的です。
例えば、月々の運転資金が合計50万円かかる見込みであれば、150万円から300万円を資本金として準備しておくと、安心して事業の立ち上げに集中できます。
事業に必要な許認可と最低資本金
行う事業の種類によっては、事業を開始するために国や都道府県から「許認可」を取得する必要があります。
そして、この許認可の要件として、一定額以上の資本金や自己資本が定められている場合があります。
例えば、以下のような事業では財産的基礎が要件とされています。
| 許認可の種類 | 必要な資本金(または財産的基礎) | 主な事業内容 |
|---|---|---|
| 一般建設業許可 | 自己資本の額が500万円以上であること | 建設工事の請負 |
| 特定建設業許可 | 資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上など | 大規模な建設工事の元請 |
| 一般労働者派遣事業許可 | 資産総額2,000万円以上(うち現金・預金1,500万円以上) | 人材派遣 |
| 第一種旅行業 | 基準資産額が3,000万円以上であること | 海外・国内の企画旅行の実施 |
これらの要件を満たさなければ、そもそも事業を始めることすらできません。
自社が計画している事業に許認可が必要かどうか、そしてその財産的要件は何かを、会社設立前に必ず確認し、それを満たす資本金額を設定することが不可欠です。
資本金の金額別メリットとデメリットを徹底比較

株式会社を設立する際の資本金額は、今後の事業運営に大きな影響を与えます。
会社の体力や信用度、さらには税金の負担まで変わってくるため、自社の事業計画に合わせた最適な金額設定が不可欠です。
ここでは、資本金の金額を3つのレンジに分け、それぞれのメリット・デメリットを具体的に比較・解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な資本金額を見つけるための参考にしてください。
資本金100万円未満で株式会社を設立する場合
会社法の改正により、資本金1円からでも株式会社の設立は可能です。
しかし、設立のしやすさと事業継続のしやすさは全く別の問題です。
資本金100万円未満で設立する際のメリットと、それを上回る可能性のあるデメリットを正しく理解しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 設立ハードルの低さ: 自己資金が少なくても法人格を取得でき、起業への第一歩をすぐに踏み出せる。リスクの抑制: スモールスタートで事業を開始できるため、万が一事業がうまくいかなかった場合のリスクを最小限に抑えられる。 |
| デメリット | 対外的な信用の低さ: 金融機関や取引先から「事業継続の体力がない」と判断されやすく、融資や新規取引の審査で著しく不利になる。資金繰りの悪化リスク: 設立直後の運転資金が乏しいため、売上が立つ前に資金がショートする危険性が非常に高い。赤字が続けば、すぐに債務超過に陥ってしまう。許認可の取得不可: 建設業や人材派遣業など、事業によっては法律で定められた最低資本金の基準を満たせず、そもそも事業を開始できない。 |
資本金100万円未満での設立は、初期投資がほとんど不要で、設立後すぐに安定した売上が見込めるWebライターやコンサルタントのような事業、あるいは個人事業主からの法人成りで既に事業基盤が確立しているケースなどに限定される選択肢と言えるでしょう。
資本金100万円から300万円で株式会社を設立する場合
多くのスタートアップ企業や小規模事業者が選択する、最も現実的な価格帯がこの100万円から300万円のレンジです。
対外的な信用と設立時の資金負担のバランスが良く、事業を安定させるための土台となり得ます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 一定の信用度の確保: 「事業のためにしっかりと準備をしてきた」という姿勢を示すことができ、100万円未満の場合と比較して金融機関や取引先からの見方が変わる。創業融資の土台となる: 日本政策金融公庫の新創業融資制度などを利用する際、自己資金の証明として資本金が重要視されます。この金額帯であれば、融資の申し込みが現実的な選択肢となります。当面の運転資金の確保: 事務所の家賃や人件費、仕入れ費用など、事業が軌道に乗るまでの数ヶ月分の運転資金を賄うことができ、経営に余裕が生まれる。 |
| デメリット | 十分とは言えないケースも: 大口の取引を希望する場合や、企業の信用力を特に重視する業界では、まだ不十分と見なされる可能性がある。許認可の基準に満たない場合: 業種によっては、この金額帯でも最低資本金の要件(例:一般建設業許可500万円以上)を満たせないことがある。 |
飲食店や美容室、小売店などの店舗型ビジネスや、ITサービス開発など、初期にある程度の運転資金が必要となる事業を始める場合、この価格帯での資本金設定は最低限のラインと言えます。創業融資の活用を視野に入れている創業者にとって、まず目指すべき現実的な目標金額です。
資本金300万円から1,000万円未満で株式会社を設立する場合
事業の安定性と将来の成長を強く意識するならば、300万円以上の資本金設定が理想的です。
特に重要なのは、消費税免除のメリットを最大限に享受できる「1,000万円未満」に抑えるという点です。
この価格帯は、信用力、資金力、税制上の優遇措置のすべてをバランス良く享受できる、いわば「ゴールデンゾーン」と言えるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 高い対外信用力: 金融機関や取引先から「経営基盤が安定している体力のある会社」と評価され、融資審査や取引条件で有利に働く可能性が格段に高まる。潤沢な運転資金による経営の安定: 予期せぬ出費や売上の変動にも対応しやすく、資金繰りを気にすることなく事業計画の遂行に集中できる。高額融資への道が開ける: 自己資金が豊富にあることで、より高額な創業融資を引き出しやすくなり、大規模な設備投資や積極的な人材採用といった成長戦略を実行できる。税制メリットの最大活用: 資本金を1,000万円未満にすることで、設立から最大2事業年度、消費税の納税が免除されるという大きなメリットを受けられる。 |
| デメリット | 設立時の資金調達ハードル: 会社設立時にまとまった自己資金を用意する必要がある。 |
最初からある程度の規模での事業展開を計画している場合や、BtoBビジネスで企業の信用力が直接受注に結びつくような業種、また高額な設備投資が必要な事業を始める創業者には、この価格帯での資本金設定を強く推奨します。
会社の成長を加速させるための強固な土台となるでしょう。
株式会社設立時の資本金に関する手続きと注意点
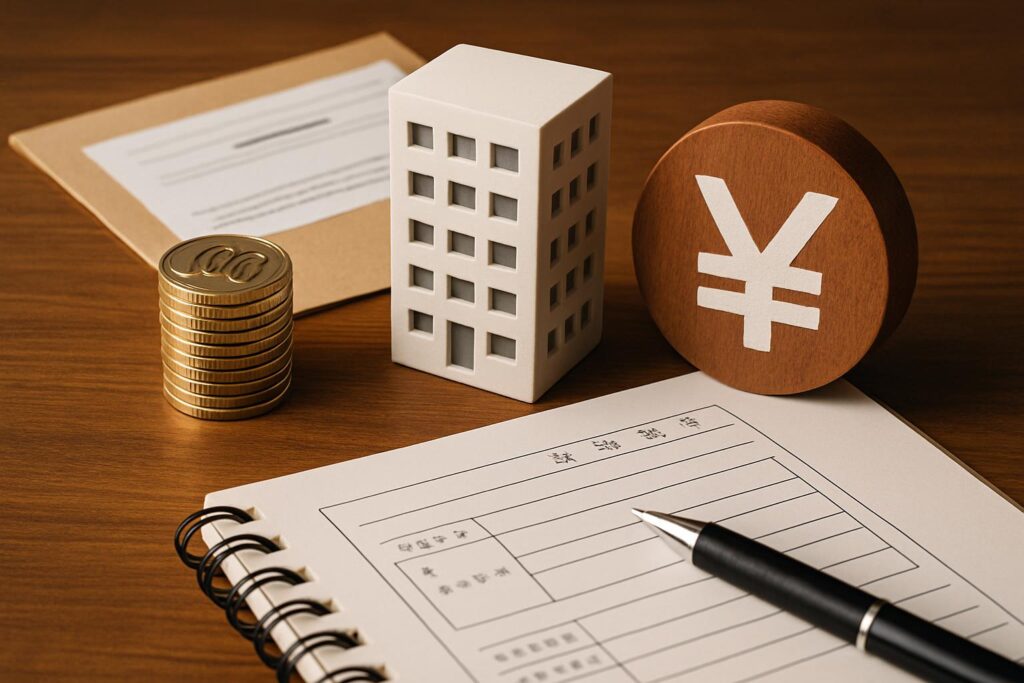
資本金の金額を決めたら、次は実際にそれを会社のお金として準備する手続きに進みます。
このステップは、会社の設立登記を完了させるために不可欠なプロセスです。
ここでは、資本金の払い込みに関する具体的な方法から、知っておくべき注意点、そして絶対に避けるべき行為までを詳しく解説します。
正しい手続きを踏むことが、スムーズな会社設立と将来の信用につながります。
資本金の払い込み方法とタイミング
資本金の払い込みは、法律で定められた手順に沿って正確に行う必要があります。
特に「いつ」「どこに」「どのように」払い込むのかを正しく理解しておきましょう。
払い込みのタイミングと流れ
資本金の払い込みは、「定款の認証後」から「設立登記申請前」までの間に行います。
会社設立前はまだ会社名義の銀行口座は作れないため、発起人(会社設立の準備をする人)の代表者個人の銀行口座を使用するのが一般的です。
- 発起人個人の銀行口座を用意する
新しく口座を開設する必要はなく、既存の口座で問題ありません。ただし、残高が0円の口座や、入出金が少なく履歴が分かりやすい口座を利用すると、後の証明がスムーズです。 - 各発起人が出資額を振り込む
用意した口座に、各発起人がそれぞれの出資額を振り込みます。この時、誰がいくら振り込んだか分かるように、振込人名義で入金するのが理想です。代表者が全員分をまとめて預け入れる形でも問題ありません。 - 通帳のコピーを取得する
払い込みが完了したら、その証明として通帳のコピーが必要です。法務局に提出するために、以下の3つの部分をコピーします。- 通帳の表紙
- 表紙を1枚めくった支店名や口座番号、名義人が記載されているページ
- 実際に資本金の払い込みが記帳されたページ
- 払込証明書を作成する
コピーした通帳と合わせて、「払込証明書」という書類を作成します。これは、代表取締役が「確かに資本金の払い込みがあったこと」を証明する書類です。
これらの書類が、設立登記申請の際に資本金が正しく準備されたことの証明となります。
単なる残高証明では認められず、実際に資金が動いた「振り込み」や「預け入れ」の履歴が必要な点に注意してください。
現金以外も可能 現物出資という選択肢
資本金は現金で用意するのが基本ですが、車やパソコン、不動産といった「モノ(現物)」で出資することも可能です。
これを「現物出資」と呼びます。
手元の現金は少なくても、事業に必要な資産をすでに所有している場合に有効な手段です。
例えば、事業で使う予定のパソコン(20万円相当)と自動車(80万円相当)を現物出資すれば、現金がなくても資本金100万円の会社を設立できます。
現物出資の対象と手続きの注意点
現物出資の対象となるのは、貸借対照表に資産として計上できる譲渡可能なものです。
| 内容 | |
|---|---|
| メリット | 手元の現金が少なくても資本金を増やせる。 創業融資の審査で自己資金として評価されやすくなる。 |
| デメリット | 手続きが複雑になる。 資産の価額を客観的に評価する必要がある。 |
現物出資を行う場合、その財産の価額が妥当であるかを証明する必要があります。
原則として裁判所が選任した検査役による調査が必要ですが、手続きが煩雑で費用もかかります。
しかし、現物出資する財産の総額が500万円以下である場合、検査役の調査は不要となります。
そのため、多くの小規模な会社設立では、この500万円の範囲内で現物出資が行われています。
ただし、定款に記載した現物出資の価額が、実際の時価よりも著しく高い場合、発起人はその差額を支払う義務(価額てん補責任)を負うリスクがあるため、価額の評価は慎重に行いましょう。
絶対にやってはいけない見せ金のリスク
資本金を準備する際、絶対に手を出してはならないのが「見せ金(みせがね)」です。
見せ金とは、一時的に他人からお金を借りてきて資本金として払い込み、会社の設立登記が終わったらすぐに引き出して返済する行為を指します。
資本金が実在しないにもかかわらず、あたかも存在するかのように見せかけるため、違法行為とされています。
見せ金が発覚した場合の重大なペナルティ
見せ金は、金融機関の融資審査や税務調査などで発覚する可能性があります。
例えば、設立直後に資本金と同額の不自然な出金履歴があれば、すぐに見せ金と疑われます。
この行為が発覚した場合、以下のような非常に重いペナルティが科せられます。
- 会社設立が無効になる可能性
見せ金による払い込みは法的に無効であり、会社の設立自体が無効とされるリスクがあります。(会社法第52条の2) - 刑事罰の対象になる可能性
法務局に虚偽の登記申請を行ったとして、「公正証書原本不実記載等罪」という刑法上の罪に問われる可能性があります。 - 金融機関からの信用失墜
最も現実的なリスクとして、金融機関からの信用を完全に失います。見せ金を行った事実が発覚すれば、将来にわたってその会社や経営者が銀行から融資を受けることは絶望的になります。
資本金は、会社の体力と信用を示すための重要なお金です。目先の金額を大きく見せるために安易に見せ金に手を出すと、会社の未来を閉ざすことになりかねません。
必ず自己資金で準備するようにしてください。
株式会社設立後に資本金を変更する方法

株式会社は、設立後も事業の状況や経営戦略に応じて資本金の額を変更することができます。
事業を拡大するための資金調達として資本金を増やす「増資」と、財務体質の改善などを目的として資本金を減らす「減資」の2つの方法があります。
それぞれ目的や手続きが大きく異なるため、自社の状況に合わせて適切な方法を選択することが重要です。
ここでは、増資と減資の具体的な手続きと注意点について詳しく解説します。
事業拡大に伴う増資の手続き
増資とは、新たに株式を発行し、会社の資本金を増やす手続きです。
主に、新規事業の立ち上げや設備投資など、事業拡大に必要な資金を調達する目的で行われます。
また、自己資本比率が高まることで財務基盤が強化され、金融機関や取引先からの信用度が向上するというメリットもあります。
増資の主な種類
増資には、実際に出資金の払い込みを伴う「有償増資」と、会社の資本準備金などを資本金に振り替える「無償増資」があります。
中小企業で一般的に行われる有償増資には、主に以下の2つの方法があります。
- 株主割当増資:既存の株主に対して、その持株比率に応じて新株を引き受ける権利を与える方法です。株主構成を変えずに資金調達ができます。
- 第三者割当増資:特定の第三者(取引先、提携先、役員、ベンチャーキャピタルなど)に新株を割り当てて引き受けてもらう方法です。外部から新たな経営パートナーを迎え入れたり、業務提携を強化したりする際に活用されます。
増資(第三者割当増資)の一般的な手続きの流れ
増資の手続きは会社法に定められており、厳格な手順を踏む必要があります。
ここでは、中小企業でよく利用される第三者割当増資の例で、手続きの流れを解説します。
- 募集事項の決定:株主総会の特別決議(または定款の定めに従い取締役会決議)で、発行する株式数、払込金額、払込期日などの募集事項を決定します。
- 募集株式の申し込みと割当て:引受希望者から申し込みを受け、会社が誰に何株を割り当てるかを決定し、通知します。
- 出資金の払い込み:引受人は、定められた期日までに会社の指定する金融機関の口座に出資金を払い込みます。
- 変更登記申請:払込期日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ資本金の額の変更登記を申請します。この登記が完了して、正式に増資の効力が発生します。
増資の登記に必要な費用と書類
増資の変更登記には、登録免許税をはじめとする費用がかかります。
必要となる主な書類と費用の目安は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要な書類(一例) | 株式会社変更登記申請書株主総会議事録取締役会議事録(設置会社の場合)募集株式の引受けの申込み又は総数引受契約を証する書面払込みがあったことを証する書面(通帳のコピーなど)資本金の額の計上に関する証明書 |
| 主な費用 | 登録免許税:増加した資本金の額の1,000分の7。この金額が3万円に満たない場合は、申請1件につき3万円となります。司法書士への報酬:手続きを依頼する場合、別途5万円~10万円程度の報酬が必要です。 |
増資を行うと、1株あたりの価値や既存株主の持株比率が変動する可能性があるため、既存株主への丁寧な説明が不可欠です。
経営状況に応じた減資の手続き
減資とは、株主総会の決議によって資本金の額を減少させる手続きです。
会社の財産が社外に流出する「有償減資」と、財産の流出を伴わず帳簿上でのみ資本金を減らす「無償減資」があります。
中小企業では、主に過去の赤字(繰越欠損金)を資本金で補填し、財務諸表を改善する目的(欠損填補)で無償減資が利用されるケースが一般的です。
減資の大きな注意点「債権者保護手続」
減資は、会社の財産的基礎である資本金を減少させる行為であり、会社の債権者(金融機関や取引先など)にとっては返済能力の低下につながる可能性があります。
そのため、会社法では減資を行う際に必ず「債権者保護手続」を行うことを義務付けています。
これは、増資にはない減資特有の重要な手続きです。
減資(無償減資)の一般的な手続きの流れ
欠損填補を目的とした無償減資を例に、手続きの流れを解説します。
- 株主総会での決議:株主総会の特別決議で、減少させる資本金の額や減資の効力発生日などを決定します。
- 債権者保護手続:以下の2つの手続きを両方行う必要があります。
- 官報公告:国の機関紙である「官報」に、減資を行う旨と、債権者が異議を述べることができる旨を掲載します。
- 個別催告:会社が把握している個別の債権者(金融機関、仕入先など)に対して、書面で同様の内容を通知します。
- 減資の効力発生:株主総会で定めた効力発生日を迎えることで、減資の効力が生じます。
- 変更登記申請:効力発生日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ資本金の額の変更登記を申請します。
減資の登記に必要な費用と書類
減資の手続きは複雑で時間もかかるため、専門家への相談を推奨します。
必要となる主な書類と費用の目安は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要な書類(一例) | 株式会社変更登記申請書株主総会議事録資本金の額の計上に関する証明書公告及び催告をしたことを証する書面(掲載された官報など)異議を述べた債権者がいる場合、その債権者に対し弁済等をしたことを証する書面 |
| 主な費用 | 登録免許税:申請1件につき一律3万円です。官報公告費用:掲載する行数にもよりますが、約3万円~15万円程度です。司法書士への報酬:手続きを依頼する場合、債権者保護手続も含むため10万円~15万円程度が相場です。 |
減資は、対外的に「会社の財産が減少した」と見なされ、信用力が低下するリスクも伴います。
手続きを進める際は、その目的と影響を十分に検討することが重要です。
まとめ
株式会社設立の資本金は、融資・税金・信用の観点から戦略的に決めることが成功の鍵です。
日本政策金融公庫の創業融資を有利に進めるには、自己資金と見なされる資本金は重要です。
また、資本金を1,000万円未満に設定すれば、消費税が最大2年間免除されるという大きな税制メリットがあります。
事業の安定性や取引先からの信用も考慮し、自社の計画に最適な金額を決定しましょう。



