個人事業主から合同会社への法人成りを検討中ですか?
最適なタイミングは、事業の利益が600万円〜800万円を超え、節税メリットが社会保険料の負担増を上回る時です。
この記事では、具体的な年商・利益の目安や税金シミュレーション、設立手順から事業引継ぎまでを網羅的に解説。
あなたの事業状況に合わせたベストな判断基準が明確にわかります。
個人事業主から合同会社の結論と要点
個人事業主として事業が順調に成長し、「法人成り」を考え始めたとき、株式会社と並んで有力な選択肢となるのが合同会社です。
設立コストを抑えつつ、法人格のメリットを享受できるため、多くのスモールビジネスオーナーに選ばれています。
しかし、どのタイミングで移行するのが最適なのか、判断に迷う方も少なくありません。
この章では、あなたが法人成りを検討する上で最も知りたい「ベストなタイミング」「年商・利益の目安」「税金や社会保険の具体的な変化」について、結論を先に分かりやすく解説します。
この記事を読み進めることで、ご自身の状況に合わせた最適な判断ができるようになります。
ベストタイミングの早見表
個人事業主から合同会社への移行を検討すべきタイミングは、利益水準、売上、事業計画など、複数の要素から総合的に判断します。
以下の表で、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
| 判断軸 | 検討を開始するサイン | 移行を強く推奨するサイン |
|---|---|---|
| 所得(利益) | 事業所得が500万円を超え始めた | 事業所得が安定して800万円を超えている(所得税と法人税の税率逆転が顕著になる) |
| 売上高(年商) | 課税売上高が1,000万円に近づいている | 2年前の課税売上高が1,000万円を超え、消費税の納税義務が発生した(新設法人として最大2年間の免税メリットを狙える) |
| 事業計画 | 融資や大型の設備投資を検討している | 従業員の採用を予定している、または社会的信用度が求められるBtoB取引を拡大したい |
| 節税・保障 | 役員報酬による所得分散や退職金の準備を考え始めた | 生命保険の法人契約や社宅制度など、より高度な節税策を活用したい(社会保険加入による将来の保障も重視) |
年商と利益の目安
法人成りを検討する上で最も分かりやすい指標が「利益」と「年商」です。
税金の観点から、具体的な目安が存在します。
利益については、個人事業の所得が500万円を超えたあたりから法人化のメリットが出始め、800万円を超えると多くの場合で法人の方が有利になります。
これは、個人の所得税が累進課税(所得が高いほど税率が上がる)であるのに対し、法人税の税率が一定であるため、ある利益水準を超えると税率が逆転するためです。
年商については、「1,000万円の壁」が重要なポイントです。個人事業主は、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。
しかし、新たに合同会社を設立すれば、原則として最大2年間は消費税が免除される可能性があります。
この免税メリットを最大限に活用するために、年商1,000万円を超えるタイミングで法人化を計画するケースが非常に多いです。
税金と社会保険の変化の概要
合同会社になると、お金の面で最も大きく変わるのが「税金」と「社会保険」です。
メリットとデメリットの両側面を理解しておくことが不可欠です。
| 項目 | 個人事業主 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 税金の種類 | 所得税、住民税、事業税、消費税 | 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税 (経営者個人には給与所得として所得税・住民税がかかる) |
| 社会保険 | 国民健康保険、国民年金(従業員5人未満は任意) | 健康保険、厚生年金保険(役員1人でも強制加入) |
| 経費(損金)の範囲 | 事業に関連する費用のみ | 事業関連費用に加え、経営者への給与(役員報酬)や退職金、生命保険料(一部)、社宅家賃(一部)なども損金にできる |
| 大きなメリット | 手続きがシンプル、赤字の場合の税負担が軽い | 役員報酬による所得分散や多様な経費計上による高い節税効果、社会的信用の向上 |
| 大きなデメリット | 節税策が限定的、社会的信用が法人に劣る | 社会保険料の会社負担分が発生しキャッシュフローを圧迫する可能性、赤字でも法人住民税(均等割)が発生する、事務負担の増加 |
このように、合同会社への移行は節税の選択肢を広げる一方で、社会保険料という新たな固定費が発生します。
これらの変化を踏まえ、ご自身の事業にとって本当にメリットがあるのか、慎重に見極めることが失敗しないための鍵となります。
個人事業主から合同会社にするメリットとデメリット

個人事業主から合同会社へ法人成りする際には、多くのメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。
節税効果や信用の向上といった魅力的な側面だけでなく、コストや事務負担の増加といった現実的な課題も理解し、ご自身の事業状況と照らし合わせて総合的に判断することが重要です。
ここでは、法人成りによる光と影を具体的に解説します。
節税と資金繰りのメリット
法人化を検討する最大の動機は「節税」でしょう。
個人事業主に適用される所得税と、法人に課される法人税の仕組みの違いを利用することで、手元に残るキャッシュを最大化できる可能性があります。
また、経費として認められる範囲が広がるため、資金繰りの改善にも繋がります。
役員報酬で所得分散
個人事業主の場合、事業で得た利益の全額が事業主個人の「事業所得」となり、所得が大きくなるほど税率が上がる累進課税が適用されます。
しかし、合同会社を設立すると、事業の利益を役員である自分自身への「役員報酬(給与)」として支払うことができます。
役員報酬は「給与所得」となり、経費の一種である「給与所得控除」が適用されるため、課税対象額を大きく圧縮できます。
例えば、所得が800万円の場合、個人事業主は800万円が課税対象のベースになりますが、法人から役員報酬800万円を受け取ると、190万円の給与所得控除が適用され、課税対象のベースは610万円にまで下がります。
さらに、配偶者や親族を役員に加え、それぞれに役員報酬を支払うことで、世帯全体での所得を分散できます。
一人に所得が集中するよりも、複数人に分散させた方が、それぞれに低い税率が適用されるため、世帯全体で納める所得税・住民税を大幅に軽減できるのです。
退職金や生命保険の活用
法人格を持つことで、個人事業主では認められない節税策が活用可能になります。
特に大きいのが、退職金と生命保険です。
- 役員退職金:個人事業主には退職金という概念がありませんが、法人の役員は退職金を受け取れます。役員退職金は会社の経費(損金)となり、法人税を圧縮します。受け取る側も「退職所得」として扱われ、勤続年数に応じた多額の「退職所得控除」が適用されるため、税負担が非常に軽いという大きなメリットがあります。将来の勇退に向けた資産形成と節税を両立できる、法人ならではの強力な制度です。
- 生命保険:法人名義で役員を被保険者とする生命保険に加入し、保険料の一部または全額を会社の経費(損金)に計上できます。これにより、節税しながら経営者の万が一の保障を確保したり、解約返戻金を将来の退職金の原資に充てたりすることが可能です。
社宅や旅費規程の活用
役員の生活に関連する費用の一部を経費化できるのも、法人化の大きなメリットです。
代表的なものに「社宅制度」と「旅費規程」があります。
- 社宅制度:会社名義で物件を賃貸契約し、役員に貸し出すことで、家賃の一部を会社の経費にできます。役員は会社に一定の賃料(賃料相当額)を支払う必要がありますが、個人で全額負担するよりも実質的な家賃負担を大幅に軽減できます。
- 旅費規程:出張に関するルールを「旅費規程」として定めておくことで、交通費や宿泊費の実費とは別に、役員に対して「出張日当」を支給できます。この日当は、会社にとっては経費(損金)となり、受け取った役員個人にとっては非課税所得となります。節税しながら役員の手取りを増やせる有効な手段です。
信用力や取引面のメリット
合同会社を設立し「法人格」を得ることは、税金面だけでなく、ビジネスの拡大においても大きなアドバンテージとなります。
個人事業主と比較して、社会的信用度が格段に向上するためです。
- 金融機関からの融資:事業拡大のための資金調達において、法人は個人事業主よりも有利な条件で融資を受けやすい傾向にあります。決算書によって経営状況が客観的に示されるため、金融機関が審査しやすくなるためです。
- 取引先の拡大:大企業の中には、コンプライアンスや与信管理の観点から「法人でなければ取引しない」という方針を持つ会社が少なくありません。法人化することで、これまで取引できなかった企業との新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。
- 人材採用:求人募集を行う際も、個人事業主より法人の方が応募者からの信頼を得やすく、優秀な人材を確保しやすくなります。社会保険が完備されている点も、求職者にとって大きな魅力となります。
デメリットと注意点
法人化には多くのメリットがある反面、必ず考慮すべきデメリットも存在します。
特に社会保険料の負担と事務的な手間の増加は、法人成り後のキャッシュフローや業務運営に直接影響を与えるため、事前の理解と準備が不可欠です。
社会保険の負担増
法人化した場合、たとえ社長一人だけの会社であっても、健康保険と厚生年金保険(総称して「社会保険」)への加入が法律で義務付けられています。
個人事業主時代の国民健康保険・国民年金と比較すると、保険料の総額が大幅に増加するケースがほとんどです。
保険料は会社と個人で折半して負担しますが、会社負担分も元は事業の利益から支払われるため、経営上のコスト増となります。
一方で、厚生年金に加入することで将来受け取る年金額が増えたり、病気やケガで働けなくなった場合に傷病手当金が支給されたりと、保障が手厚くなるというメリットもあります。
単なるコスト増と捉えるのではなく、福利厚生の充実という側面も考慮する必要があります。
| 個人事業主 | 合同会社(役員) | |
|---|---|---|
| 公的医療保険 | 国民健康保険(全額自己負担) | 健康保険(会社と個人で折半) |
| 公的年金 | 国民年金(全額自己負担・定額) | 厚生年金保険(会社と個人で折半・報酬比例) |
| 保障内容 | 比較的シンプル | 傷病手当金や出産手当金など保障が手厚い |
| 将来の年金 | 基礎年金のみ | 基礎年金+報酬比例の厚生年金 |
事務負担の増加
個人事業主の確定申告に比べ、法人の経理・労務・法務に関する事務作業は格段に複雑化し、量も増えます。
- 経理・税務:日々の記帳は複式簿記が必須となり、年に一度の決算では貸借対照表や損益計算書などの決算書を作成し、法人税申告書を提出する必要があります。これらは個人事業主の青色申告決算書よりも専門性が高く、税理士に依頼するのが一般的です。
- 労務:役員報酬の支払いや従業員を雇用した際の給与計算、年末調整、社会保険の加入・喪失手続きなど、人事労務に関する事務作業が発生します。
- 法務:役員の変更、本店の移転、事業目的の追加など、会社組織に変更があった場合は、その都度、法務局で変更登記の手続きが必要となり、登録免許税などの費用もかかります。これらの事務手続きを怠るとペナルティが課されることもあるため、正確な管理が求められます。
対外イメージと将来の上場不可
合同会社は設立コストが低く、経営の自由度が高いというメリットがある一方で、株式会社と比較した場合のデメリットも存在します。
- 対外的なイメージ:近年は有名外資系企業が合同会社の形態をとる例も増えましたが、依然として国内では株式会社の方が知名度・信頼性が高いと認識される傾向があります。特に伝統的な業界やBtoCビジネスでは、株式会社の方が有利に働く場面があるかもしれません。
- 上場(IPO)ができない:合同会社は株式を発行しないため、証券取引所に上場して広く一般から資金を調達することができません。将来的に事業を大きく成長させ、株式上場(IPO)を目指すビジョンがある場合は、最初から株式会社を選択するか、途中で合同会社から株式会社へ組織変更する必要があります。組織変更には手間とコストがかかるため、将来の事業計画をよく見据えて会社形態を選択することが重要です。
年商と利益の目安シミュレーション

個人事業主から合同会社への法人成りを検討する際、最も気になるのが「いつ、どのくらいの稼ぎで切り替えるのが得なのか?」という点でしょう。
この章では、具体的な「利益」と「年商」の金額を軸に、法人化のメリットがどのタイミングで出やすいのかをシミュレーションします。
税金や社会保険の負担を考慮した、実践的な判断基準を掴みましょう。
利益がいくらなら法人成りの効果が出やすいか
法人成りのタイミングを計る上で、年商(売上)よりも重要な指標が「利益(所得)」です。
これは、個人事業主にかかる「所得税」と、法人にかかる「法人税」の税率構造の違いに起因します。
個人の所得税は、利益が増えるほど税率が上がる「累進課税」です。
一方、法人税は利益の額にかかわらず税率がほぼ一定です。
そのため、ある利益のラインを超えると、個人の高い税率で納税するよりも、法人化して役員報酬と法人税に分けた方が、トータルの税負担が軽くなる「損益分岐点」が存在します。
ここでは、その目安となる2つの利益ラインについて詳しく解説します。
利益六百万円前後のライン
一般的に、法人化を検討し始める最初の目安として「利益600万円」という数字がよく挙げられます。
これは、個人の所得税率が20%(課税所得330万円超)になる領域に差し掛かり、法人税率との比較で有利になる可能性が出始めるためです。
ただし、この段階では注意が必要です。法人化すると社会保険への加入が義務となり、その負担が個人事業主時代の国民健康保険・国民年金よりも重くなるケースが多いためです。
税金のメリットよりも社会保険料の負担増が上回り、結果的に手残りが減ってしまう可能性も十分にあります。
したがって、利益600万円前後は「即座に法人化すべきライン」ではなく、「具体的なシミュレーションを開始すべき検討ライン」と捉えるのが適切です。
ご自身の状況で税理士などの専門家に試算を依頼し、メリット・デメリットを慎重に比較検討するスタート地点としましょう。
以下の表は、あくまで一例ですが、利益600万円の場合の個人事業主と合同会社(役員報酬480万円設定)の手残り額のイメージです。
| 項目 | 個人事業主 | 合同会社(役員報酬480万円) |
|---|---|---|
| 利益(所得) | 600万円 | 600万円 |
| 個人の税金・社会保険料 | 約165万円 | 約115万円(役員報酬から天引き) |
| 法人の税金・社会保険料 | – | 約100万円(法人負担の社会保険料含む) |
| 合計手残り(個人+法人) | 約435万円 | 約385万円 |
※前提:40歳未満・独身・東京都在住・青色申告特別控除65万円適用・その他控除は基礎控除のみ。法人の役員報酬は月額40万円(年480万円)とし、残りの120万円は法人利益とする。
あくまで概算であり、実際の金額は個別の状況により変動します。
利益八百万円以上のライン
法人化による税務上のメリットが明確になりやすいのが、利益が800万円を超えてくるラインです。
この水準になると、個人の所得税率は23%(課税所得695万円超)となり、累進課税による負担がかなり重くなってきます。
法人化して自身への役員報酬を例えば600万円程度に設定すると、個人の税率は低いまま抑えられます。
会社に残った利益(この場合200万円)には低い法人税率が適用されるため、「個人事業主として全額に高い所得税率で課税される」よりも「役員報酬と法人利益に分散して、それぞれ低い税率で課税される」方が、トータルの税負担を大きく軽減できる可能性が高まります。
さらに、役員報酬は「給与所得控除」の対象となるため、個人事業主の「事業所得」よりも課税対象額を圧縮できる効果もあります。
社会保険料の負担増を考慮しても、それを上回る節税効果を期待できるのがこのラインです。
| 項目 | 個人事業主 | 合同会社(役員報酬600万円) |
|---|---|---|
| 利益(所得) | 800万円 | 800万円 |
| 個人の税金・社会保険料 | 約240万円 | 約155万円(役員報酬から天引き) |
| 法人の税金・社会保険料 | – | 約115万円(法人負担の社会保険料含む) |
| 合計手残り(個人+法人) | 約560万円 | 約530万円 |
※前提は上記と同様。法人の役員報酬は月額50万円(年600万円)とし、残りの200万円は法人利益とする。
このシミュレーションでは手残り額がまだ個人有利に見えますが、法人に残ったお金は将来の退職金や設備投資に活用できるため、単純比較はできません。
役員社宅などの福利厚生を活用すれば、法人の実質的な手残りはさらに増加します。
年商一千万円と消費税の関係
利益と並んで、法人成りのタイミングを左右するもう一つの重要な指標が「年商(課税売上高)1,000万円」です。
これは消費税の納税義務に関わる、いわゆる「1,000万円の壁」です。
個人事業主は、原則として基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、その年から消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が生じます。
このタイミングをどう捉えるかが、法人化戦略の鍵となります。
基準期間と特定期間の判定
消費税の納税義務は、単純に「年商1,000万円を超えたら即発生」というわけではありません。
判定には2つの期間が用いられます。
- 基準期間:原則として、判定したい年の「前々年」の課税売上高で判定します。例えば、2025年に課税事業者になるかどうかは、2023年の課税売上高が1,000万円を超えているかで判定します。
- 特定期間:基準期間の売上が1,000万円以下でも、判定したい年の「前年」の上半期(1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その年から課税事業者になります。(※売上高の代わりに給与支払額で判定する方法もあります)
このルールにより、例えば開業1年目に年商1,200万円を達成した場合、課税事業者になるのはその2年後の3年目からとなります。
この「課税事業者になるまでのタイムラグ」を理解しておくことが重要です。
新設法人の免税判定とインボイスの実務
法人成りにおける消費税の最大のメリットは、「納税義務のリセット」にあります。
個人事業主としての売上は、新しく設立した法人には引き継がれません。
資本金1,000万円未満で設立された新設法人は、原則として設立1期目と2期目は消費税の免税事業者となります。
つまり、個人事業主として課税事業者になる直前のタイミングで合同会社を設立すれば、そこからさらに最大2年間、消費税の納税が免除される期間を作り出せるのです。
これは資金繰りにおいて非常に大きなメリットです。
ただし、2023年10月から開始されたインボイス制度により、この戦略は見直しが必要になりました。
免税事業者でいるということは、取引先が仕入税額控除に使えない「適格請求書(インボイス)」を発行できないことを意味します。
そのため、以下のような判断が求められます。
- BtoB取引が中心の場合:取引先からインボイスの発行を求められる可能性が非常に高いです。その場合、免税のメリットを捨てて、設立初年度から「適格請求書発行事業者の登録」を行い、あえて課税事業者になる選択が賢明です。
- BtoC取引が中心の場合:一般消費者はインボイスを必要としないため、免税事業者のままでいることのデメリットはほぼありません。この場合は、従来通り最大2年間の免税メリットを最大限に享受する戦略が有効です。
このように、年商1,000万円が見えてきたら、ご自身の事業モデル(BtoBかBtoCか)と取引先の状況を考慮し、消費税の免税メリットを享受するのか、あるいはインボイス対応を優先するのかを戦略的に判断した上で、法人成りのスケジュールを組むことが失敗しないためのポイントとなります。
税金の違いと節税ポイント

個人事業主から合同会社へ法人成りする最大の動機の一つが「節税」です。
しかし、単純に税率が下がるわけではなく、課される税金の種類やルールが根本的に変わります。
この違いを正確に理解し、法人ならではの節税ポイントを最大限に活用することが、法人化の成否を分けると言っても過言ではありません。
ここでは、個人事業主と合同会社で具体的にどの税金がどう変わるのか、そして合同会社だからこそ使える節税策を詳しく解説します。
所得税と法人税の違い
個人事業主の利益(所得)に対して課されるのが「所得税」、合同会社の利益(所得)に対して課されるのが「法人税」です。
この二つの税金は、税率の構造が大きく異なります。
個人事業主の所得税は、所得が増えれば増えるほど税率も高くなる「超過累進課税」が採用されています。
一方、法人税は資本金1億円以下の普通法人の場合、所得800万円を境に2段階の税率が適用される、比較的フラットな税率構造になっています。
| 課税所得金額 | 所得税率(個人) | 法人税率(法人) |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 15%(所得800万円以下の部分) |
| 195万円超〜330万円 | 10% | |
| 330万円超〜695万円 | 20% | |
| 695万円超〜900万円 | 23% | |
| 900万円超〜 | 33%〜 | 23.2%(所得800万円超の部分) |
※所得税には復興特別所得税が、法人税には地方法人税が別途課されます。
上記はあくまで比較のための概算税率です。
この表からもわかるように、所得が一定額(一般的に600万〜800万円)を超えると、個人の所得税率が法人税率を上回るため、法人化した方が税負担を抑えられる可能性が高まります。
損金算入できる範囲の違い
法人化の大きな節税メリットは、経費として認められる範囲(法人税法上は「損金」と呼びます)が広がることです。
個人事業主の「必要経費」と比べて、特に以下の項目が大きな違いとなります。
- 役員報酬:個人事業主は自分自身に給与を支払うことはできませんが、合同会社では経営者である自分自身に「役員報酬」を支払うことができます。この役員報酬は会社の損金となり、受け取った個人側では給与所得控除が適用されるため、所得を分散し、会社と個人のトータルでの税負担を軽減できます。
- 退職金:経営者自身や家族従業員(役員)に対して、退職金を支払うことができます。退職金は会社の損金になるだけでなく、受け取る側も税制上非常に優遇された「退職所得控除」が使えるため、大きな節税効果が期待できます。
- 生命保険料:経営者を被保険者とする生命保険や医療保険の保険料のうち、一定の要件を満たすものは全額または一部を会社の損金に算入できます。将来の保障を確保しながら、当期の法人税を圧縮することが可能です。
- 社宅:個人名義で借りている自宅を会社名義で借り上げ、役員社宅として利用することで、家賃の一部を会社の損金にできます。個人が負担する家賃も、一定の計算式に基づいた妥当な金額であれば給与として課税されないため、可処分所得を増やす効果があります。
住民税と事業税の違い
所得税と法人税だけでなく、地方税である住民税と事業税も個人と法人で異なります。
- 個人:所得に応じて課される「個人住民税」と、所得が290万円を超えた場合に課される「個人事業税」があります。
- 法人:会社の所得に応じて課される「法人住民税(所得割)」と「法人事業税」に加え、赤字であっても必ず支払わなければならない「法人住民税(均等割)」が発生します。
この「均等割」の存在が、法人を維持するための固定コストとなります。
均等割の最低額の目安
法人住民税の均等割は、会社の資本金の額と従業員数に応じて決まりますが、最も小規模な会社の場合でも納税義務が生じます。
資本金1,000万円以下、従業員50人以下の合同会社の場合、均等割の最低額は年間で合計7万円程度です。(都道府県民税2万円+市町村民税5万円)
これは利益が出ていなくても、つまり赤字決算でも毎年発生するコストです。
法人化を検討する際は、この固定費を支払ってもなおメリットがあるかどうかを慎重に判断する必要があります。
消費税とインボイス制度の対応
消費税は、法人成りにおいて非常に重要な論点です。
特に2023年10月から始まったインボイス制度により、戦略的な対応が求められるようになりました。
課税事業者選択と簡易課税
消費税の納税額は、原則として「預かった消費税(売上)-支払った消費税(仕入・経費)」で計算します(原則課税)。
一方で、基準期間(2期前)の課税売上高が5,000万円以下の場合、「簡易課税制度」を選択できます。
これは、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って納税額を計算する方法で、事務負担が軽減されるメリットがあります。
ただし、大きな設備投資などで支払った消費税が多い場合は、原則課税の方が有利になることもあります。
どちらを選択するかは、事業の実態に合わせて慎重に検討し、事前に届出を提出する必要があります。
免税の活用とデメリット
資本金1,000万円未満で設立した合同会社は、原則として設立1期目と2期目は消費税の納税が免除される「免税事業者」のメリットを享受できる可能性があります。
しかし、インボイス制度下ではこの考え方が通用しにくくなっています。
免税事業者のままでは、適格請求書(インボイス)を発行できず、取引先が仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。
これにより、取引を敬遠されたり、消費税分の値引きを要求されたりするリスクが生じます。
そのため、BtoB取引がメインの事業者は、設立当初から「適格請求書発行事業者」の登録申請を行い、あえて課税事業者を選択するケースがほとんどです。
免税メリットを享受できるのは、顧客が一般消費者(BtoC)中心の場合などに限定されるのが現状です。
源泉所得税と年末調整の実務
合同会社を設立し、自分に役員報酬を支払うようになると、会社は給与から所得税を天引き(源泉徴収)し、原則として翌月10日までに国に納付する義務を負います。
これを「源泉所得税」の納付といいます。
さらに、年末には役員や従業員の年間の所得税を精算する「年末調整」を行う必要があります。
個人事業主時代は自分の確定申告だけで完結していましたが、法人になると、会社としてこれらの手続きを行う事務負担が発生します。
税理士に依頼しない場合は、これらの手続きを自社で行うための知識と時間が必要になります。
交際費や役員給与のルール
法人化すると経費の範囲が広がる一方で、特定の費用については個人事業主時代よりも厳格なルールが課せられます。
- 交際費:個人事業主では事業関連性があれば上限なく経費にできましたが、法人(資本金1億円以下)の場合、損金にできる交際費には「年間800万円まで」または「飲食費の50%まで」という上限が設けられています。
- 役員給与:節税の要である役員報酬ですが、損金として認められるためには厳格なルールを守る必要があります。原則として、事業年度の途中で自由に金額を変更することはできず、毎月同じ額を支払う「定期同額給与」としなければなりません。もし事業年度の途中で利益が出たからといって、勝手に役員報酬を増額すると、その増額分は損金として認められないため、事業計画に基づいた慎重な金額設定が求められます。
これらのルールを理解せず安易に経費処理を行うと、税務調査で否認され、追徴課税を受けるリスクがあるため注意が必要です。
社会保険の加入要件と負担の試算

個人事業主から合同会社へ法人成りする際、最も大きな変化の一つが社会保険です。
これまで国民健康保険と国民年金に加入していた方も、法人化すると原則として健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられます。
ここでは、その加入要件や保険料の負担、そして将来得られるメリットについて詳しく解説します。
合同会社の社会保険加入の義務
個人事業主の場合、従業員が5人未満であれば社会保険への加入は任意でした。
しかし、合同会社を設立すると、たとえ社長一人だけの会社であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられます。
これは「強制適用事業所」となるためです。
役員報酬を受け取る代表社員(社長)は、被保険者として加入しなければなりません。
もし従業員を雇用する場合も、正社員はもちろん、パートやアルバ’イトであっても週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば、加入義務が発生します。
法人設立後は、速やかに管轄の年金事務所へ「新規適用届」や「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
保険料の負担とキャッシュフロー
社会保険料は、毎月の役員報酬や給与を基に算出される「標準報酬月額」に、定められた保険料率を掛けて計算されます。
そして、算出された保険料を会社と個人(役員・従業員)が半分ずつ負担(労使折半)するのが大きな特徴です。
会社が負担する分の保険料は、経費(損金)として「法定福利費」に計上できるため、法人税の節税に繋がります。
一方で、個人負担分は役員報酬から天引きされ、会社負担分は会社の経費となるため、法人全体のキャッシュフローに与える影響は小さくありません。
役員報酬を決める際は、この社会保険料負担も考慮した資金繰り計画が不可欠です。
以下に、役員報酬額に応じた社会保険料の負担額の目安を試算します。(東京都、40歳未満、令和6年度の保険料率で計算)
| 役員報酬(月額) | 標準報酬月額 | 健康保険料(合計) | 厚生年金保険料(合計) | 合計保険料 | 個人負担額 | 会社負担額(法定福利費) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000円 | 300,000円 | 約29,940円 | 54,900円 | 約84,840円 | 約42,420円 | 約42,420円 |
| 400,000円 | 410,000円 | 約40,918円 | 74,040円 | 約115,758円 | 約57,879円 | 約57,879円 |
| 500,000円 | 500,000円 | 約49,900円 | 91,500円 | 約141,400円 | 約70,700円 | 約70,700円 |
※健康保険料率は都道府県ごとに異なります。40歳以上の場合は介護保険料が上乗せされます。賞与からも同様に保険料が徴収されます。
将来の年金や保障のメリット
保険料の負担は増えますが、その分、個人事業主時代の国民年金・国民健康保険にはない手厚い保障を受けられるのが社会保険の大きなメリットです。
将来の年金額が増える
国民年金(基礎年金)に加えて、報酬額に比例した厚生年金が上乗せされるため、将来受け取れる年金額が大幅に増えます。
これは老後の生活の安定に直結する重要なポイントです。
手厚い医療保障と手当金
健康保険に加入することで、医療費の自己負担が3割になる点は国民健康保険と同じですが、それに加えて以下のような手厚い保障があります。
- 傷病手当金:業務外の病気やケガで連続4日以上働けなくなった場合、給与(標準報酬日額)の約3分の2が最長1年6ヶ月にわたって支給されます。収入が途絶えるリスクに備えられる、フリーランスにはない強力なセーフティネットです。
- 出産手当金:産休中に給与が支払われない場合に、傷病手当金と同様の金額が支給されます。
扶養家族の保険料が不要に
個人事業主が加入する国民健康保険には「扶養」の概念がなく、家族の人数分だけ保険料が増えるのが一般的です。
しかし、会社の健康保険では、一定の収入基準(年収130万円未満など)を満たす配偶者や子供、両親などを扶養に入れることができます。
扶養に入った家族の分の健康保険料はかからないため、家族がいる方にとっては非常に大きなメリットとなります。
ベストタイミングの判断軸

個人事業主から合同会社への法人成りは、単に「利益がいくらになったから」という税金の損益分岐点だけで決めるべきではありません。
事業の成長ステージや将来の展望、外部環境の変化など、複数の判断軸を組み合わせて総合的に判断することが、成功の鍵を握ります。
ここでは、あなたの事業にとって最適なタイミングを見極めるための具体的な判断軸を解説します。
契約や資金調達の予定がある時
事業を拡大する上で、取引先からの信用や金融機関からの資金調達は不可欠です。
これらが具体的に必要となった時が、法人化を検討する絶好のタイミングと言えます。
個人事業主のままでは、大手企業との取引や公的機関の入札などで「法人格」が契約の必須条件となっているケースで、ビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。
法人格である合同会社になることで、社会的信用度が格段に向上し、取引の門戸が大きく広がります。
また、資金調達の面でも法人は有利です。金融機関は、個人の資産と事業の資産が明確に分離されている法人の方を、経理の透明性が高いと評価します。
日本政策金融公庫の新創業融資制度などを活用する際も、しっかりとした事業計画書とともに法人として申し込むことで、融資審査がスムーズに進む傾向にあります。
大規模な融資や重要な取引契約を具体的に計画している場合、その申し込みの数ヶ月前には設立手続きを完了させ、法人口座を開設しておくのが理想的なスケジュールです。
大型投資や採用の前に切り替える判断
事業の成長に伴う設備投資や人材採用は、法人成りの大きな動機となります。
これらの計画が具体化したタイミングで切り替えることで、税務上・労務上のメリットを最大限に享受できます。
例えば、高額な機械やソフトウェア、業務用車両などの大型投資を検討している場合、法人であれば欠損金の繰越控除期間が10年間(個人事業主は3年間)と長くなります。
投資初年度に大きな赤字(欠損金)が出ても、それを翌年以降10年間の黒字と相殺できるため、長期的な視点で節税効果を高めることができます。
従業員の採用を考えている場合も、法人化は重要な判断軸です。
法人になると、代表者1名からでも社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。
これは一見コスト増に見えますが、求職者にとっては福利厚生が充実している証となり、採用競争において大きなアドバンテージとなります。
優秀な人材を確保したい、従業員に安心して働いてもらいたいという思いがあるなら、採用活動を本格化させる前に法人成りし、社会保険制度を整備しておくことが賢明な判断です。
決算期の設定とスケジュール
合同会社は、株式会社と同様に決算月を自由に設定できます。
このメリットを活かし、戦略的に設立時期を決めることで、設立後の業務負担を大幅に軽減できます。
忙しくない時期に設立
個人事業主としての事業の繁忙期と、法人設立の手続き期間が重ならないように調整することが極めて重要です。
定款の作成・認証、登記申請、税務署や年金事務所への各種届出など、設立には多くの手続きが必要で、通常1ヶ月程度の期間を要します。
例えば、建設業であれば年度末の3月、小売業であれば年末商戦の12月は避けるべきです。
自社の事業サイクルを把握し、比較的業務が落ち着いている時期を設立準備期間に充てることで、本業に支障をきたすことなく、スムーズに法人化を進めることができます。
確定申告と決算の二重対応を避ける工夫
法人成りした初年度は、個人事業主としての廃業手続きと確定申告、そして新設法人の経理処理という2つの作業が発生します。
この負担を避けるため、設立日の設定には工夫が必要です。
最も避けたいのは、年末(11月〜12月)に法人を設立するケースです。
この場合、翌年の2月〜3月にかけて、前年分の個人の確定申告と、設立したばかりの法人の経理体制の構築が重なり、非常に煩雑になります。
おすすめは、個人事業主の確定申告が終わった直後(3月下旬〜4月)や、年明けすぐ(1月)に法人を設立することです。
例えば1月15日に法人を設立した場合、その年の個人事業の事業期間は1月1日〜14日までのわずか14日間となり、確定申告の計算が非常に楽になります。
法人の第1期決算は翌年になるため、事務作業の時期を分散させることが可能です。
消費税の課税事業者判定を味方にする
消費税は、法人成りのタイミングを決定する上で最も重要な税務戦略の一つです。
うまく活用すれば、最大で2年間、消費税の納税が免除される可能性があります。
個人事業主は、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、その年から消費税の課税事業者となり、消費税を納める義務が生じます。
この仕組みを利用し、個人事業主として課税事業者になる直前のタイミングで法人成りするのが、節税効果を最大化するベストタイミングです。
具体例を見てみましょう。
| 期間 | 状況 | 消費税の納税義務 |
|---|---|---|
| 2023年(基準期間) | 個人事業主として課税売上高が1,200万円になる | 免税事業者 |
| 2024年 | 個人事業主として事業を継続 | 免税事業者 |
| 2025年1月1日 | このタイミングで合同会社を設立(法人成り) | (個人事業は廃業するため納税義務なし) |
| 2025年(法人1期目) | 新設法人として事業運営 | 原則、免税事業者 |
| 2026年(法人2期目) | 新設法人として事業運営 | 原則、免税事業者 |
上記の例では、個人事業主のままなら2025年から課税事業者になるところを、法人成りすることで納税を回避し、さらに新設法人として2025年、2026年の2年間、消費税の免税メリットを享受できる可能性があります。
ただし、注意点もあります。
資本金が1,000万円以上の場合や、特定期間(前事業年度の開始から6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、2期目から課税事業者になる可能性があります。
また、インボイス制度(適格請求書等保存方式)に登録すると、免税事業者であっても課税事業者として扱われます。
自社の取引環境や将来の売上予測を踏まえ、税理士などの専門家と相談しながら最適なタイミングを慎重に判断しましょう。
設立手順と必要書類
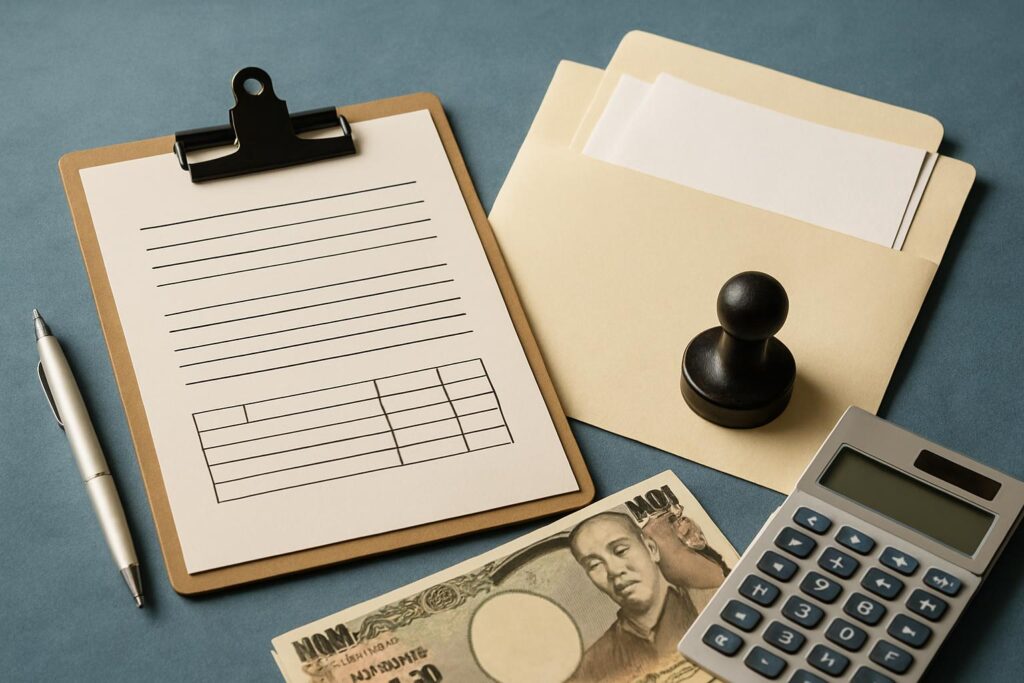
個人事業主から合同会社への法人成りは、株式会社に比べて手続きがシンプルで費用も抑えられるのが魅力です。
しかし、会社を法的に設立し、事業を円滑に開始するためには、定められた手順を正確に踏む必要があります。
ここでは、合同会社設立の具体的な流れから、設立後に必須となる各種届出までを詳しく解説します。
手続きの全体像を把握し、漏れなく準備を進めましょう。
合同会社設立の流れ
合同会社の設立は、大きく分けて
- 「基本事項の決定」
- 「定款の作成・認証」
- 「出資金の払込」
- 「登記申請」
- 「設立後の届出」
という5つのステップで進みます。
特に、会社の憲法ともいえる定款の作成と、法務局への登記申請が中心的な手続きとなります。
定款作成と電子定款
定款(ていかん)とは、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めた書類です。
合同会社の設立には、まずこの定款を作成する必要があります。
定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商号 | 会社の名称です。前後に「合同会社」という文字を入れる必要があります。 |
| 事業目的 | 会社がどのような事業を行うかを具体的に記載します。将来行う可能性のある事業も記載しておくと、後々の変更手続きが不要になります。 |
| 本店所在地 | 会社の住所です。最小行政区画(例:東京都新宿区)までの記載でも可能ですが、番地まで記載するのが一般的です。 |
| 社員の氏名及び住所 | 出資者(社員)全員の情報を記載します。 |
| 社員全員が有限責任社員である旨 | 合同会社の特徴である、出資額の範囲内でのみ責任を負うことを明記します。 |
| 社員の出資の目的及びその価額 | 各社員が金銭でいくら出資するのか、または現物出資する資産とその評価額を記載します。 |
定款は紙で作成する方法と、PDFファイルで作成する「電子定款」があります。
電子定款で作成すれば、紙の定款で必要となる4万円の収入印紙が不要になるという大きなメリットがあります。
電子定款の作成にはマイナンバーカードやICカードリーダーライタなどが必要ですが、司法書士などの専門家に依頼すれば、これらの機材がなくても電子定款の恩恵を受けられます。
出資と資本金の決め方
定款を作成したら、次に出資金(資本金)を払い込みます。
この手続きは、定款作成後、登記申請前に行います。
会社設立前なので、法人口座はまだありません。
そのため、発起人(代表社員)個人の銀行口座に出資者全員が資本金を振り込みます。
振込が完了したら、その口座の通帳の表紙、裏表紙、そして振込が記帳されたページをコピーします。
このコピーと、代表社員が作成した「払込証明書」を合わせて、出資金が正しく払い込まれたことの証明書類とします。
資本金は法律上1円から設立可能ですが、会社の信用度や初期の運転資金を考慮して設定することが重要です。
一般的には、初期費用や当面の運転資金として3ヶ月分程度の金額を目安にするとよいでしょう。
登記申請と法務局での手続き
出資金の払込が完了したら、いよいよ法務局で設立登記の申請を行います。
この登記申請日が、会社の設立日となります。
申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
登記申請に必要な主な書類は以下の通りです。
事案によって異なる場合があるため、事前に法務局のウェブサイトで確認するか、専門家に相談することをおすすめします。
- 合同会社設立登記申請書
- 定款(電子定款または紙の定款)
- 代表社員の印鑑証明書
- 払込証明書
- 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面(定款で定めていない場合)
- 印鑑届書(会社の代表印を登録するための書類)
申請方法は、法務局の窓口に持参するほか、郵送やオンライン(登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと」)でも可能です。
申請後、1週間から10日ほどで登記が完了し、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が取得できるようになります。
設立費用の相場
合同会社の設立には、法定費用と呼ばれる必ずかかる費用と、専門家に依頼した場合の報酬が発生します。
自分で手続きを行うか、専門家に依頼するかで総額は変わってきます。
登録免許税や収入印紙
法定費用は、手続きを自分で行った場合にかかる最低限のコストです。
電子定款を利用するかどうかで金額が大きく変わります。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の額 × 0.7% (最低6万円) | 登記申請時に法務局へ納付します。資本金が約857万円以下であれば、一律6万円です。 |
| 定款認証手数料 | 0円 | 株式会社と異なり、合同会社は公証役場での定款認証が不要です。 |
| 定款に貼る収入印紙代 | 4万円(紙の定款の場合) 0円(電子定款の場合) | 電子定款にすることで4万円の節約が可能です。 |
| 合計(最低額) | 6万円~10万円 | 電子定款なら6万円、紙定款なら10万円が最低限の法定費用となります。 |
この他に、会社の実印や銀行印などの印鑑作成費用(1万円~3万円程度)、代表社員の印鑑証明書取得費用(1通300円程度)などがかかります。
司法書士や行政書士に依頼する費用
設立手続きを司法書士や行政書士などの専門家に依頼する場合、上記の法定費用に加えて専門家への報酬が必要になります。
報酬の相場は5万円から10万円程度です。
一見、費用が高くなるように感じますが、多くの専門家は電子定款に対応しています。
そのため、自分で紙の定款を作成する場合(法定費用10万円)と比較して、専門家に依頼した方が(法定費用6万円+報酬)、結果的に総額が安くなるケースや、同程度の費用で手間を大幅に削減できるケースも少なくありません。
手続きの確実性や時間を考慮すると、専門家への依頼は有力な選択肢です。
設立後に必須の届出
法務局での登記が完了しても、手続きは終わりではありません。
事業を始めるためには、税務署や年金事務所など、各官公庁へ事業開始の届出を行う必要があります。
これらの届出を怠ると、税金の優遇措置が受けられなくなったり、罰則の対象となったりする可能性があるため、必ず期限内に行いましょう。
税務署への各種届出
会社の設立後は、本店所在地を管轄する税務署へ以下の書類を提出します。
特に青色申告の承認申請は、節税の観点から非常に重要です。
| 届出書類名 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 | 必須の届出です。定款のコピーや登記簿謄本などを添付します。 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立後3ヶ月を経過した日か、第1期事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで | 欠損金の繰越控除など、税制上の多くのメリットを受けるために必須です。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 事務所開設から1ヶ月以内 | 役員報酬や従業員給与を支払う場合に提出します。 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 適用を受けたい月の前月末まで | 従業員が常時10人未満の場合、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる特例です。 |
これらの届出は、都道府県税事務所と市区町村役場にも必要です(通常、税務署に提出すれば連携されますが、自治体によっては別途提出が必要な場合があります)。
日本年金機構とハローワークの手続き
法人は、社長1人であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。
また、従業員を雇用する場合は労働保険(雇用保険・労災保険)の手続きも必要です。
- 社会保険(健康保険・厚生年金):設立から5日以内に、管轄の年金事務所へ「新規適用届」や「被保険者資格取得届」を提出します。
- 労働保険(労災保険・雇用保険):従業員を雇用した場合、まず労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」を提出し、その後ハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」などを提出します。
法人口座開設とGビズID
個人事業とは異なり、法人では個人のお金と会社のお金を明確に区別する必要があります。
そのため、会社の設立登記が完了したら、速やかに法人口座を開設しましょう。
メガバンク、地方銀行、ネット銀行などで開設できますが、近年は審査が厳格化しており、登記簿謄本や事業計画書の提出を求められることもあります。
審査には数週間かかる場合もあるため、早めに準備を始めることが肝心です。
また、今後の事業運営の効率化のために「GビズID」の取得も強く推奨します。
GビズIDは、社会保険手続きや各種補助金の電子申請など、様々な行政サービスに1つのアカウントでログインできる仕組みです。
無料で取得でき、今後の手続きの手間を大幅に削減できるため、設立後の早い段階で取得しておきましょう。
個人事業から合同会社への事業移管と会計処理

個人事業主から合同会社への移行、いわゆる「法人成り」は、単に会社を設立して登記すれば完了というわけではありません。
最も重要かつ複雑なのが、これまで個人で営んできた事業の資産や負債を、新しく設立した法人へ適切に引き継ぐ「事業移管」のプロセスです。
この手続きを正確に行わないと、後々税務上の問題が発生したり、会計処理が混乱したりする原因となります。
ここでは、スムーズな事業移管を実現するための具体的な方法と会計処理のポイントを詳しく解説します。
資産や負債の引き継ぎ方法
個人事業で使っていた資産(現金、預金、売掛金、商品、PC、車両、不動産など)や、負債(買掛金、借入金など)を法人に引き継ぐ方法は、主に「現物出資」「売買(譲渡)」「賃貸借」の3つがあります。
どの方法を選択するかによって、手続きの煩雑さや税務上の扱いが大きく異なるため、自社の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。
一般的には「現物出資」か「売買(譲渡)」が選択されるケースが多く見られます。
現物出資と譲渡の違い
現物出資と売買(譲渡)は、資産を法人に移管する代表的な方法です。
それぞれの特徴を理解し、メリット・デメリットを比較検討しましょう。
現物出資とは、現金ではなく個人事業で使っていた資産(PC、車両、商品など)を資本金として出資する方法です。
手元に現金がなくても資本金を増やせるメリットがありますが、手続きがやや複雑になります。
売買(譲渡)とは、個人事業主が法人に対して資産を売却する方法です。
個人と法人の間で売買契約書を交わすことで手続きが完了するため、比較的シンプルです。
ただし、法人側は資産を買い取るための資金を用意する必要があります。
両者の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 現物出資 | 売買(譲渡) |
|---|---|---|
| 概要 | 個人資産を資本金として出資する | 個人資産を法人に売却する |
| 手続き | 定款への記載、財産引継書、資本金の額の計上に関する証明書などが必要。原則として検査役の調査が必要だが、価額500万円以下などの要件を満たせば不要。 | 個人と法人で売買契約書を締結する。手続きは比較的シンプル。 |
| 資金 | 法人側に購入資金が不要。 | 法人側に購入資金が必要。個人から法人への貸付金として処理することも可能。 |
| 税金(個人側) | 原則として非課税。 | 譲渡する資産によっては譲渡所得が発生し、所得税・住民税が課税される可能性がある。 |
| メリット | 現金がなくても資本金を増やせる。 | 手続きが分かりやすい。 |
| デメリット | 手続きが複雑で、専門家のサポートが必要になる場合がある。 | 法人に買取代金が必要。個人に譲渡所得税がかかるリスクがある。 |
固定資産や在庫の扱い
事業で使っていたPCや車両、ソフトウェアなどの固定資産や、商品・原材料といった在庫(棚卸資産)の引き継ぎには特に注意が必要です。
これらの資産は、原則として「時価」で評価して法人へ引き継がなければなりません。
時価が適正でないと、税務署から個人から法人への寄付とみなされ、法人側に受贈益が認定されたり、個人側にみなし譲渡所得が課税されたりするリスクがあります。
固定資産の引き継ぎ
中古市場の価格や専門家の鑑定などを参考に、客観的な時価を設定します。
引き継いだ法人は、その時価を新たな取得価額として減価償却を行っていきます。
個人の減価償却未済額をそのまま引き継ぐわけではない点に注意してください。
在庫(棚卸資産)の引き継ぎ
在庫は、原則として通常の販売価額で引き継ぎます。
これにより、個人事業の最後の決算で売上として計上され、法人はその価額で期首商品棚卸高として計上します。
実務上は、手続きの簡便さから仕入価額(帳簿価額)で引き継ぐケースもありますが、その場合でも税務上の妥当性を説明できるようにしておくことが望ましいでしょう。
売掛金や買掛金の引継ぎの注意点
売掛金や買掛金といった債権・債務の引き継ぎは、取引先との関係に直接影響するため、慎重に進める必要があります。
売掛金の引き継ぎ
売掛金を引き継ぐ場合、債務者である取引先に対して、債権者が個人から法人へ変更されたことを通知し、承諾を得ることが不可欠です。
これを怠ると、取引先が引き続き個人名義の口座に代金を振り込んでしまい、入金管理が煩雑になるだけでなく、取引上のトラブルに発展する可能性もあります。
実務的には「債権譲渡通知書」を送付するか、今後の請求書の名義を法人に変更し、振込先口座も法人口座に切り替える旨を丁寧に案内します。
買掛金・借入金の引き継ぎ
買掛金や借入金などの債務を引き継ぐ場合も同様に、債権者である仕入先や金融機関の承諾が必要です。
特に、金融機関からの事業用融資を引き継ぐ場合は、改めて法人の事業計画や財務状況に基づく審査が行われます。
個人の信用で受けていた融資が、法人になったからといって必ずしも引き継げるわけではないため、事前に金融機関へ相談しておくことが重要です。
承認が得られない場合は、個人で返済を続けるか、法人として新たに融資を申し込むことになります。
開業廃業等届出書と青色申告の取りやめ
合同会社を設立し、事業を完全に法人へ移管した場合、個人事業は廃業扱いとなるため、関連する手続きを忘れずに行う必要があります。
個人事業の廃業手続き
事業を廃止した日から1ヶ月以内に、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)」を提出します。
この届出をしないと、個人事業が継続しているとみなされ、確定申告の案内が届き続けるなど、混乱の原因となります。
青色申告の取りやめ手続き
青色申告を行っていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出が必要です。
提出期限は、青色申告をやめることとなる年の翌年3月15日までです。
例えば、2024年中に法人成りして個人事業をやめた場合、2025年3月15日までに提出します。
その他、個人事業で消費税の課税事業者であった場合は「事業廃止届出書」、従業員を雇用していた場合は労働基準監督署やハローワークへの関連書類の提出も必要になります。
家族従業員の給与と役員への移行
個人事業主時代に家族を「青色事業専従者」として雇用し、給与を支払っていた場合、法人成りによってその位置づけが大きく変わります。
個人事業の「青色事業専従者給与」は、あくまでも個人事業主の所得から控除される経費の一種です。
一方、法人成りした後は、その家族を「役員」とするか「従業員」とするかを選択することになります。
役員にする場合
家族を合同会社の業務執行社員(役員)に就任させ、「役員報酬」を支払う形が一般的です。役員報酬は、定期同額給与などの要件を満たせば法人の経費(損金)にできます。
しかし、最も大きな変化は、役員になると原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられることです。
これにより、保険料の法人負担と個人負担が発生し、世帯全体での手取り額やキャッシュフローに大きな影響を与えます。
従業員として雇用する場合
役員ではなく、一般の従業員として法人と雇用契約を結ぶことも可能です。
この場合は「給与」として支払われ、労働時間などの条件によっては社会保険の加入義務が発生します。
青色事業専従者から役員へ移行する場合、社会保険料の負担増は避けられませんが、将来受け取る年金額が増えるというメリットもあります。
どちらの選択が最適か、税金と社会保険の両面からシミュレーションすることが失敗しないための鍵となります。
ケーススタディ

個人事業主から合同会社への法人成りを検討する際、最も気になるのが「自分の場合は具体的にどう変わるのか?」という点でしょう。
ここでは、職種や事業規模が異なる3つのモデルケースを取り上げ、税金や社会保険料、そして最終的な手残りがどう変化するのかを具体的にシミュレーションします。
※以下のシミュレーションは、各種控除を簡略化し、特定の年度の税率・保険料率を基にした概算です。あくまで判断の目安としてご覧いただき、正確な金額は必ず税理士などの専門家にご相談ください。
フリーランスエンジニア 年商一千二百万円 利益七百万円の場合
インボイス制度を機に法人化を検討している、経験豊富なフリーランスエンジニアのケースです。
年商1,000万円を超えており、利益も700万円と法人化のメリットが出やすい水準にあります。
ここでは役員報酬を540万円(月45万円)に設定した場合を想定します。
| 項目 | 個人事業主のままの場合 | 合同会社を設立した場合 |
|---|---|---|
| 売上 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 経費 | 500万円 | 500万円 |
| 個人の所得 | 700万円(事業所得) | 540万円(給与所得) |
| 会社の利益 | – | 160万円(売上-経費-役員報酬) |
| 税金合計(概算) | 約205万円 (所得税・住民税・事業税) | 約141万円 (法人税等 約38万円 + 個人の所得税・住民税 約103万円) |
| 社会保険料(概算) | 約120万円 (国民健康保険・国民年金) | 約158万円 (会社負担 約79万円 + 個人負担 約79万円) |
| 手取り相当額(年間) | 約375万円 (所得 – 税金 – 社会保険料) | 約440万円 (役員手取り 約358万円 + 会社内部留保 約122万円) |
このケースでは、社会保険料の負担は年間で約38万円増加しますが、税金の負担が約64万円も減少します。
結果として、個人が自由に使えるお金(役員手取り)と会社に残るお金(内部留保)を合わせた「手取り相当額」は、年間で約65万円も増加する計算になります。
所得700万円という水準は、所得税率が23%に達するラインであり、役員報酬として給与所得控除を活用し、残りを低い法人税率が適用される会社の利益として残すことで、大きな節税効果が生まれます。
将来の厚生年金受給額が増えるというメリットも考慮すると、このエンジニアにとっては法人化が非常に有効な選択肢と言えるでしょう。
EC事業者 年商三千万円 利益六百万円の場合
オンラインストアを運営し、売上は順調に伸びているものの、仕入れや広告費がかさみ利益は600万円にとどまっているEC事業者のケースです。
今後の融資による事業拡大や従業員雇用を見据え、社会的信用力を高めるために法人化を検討しています。
役員報酬は480万円(月40万円)とします。
| 項目 | 個人事業主のままの場合 | 合同会社を設立した場合 |
|---|---|---|
| 売上 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 経費 | 2,400万円 | 2,400万円 |
| 個人の所得 | 600万円(事業所得) | 480万円(給与所得) |
| 会社の利益 | – | 120万円(売上-経費-役員報酬) |
| 税金合計(概算) | 約155万円 (所得税・住民税・事業税) | 約107万円 (法人税等 約28万円 + 個人の所得税・住民税 約79万円) |
| 社会保険料(概算) | 約105万円 (国民健康保険・国民年金) | 約140万円 (会社負担 約70万円 + 個人負担 約70万円) |
| 手取り相当額(年間) | 約340万円 (所得 – 税金 – 社会保険料) | 約365万円 (役員手取り 約340万円 + 会社内部留保 約92万円) |
利益600万円のラインでは、税金の減少額(約48万円)と社会保険料の増加額(約35万円)が拮抗し始めますが、それでも手取り相当額は年間で約25万円増加します。
短期的な金銭メリットは先のエンジニアの例ほど大きくありませんが、このケースで重要なのは金銭以外のメリットです。
法人格を得ることで、金融機関からの融資が受けやすくなったり、大口の仕入先との取引条件が有利になったりする可能性があります。
また、従業員を雇用する際にも、社会保険を完備している法人の方が魅力的に映り、優秀な人材を確保しやすくなります。
事業のさらなる成長を目指すフェーズにおいては、目先の損得だけでなく、信用力向上という大きなメリットを享受するために法人化する価値は十分にあると言えます。
コンサルタント 年商八百万円 利益五百万円の場合
専門知識を活かして活動するコンサルタントで、経費は比較的少ないものの、売上・利益ともに法人化のボーダーライン上にいるケースです。
法人化すべきかタイミングを計っています。仮に役員報酬を420万円(月35万円)に設定したとします。
| 項目 | 個人事業主のままの場合 | 合同会社を設立した場合 |
|---|---|---|
| 売上 | 800万円 | 800万円 |
| 経費 | 300万円 | 300万円 |
| 個人の所得 | 500万円(事業所得) | 420万円(給与所得) |
| 会社の利益 | – | 80万円(売上-経費-役員報酬) |
| 税金合計(概算) | 約115万円 (所得税・住民税・事業税) | 約82万円 (法人税等 約19万円 + 個人の所得税・住民税 約63万円) |
| 社会保険料(概算) | 約90万円 (国民健康保険・国民年金) | 約123万円 (会社負担 約61.5万円 + 個人負担 約61.5万円) |
| 手取り相当額(年間) | 約295万円 (所得 – 税金 – 社会保険料) | 約296万円 (役員手取り 約235.5万円 + 会社内部留保 約61万円) |
このシミュレーションでは、手取り相当額はほぼ変わりません。
税金は約33万円減少しますが、社会保険料が約33万円増加するため、金銭的なメリットはほとんど相殺されてしまいます。
利益500万円前後の水準では、社会保険料の負担増が重くのしかかり、単純な節税目的での法人化は必ずしも得策ではないことがわかります。
ただし、取引先が法人に限定されている場合や、個人の資産と事業の資産を明確に分離したいという強い要望がある場合は、法人化を検討する意味があります。
また、社宅制度を導入して家賃の一部を経費化するなど、役員報酬以外の節税策を組み合わせることでメリットを出せる可能性もあります。
この段階では焦って法人化するのではなく、まずは利益を600万円以上に伸ばすことを目指し、その上で再度シミュレーションを行うのが賢明な判断と言えるでしょう。
よくある質問

個人事業主から合同会社への法人成りに関して、多くの方が抱く疑問について、一問一答形式で詳しく解説します。
設立前後の不安や具体的な手続きの疑問をここで解消しましょう。
合同会社から株式会社への組織変更は可能か
はい、合同会社から株式会社へ組織変更することは法律上可能です。
将来的に事業を拡大し、株式上場(IPO)を目指す場合や、より高い社会的信用力が必要になった際に選択肢となります。
組織変更を行うには、以下の手続きが必要です。
- 組織変更計画の作成: 商号、事業目的、役員構成、発行可能株式総数などを定めます。
- 総社員の同意: 全ての社員(出資者)から組織変更に対する同意を得る必要があります。
- 債権者保護手続き: 官報公告や個別の催告を行い、債権者が異議を申し立てる期間(1ヶ月以上)を設けます。
- 登記申請: 効力発生日から2週間以内に、合同会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に法務局へ申請します。
ただし、手続きは煩雑で、登録免許税(最低でも6万円)や官報公告費用などのコストもかかります。
そのため、設立当初から将来的な上場の可能性が少しでもある場合は、最初から株式会社を選択することも検討する価値があります。
資本金はいくらにすべきか
会社法上、資本金は1円以上で合同会社を設立できます。
しかし、現実的には事業の初期費用や当面の運転資金を考慮して設定することが重要です。
一般的には100万円から300万円程度で設立するケースが多く見られます。
資本金額を決める際の主な判断基準は以下の通りです。
| 判断基準 | 解説 |
|---|---|
| 対外的な信用力 | 資本金の額は、会社の体力や規模を示す指標の一つです。金融機関からの融資や大手企業との取引を考えている場合、あまりに少額だと信用面で不利になる可能性があります。 |
| 初期費用と運転資金 | 設立費用(登録免許税など)に加え、少なくとも3ヶ月から6ヶ月程度の運転資金(家賃、仕入費用、役員報酬など)を賄える額を資本金として準備するのが理想的です。 |
| 許認可の要件 | 建設業や人材派遣業など、特定の事業を行うためには、許認可の要件として最低資本金額が定められている場合があります。事前に必ず確認しましょう。 |
| 消費税の免税 | 資本金を1,000万円未満にすることで、原則として設立から最大2年間、消費税の納税が免除される可能性があります。節税面で大きなメリットです。 |
自己資金の範囲で、事業計画に基づいた適切な金額を設定することが失敗しないポイントです。
赤字でも合同会社にする意味はあるか
事業が赤字の見込みであっても、法人成りするメリットは存在します。
特に、長期的な視点で事業を継続する意思がある場合には、赤字でも合同会社を設立する価値は十分にあります。
主なメリットは以下の通りです。
- 欠損金の繰越控除: 法人税法では、事業で生じた赤字(欠損金)を最大10年間繰り越すことができます。将来的に事業が黒字化した際に、過去の赤字と相殺して法人税の負担を軽減できます。(個人事業主の青色申告では繰越期間は3年間です)
- 社会的信用の維持: 赤字決算であっても「法人」というだけで、個人事業主よりも取引先や金融機関からの信用を得やすい場合があります。
- 資金調達の選択肢: 法人向けの融資制度や助成金・補助金などを活用しやすくなる可能性があります。
ただし、赤字であっても法人住民税の「均等割」(最低でも年間7万円程度)や、役員がいる場合は社会保険料の負担は発生します。
これらの固定費を支払ってもなお、法人格を維持するメリットがあるかを慎重に判断する必要があります。
インボイスの登録はいつまでに行うべきか
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録タイミングは、事業の状況や取引先の要望によって異なります。
個人事業主から法人成りする場合、個人事業主としての登録と、法人としての登録は別物として扱われる点に注意が必要です。
個人事業主として既に登録済みの場合
法人を設立したら、新たに法人として「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。
同時に、個人事業については「個人事業者の死亡・合併以外の理由による消滅届出書」を提出し、登録を取り消します。
事業が途切れないよう、設立後速やかに手続きを行いましょう。
法人設立と同時に登録する場合
原則として、課税事業者になりたい課税期間の初日の前日までに登録申請を完了させる必要があります。
しかし、設立初年度から登録を受けたい場合は、設立登記が完了してから速やかに登録申請書を提出すれば、設立日から登録事業者となることが可能です。
いずれの場合も、BtoB取引がメインで、取引先からインボイスの発行を求められる可能性が高い場合は、事業開始と同時に登録を済ませておくのが最もスムーズです。
決算公告は必要か
いいえ、合同会社には、株式会社と異なり決算公告の義務はありません。
株式会社は、毎年の決算内容を官報や日刊新聞紙、電子公告などの方法で公表することが会社法で義務付けられています。
決算公告が不要であることは、合同会社の大きなメリットの一つです。
官報への掲載費用(約6万円〜)や手続きの手間を削減できるため、ランニングコストを抑えたい小規模な事業に適しています。
税理士に依頼するか自計化するか
法人化を機に、会計や税務をどうするかは大きな決断です。
個人事業主の確定申告とは異なり、法人の決算申告は非常に複雑なため、多くの場合で税理士への依頼が推奨されます。
それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自計化(自分で対応) | ・税理士費用がかからない(コスト削減) | ・膨大な手間と時間がかかる ・専門知識が必要で、間違いのリスクが高い ・有効な節税策を見逃しやすい ・税務調査の際に不利になる可能性がある |
| 税理士に依頼 | ・正確で有利な決算申告が可能 ・節税に関する専門的なアドバイスが受けられる ・経営者は本業に集中できる ・税務調査の対応を任せられる ・資金調達や経営に関する相談ができる | ・顧問料や決算料などの費用が発生する |
個人事業主の感覚で「自分でできる」と安易に判断すると、後で追徴課税を受けたり、本来受けられたはずの節税メリットを逃したりするリスクがあります。
特に法人成りは、税務・会計のルールが大きく変わるタイミングです。
信頼できる税理士を探し、設立準備の段階から相談することをおすすめします。
失敗しないチェックリスト

個人事業主から合同会社への法人成りは、事業の成長における重要なステップですが、多くの手続きと判断が伴います。
後から「こんなはずではなかった」と後悔しないために、事前に確認すべき項目を網羅したチェックリストを作成しました。
このリストを活用し、計画的かつスムーズに法人成りを進めましょう。
手続きと期限の確認
法人成りには、設立手続きだけでなく、個人事業の廃業手続きや各種届出が複雑に絡み合います。
特に税務関連の届出は、提出期限を1日でも過ぎると、設立初年度から消費税が課税されたり、青色申告の承認が受けられなかったりといった大きなデメリットが生じるため、細心の注意が必要です。
以下の表で、主要な手続きと期限を時系列で確認してください。
| タイミング | 手続き内容 | 提出先・担当 | 主な期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 設立前 | 定款の作成・認証(電子定款が主流) | 自分 or 司法書士・行政書士 | 登記申請前 |
| 資本金の払込み | 発起人個人の銀行口座 | 定款作成後、登記申請前 | |
| 印鑑証明書の取得、法人実印の作成 | 市区町村役場、印鑑作成業者 | 登記申請前 | |
| 設立日 | 合同会社設立の登記申請 | 法務局 | (この日が会社の設立日) |
| 設立後速やかに | 法人設立届出書 | 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場 | 設立後2ヶ月以内(都道府県等で異なる) |
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立後3ヶ月以内 or 第1期事業年度終了日のいずれか早い日 | |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 事務所開設から1ヶ月以内 | |
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 日本年金機構(事務センター) | 設立の事実があった日から5日以内 | |
| 労働保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇用する場合) | 労働基準監督署、ハローワーク | 保険関係成立の翌日から10日以内、設置の翌日から10日以内 | |
| 個人事業の廃業関連 | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 税務署 | 廃業から1ヶ月以内 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 税務署 | 廃業した年の翌年3月15日まで |
税金と社会保険の試算
法人成りの最大の目的の一つが節税ですが、社会保険への加入義務化により、手取り額が減少するケースも少なくありません。
感覚で判断するのではなく、必ず具体的な数字でシミュレーションを行いましょう。
- 役員報酬額の決定
自分の生活費や事業の利益水準を考慮し、役員報酬をいくらに設定するか決めましたか?この金額が、個人の所得税・住民税と社会保険料の基準となります。 - 法人税額の試算
事業の予想利益から役員報酬やその他経費を差し引いた後の「課税所得」を算出し、法人税がいくらになるか試算しましたか? - 個人の税金(所得税・住民税)の試算
設定した役員報酬(給与所得)に対してかかる所得税・住民税はいくらになるか把握していますか?個人事業主時代の事業所得とは計算方法が異なります。 - 社会保険料の試算
最も見落としがちなのが社会保険料の負担です。役員報酬月額を基に、会社負担分と個人負担分の合計額がいくらになるか、必ず試算してください。キャッシュフローに大きな影響を与えます。 - トータル手取り額の比較
「個人事業主時代の税金・国保・国民年金」と「法人成り後の法人税・個人の税金・社会保険料」を差し引いた後の、事業全体で自由に使えるお金(トータル手取り額)を比較しましたか?
契約変更や口座開設の準備
法的には個人事業主と合同会社は別人格です。
そのため、これまで個人名義で結んでいた契約は、すべて法人名義で巻き直す必要があります。
事業の根幹に関わる重要な作業であり、相手方の都合もあるため、早めにリストアップして着手しましょう。
- 取引先との契約書
主要なクライアントや仕入先との業務委託契約書や売買契約書などを、法人名義で再締結する準備はできていますか? - オフィスの賃貸借契約
事務所や店舗の賃貸借契約を法人名義に変更する手続きについて、管理会社や大家さんに確認しましたか?保証会社の再審査や保証金の積み増しが必要な場合もあります。 - 許認可の引継ぎ・再取得
建設業、飲食業、古物商など、事業に必要な許認可は法人として再取得が必要な場合があります。行政庁に手続きを確認しましたか? - 法人口座の開設準備
登記完了後、すぐに法人口座を開設できるよう、必要書類(登記簿謄本、定款の写し、代表者の本人確認書類など)を準備していますか?審査には数週間かかることもあります。 - 各種サービスの登録情報変更
Webサイトのドメイン、サーバー、利用しているクラウドサービス、電話回線、公共料金などの契約者名義を法人に変更するリストを作成しましたか?
規程や社内ルールの整備
合同会社になると、個人事業主時代には不要だった社内規程の整備が求められます。
これらの規程は、節税策を正しく実行し、税務調査で否認されるリスクを避けるための重要な証拠となります。
- 定款
会社の憲法です。事業目的は将来の展開も見据えて適切に設定されていますか?役員の任期や決算期は自社の状況に合わせて決めていますか? - 役員報酬規程
役員報酬を損金算入するための「定期同額給与」の要件を満たすため、報酬額や支給日を定めた規程を作成する準備はできていますか? - 旅費規程
出張時の日当や交通費、宿泊費のルールを定めていますか?適切に運用すれば、会社は損金に、受け取った役員は非課税所得となり、大きな節税効果があります。 - 社宅規程
自宅を社宅扱いにする場合、会社が家賃の一部を負担し、それを損金にするためのルールを定めていますか?家賃の算定方法などを明確にする必要があります。 - 就業規則(従業員を雇用する場合)
従業員を雇用する場合(常時10人以上で作成・届出義務)、労働時間や休日、賃金に関するルールを定めた就業規則の準備はできていますか?
まとめ
個人事業主から合同会社への移行は、利益が600万円~800万円を超え所得税の負担が重くなった時が有力なタイミングです。
また、年商1,000万円を超え消費税の課税が見込まれる場合も、法人化による免税メリットを享受できる好機と言えます。
ただし、社会保険料の負担増などのデメリットも存在するため、節税効果だけでなく、信用力向上や事業拡大といった将来像を見据え、総合的に判断することが失敗しないための鍵となります。



