合同会社の設立準備で、最初の大きなハードルとなる「定款作成」。
何から手をつければ良いのか、記載事項に漏れはないか、費用はどれくらいかかるのか、多くの疑問や不安を抱えていませんか?
この記事は、そんなあなたのための合同会社定款作成の完全マニュアルです。
定款の基礎知識から、事業目的や本店所在地といった絶対的記載事項の書き方見本、費用を4万円節約できる電子定款の作成手順、さらには定款完成後の設立登記手続きまで、専門知識がない方でもこの記事一つで迷わず定款を完成させられるよう、必要な情報を網羅しました。
結論として、合同会社の定款はテンプレートを活用し、電子定款で作成すれば、司法書士に依頼せずとも費用を最小限に抑えて自分で作成することが可能です。
この記事を読み終える頃には、あなたは定款作成に関する全ての疑問を解消し、自信を持って会社設立の第一歩を踏み出せるようになっているでしょう。
合同会社の定款作成 初心者がまず知っておくべきこと
合同会社の設立を決意した方が、最初に向き合うことになるのが「定款(ていかん)」の作成です。専門用語も多く、何から手をつければ良いのか戸惑うかもしれません。
しかし、ポイントさえ押さえれば、ご自身で作成することも十分に可能です。
この章では、定款作成の第一歩として、初心者がまず理解しておくべき基本知識をわかりやすく解説します。
定款とは何か?合同会社における位置づけ
定款とは、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めた書類のことで、「会社の憲法」とも呼ばれる非常に重要なものです。
会社名(商号)や事業内容、社員の構成、利益の配分方法など、会社の根幹をなす事項が記載されます。
特に合同会社は、株式会社と比べて内部のルールを自由に設計できる「社員の自治」が広く認められているのが特徴です。
そのため、社員同士の合意事項を定款に明確に記載しておくことで、将来のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな会社運営を実現する羅針盤としての役割を果たします。
株式会社の定款は、作成後に公証人役場で「認証」という手続きが必要ですが、合同会社の定款は公証人による認証が不要です。
この点が、合同会社がスピーディーかつ低コストで設立できる大きな理由の一つとなっています。
また、定款には設立時に作成する「原始定款」と、設立後に内容を変更した際の最新版である「現行定款」があります。
設立登記の際に法務局へ提出するのは「原始定款」の写しです。
定款作成の全体像と流れを把握する
定款作成は、闇雲に書き始めるのではなく、全体の流れを把握してから取り掛かることが成功の秘訣です。
大まかなステップは以下の通りです。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ステップ1:記載事項の決定 | 会社の基本情報(商号、事業目的、本店所在地など)や、運営ルールを社員全員で話し合って決めます。 | 後の章で詳しく解説する「絶対的記載事項」は、一つでも欠けると定款自体が無効になるため特に重要です。 |
| ステップ2:定款の作成 | 決定した事項をもとに、定款の条文を作成します。 作成方法は「紙の定款」と「電子定款」の2種類があります。 | 紙で作成すると4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款なら不要です。 費用を抑えたい場合は電子定款がおすすめです。 |
| ステップ3:署名または押印 | 作成した定款に、出資者である社員全員が署名(または記名押印)します。 電子定款の場合は、電子署名を行います。 | この署名・押印により、社員全員が定款の内容に同意したことを証明します。 |
| ステップ4:定款の保管と登記申請 | 完成した定款(原始定款)は、会社で大切に保管します。 そして、定款の写しを他の必要書類と共に法務局へ提出し、設立登記を申請します。 | 原始定款は会社の重要書類です。 紛失しないよう、本店に備え置く必要があります。 |
このように、まずは「何を記載するかを決める」ことから始まります。
次の章では、具体的な記載事項について、見本を交えながら一つひとつ詳しく解説していきますので、ご安心ください。
【項目別】合同会社の定款の書き方と記載例見本
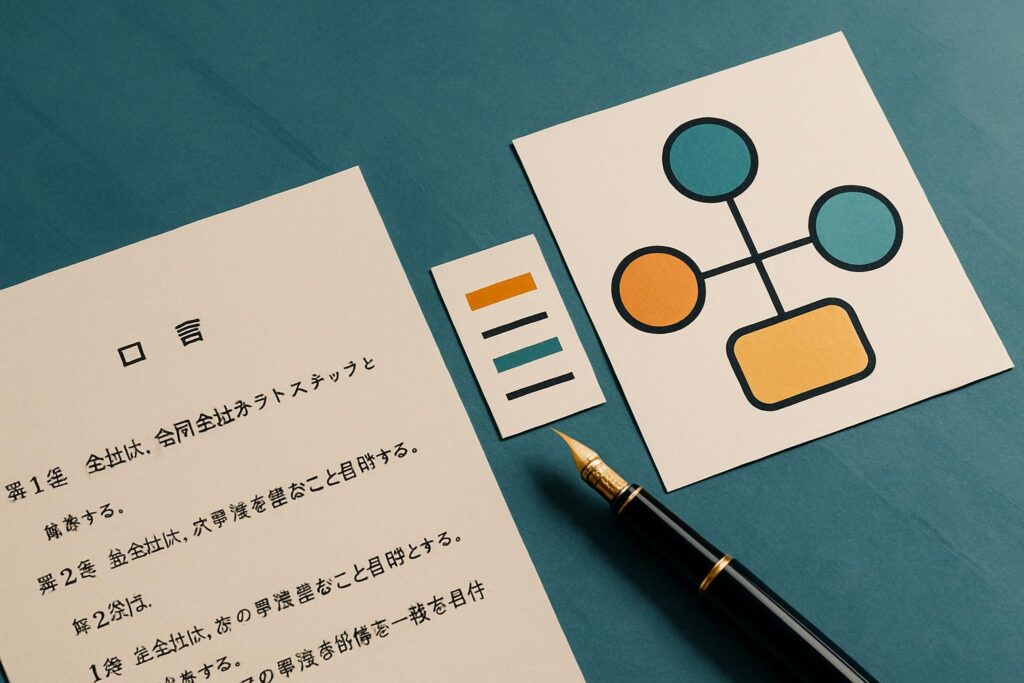
ここからは、合同会社の定款作成における最重要パートである、具体的な記載項目とその書き方について、見本を交えながら詳しく解説します。
定款の記載事項は、大きく分けて「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されます。
それぞれの違いをまず理解しておきましょう。
| 記載事項の種類 | 内容 | 記載がない場合 |
|---|---|---|
| 絶対的記載事項 | 会社法で定められた、必ず記載しなければならない事項。 | 定款そのものが無効になります。 |
| 相対的記載事項 | 定款に記載しなければ、その効力が認められない事項。 | その事項に関する効力が発生しません。 |
| 任意的記載事項 | 会社のルールとして任意で記載できる事項。法律に反しない限り有効。 | 特に問題ありませんが、記載することで社内ルールが明確になります。 |
この章では、特に重要な「絶対的記載事項」と、会社の運営ルールを定める上で欠かせない「相対的・任意的記載事項」の代表的なものを取り上げていきます。
これがないと無効になる絶対的記載事項
絶対的記載事項は、会社法第576条第1項で定められている、定款に必ず記載しなければならない6つの項目です。
一つでも記載が漏れていると、作成した定款は法的に無効となり、会社の設立登記ができません。
細心の注意を払って作成しましょう。
会社の顔となる商号の決め方
商号とは、会社の名前のことです。
自由に決められる部分も多いですが、いくつかのルールを守る必要があります。
商号のルール
- 「合同会社」という文字を必ず入れる: 商号の前(合同会社〇〇)でも後(〇〇合同会社)でも構いません。
- 使用できる文字: 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字(0~9)、一部の記号(「&」「’」「,」「‐」「.」「・」)が使用できます。ただし、記号は字句を区切る場合に限り、商号の先頭または末尾には使用できません(「.」を除く)。
- 同一商号・同一本店の禁止: 同じ住所に同じ商号の会社は登記できません。
- 不正競争防止法: 有名な企業やブランドと間違われるような商号は、後々トラブルになる可能性があるため避けるのが賢明です。
商号を決めたら、法務局の「オンライン登記情報検索サービス」や国税庁の「法人番号公表サイト」で、類似の商号がないか事前に調査しておくと安心です。
【記載例】
| (商号) 第1条 当会社は、合同会社ネクストステップと称する。 |
許認可にも関わる事業目的の書き方
事業目的は、その会社がどのような事業を行うのかを具体的に示す項目です。
将来的に許認可(建設業、飲食業、古物商など)が必要な事業を行う可能性がある場合、その許認可の要件に合った文言を正確に記載しておく必要があります。
後から目的を追加するには定款変更の手続きと費用がかかるため、将来展開する可能性のある事業も幅広く記載しておくことをおすすめします。
事業目的のポイント
- 適法性: 法律や公序良俗に反する事業は目的とすることはできません。
- 営利性: 会社は利益を追求する組織であるため、ボランティア活動のような非営利な活動は目的とできません。
- 明確性: 第三者が見ても事業内容が理解できるよう、具体的で分かりやすい言葉で記載します。
- 将来性: すぐに始めなくても、将来行う可能性のある事業は含めておきましょう。
最後に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」という一文(バスケット条項)を入れておくと、事業内容を広くカバーできるため一般的によく使われます。
【記載例】
| (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.ウェブサイトの企画、制作、運営及び保守 2.インターネットを利用した広告業務及びマーケティング支援 3.各種イベントの企画及び運営 4.飲食店の経営 5.前各号に附帯又は関連する一切の事業 |
本店所在地をどこまで記載するか
本店所在地とは、会社の主たる営業所の住所のことです。
定款への記載方法は2パターンあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
- 最小行政区画まで記載する(例:「東京都新宿区」)
メリット:同じ市区町村内で移転する場合、定款の変更が不要です。登記の変更のみで済みます。
デメリット:登記申請時には、番地までの詳細な住所を記載した「本店所在地決定書」が別途必要になります。 - 地番まで詳細に記載する(例:「東京都新宿区西新宿二丁目8番1号」)
メリット:定款だけで正確な所在地が分かります。
デメリット:同じ市区町村内であっても、少しでも移転すれば定款変更の手続き(登録免許税3万円)が必要になります。
将来的な移転の可能性を考えると、定款変更の手間とコストを省ける「最小行政区画まで」の記載が一般的でおすすめです。
【記載例(最小行政区画まで)】
| (本店所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 |
社員と出資に関する重要事項
合同会社における「社員」とは、従業員のことではなく、会社に出資し経営を行うオーナー(株式会社の株主に相当)を指します。
定款には、以下の事項を必ず記載する必要があります。
- 社員の氏名(法人の場合は名称)と住所
- 社員全員が「有限責任社員」であること
- 各社員の出資の目的(金銭か、不動産などの現物か)とその価額
「有限責任社員」とは、会社の債務に対し、自分が出資した金額の範囲内でのみ責任を負うということです。
合同会社の最大の特徴の一つであるため、この旨を明確に記載します。
【記載例】
| (社員及び出資) 第4条 当会社の社員の氏名、住所及び出資の価額は、次のとおりである。 金100万円 東京都新宿区〇〇一丁目2番3号 有限責任社員 山田 太郎 金 50万円 神奈川県横浜市中区〇〇四丁目5番6号 有限責任社員 鈴木 花子 (社員の責任) 第5条 当会社の社員は、すべて有限責任社員とする。 |
会社のルールを明確にする相対的・任意的記載事項
絶対的記載事項とは異なり、記載がなくても定款が無効になるわけではありません。
しかし、会社の運営ルールを明確にし、後のトラブルを避けるために定めておいた方が良い重要な項目です。
ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。
代表社員や業務執行社員の定め
合同会社では、原則として出資者である社員全員が会社の「代表権」と「業務執行権」を持ちます。
しかし、複数人で会社を設立する場合、全員が代表では意思決定が煩雑になる可能性があります。
そこで、定款で特定の社員を「業務執行社員」や「代表社員」と定めることができます。
- 業務執行社員: 会社の日常的な業務を行う権限を持つ社員。定款で定めない場合は、全社員が業務執行社員となります。
- 代表社員: 会社を代表して契約などの法律行為を行う権限を持つ社員。業務執行社員の中から選ぶのが一般的です。
役割分担を明確にしたい場合は、これらの役職を定款で定めておくことを強く推奨します。
【記載例】
| (業務の執行) 第〇条 当会社の業務は、業務執行社員の過半数をもって決定し、各業務執行社員がこれを執行する。 (代表社員) 第〇条 当会社の代表社員は、次の者とする。 東京都新宿区〇〇一丁目2番3号 代表社員 山田 太郎 2 代表社員は、当会社を代表し、当会社の業務を統括する。 |
事業年度の決め方と決算月
事業年度とは、会社の損益を計算するための期間のことで、通常1年間です。
事業年度の末日(決算日)の翌日から2ヶ月以内に法人税などの税務申告と納税を行う必要があります。
決算月は自由に決められますが、以下の点を考慮すると良いでしょう。
- 繁忙期を避ける: 会社の最も忙しい時期と決算業務が重ならないように設定します。
- 消費税の免税期間: 資本金1,000万円未満の場合、設立1期目と2期目は原則として消費税が免除されます。事業年度を設立日からなるべく長く(約1年)設定することで、免税のメリットを最大限享受できます。
一度決めた事業年度を変更するには定款変更の手続きが必要になるため、慎重に検討しましょう。
【記載例】
| (事業年度) 第〇条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 |
合同会社の定款作成費用を徹底比較 紙と電子どちらがお得?
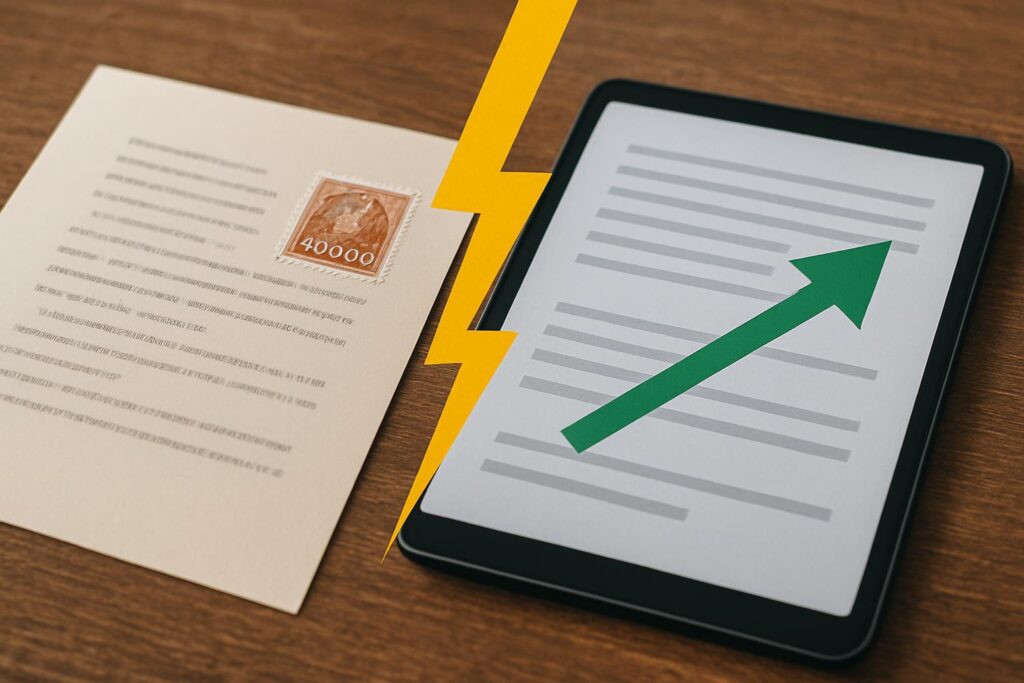
合同会社の定款を作成する方法は、大きく分けて「紙の定款」と「電子定款」の2種類があります。
どちらを選ぶかによって、会社設立の初期費用が大きく変わるため、それぞれの特徴とコストを正確に理解しておくことが重要です。
結論から言うと、費用面で圧倒的にお得なのは電子定款です。
ここでは、なぜそう言えるのか、具体的な金額を交えながら詳しく比較・解説していきます。
紙の定款で発生する収入印紙代4万円
従来からあるオーソドックスな方法が、作成した定款を紙に印刷して製本する「紙の定款」です。
この方法を選択した場合、必ず発生するのが収入印紙代として4万円の費用です。
これは、印紙税法という法律によって、定款が「課税文書」と定められているために課される税金です。
作成した紙の定款に4万円分の収入印紙を貼り付け、消印をすることで納税したことになります。
この収入印紙が貼られていない定款は、法的に有効なものとして認められず、設立登記の申請も受理されません。
会社設立にかかる費用全体の中でも、この4万円は非常に大きな割合を占めます。
専門家に依頼せず自分で手続きを進める場合、この印紙代が設立費用の中で最も高額な出費となるケースも少なくありません。
電子定款なら費用を大幅に節約できる
一方、近年主流となりつつあるのが、定款をPDFなどの電子データで作成する「電子定款」です。
電子定款の最大のメリットは、紙の定款で必須だった収入印紙代4万円が一切かからなくなる点にあります。
なぜなら、印紙税はあくまで「紙の文書」に対して課される税金であり、電子データで作成された文書は印紙税法上の課税文書に該当しないためです。
つまり、作成方法を紙から電子に変えるだけで、設立費用を4万円も節約できるのです。
ただし、電子定款の作成には、マイナンバーカードやICカードリーダライタといった専用の機器やソフトの準備が必要になるため、その分の初期費用(数千円程度)がかかります。
それでも、4万円の印紙代と比較すれば、コストメリットは絶大です。
紙の定款と電子定款の費用を比較すると、その差は一目瞭然です。
| 項目 | 紙の定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 公証人による認証手数料 | 0円(合同会社は不要) | 0円(合同会社は不要) |
| その他(機器購入費など) | 0円 | 数千円程度(ICカードリーダライタ等) |
| 合計費用(目安) | 40,000円 | 数千円程度 |
このように、合同会社の設立費用を少しでも抑えたいのであれば、電子定款を選択することが最も賢明な判断と言えるでしょう。
次の章では、自分で電子定款を作成するための具体的な手順を詳しく解説します。
自分でできる電子定款の作成方法パーフェクトガイド

合同会社の設立費用を大幅に削減できる電子定款。
以前は専門的な知識や高価なソフトが必要でしたが、現在では環境さえ整えればご自身で作成することも十分可能です。
ここでは、電子定款の作成に必要な準備から具体的な手順、そして初心者がつまずきやすいポイントまで、誰にでも分かるように徹底解説します。
電子定款のメリットとデメリット
電子定款の導入を検討する上で、まずはそのメリットとデメリットを正確に把握しておくことが重要です。
特にコスト面でのメリットは大きいですが、準備には手間がかかる側面もあります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 費用 | 収入印紙代4万円が不要になる点が最大のメリットです。 設立費用を大きく抑えられます。 | ICカードリーダライタの購入費用(数千円程度)や、PDF作成ソフト(Adobe Acrobatなど)の購入費用がかかる場合があります。 |
| 時間・手間 | データでやり取りできるため、印刷・製本・押印の手間が省けます。 登記申請までオンラインで行えば、法務局へ出向く必要もありません。 | パソコンの初期設定や、必要なソフトウェアのインストール、電子署名の付与など、特有の準備と作業に手間がかかります。 |
| 保管・管理 | データとしてパソコンやクラウド上に保管できるため、物理的な保管場所が不要です。 紛失のリスクが低く、複製も容易です。 | データの破損や消失、サイバー攻撃などのリスク対策が必要です。 適切なバックアップが求められます。 |
準備するものリストと作成手順
電子定款を自分で作成するために必要なものをリストアップしました。
ハードウェアとソフトウェアの両方が必要になるため、事前に漏れなく準備しましょう。
準備するものリスト
| 分類 | 具体的なもの | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ハードウェア | パソコン | Windows搭載のパソコン | 法務省の推奨環境はWindowsです。 Macでも可能ですが、設定が複雑になる場合があります。 |
| 電子証明書 | マイナンバーカード | 署名用電子証明書が搭載されているものが必要です。 事前に市区町村の窓口で発行手続きを済ませておきましょう。 | |
| 読取装置 | ICカードリーダライタ | マイナンバーカードに対応している製品を選びます。 家電量販店やオンラインストアで数千円で購入可能です。 | |
| ソフトウェア | PDF作成・署名ソフト | Adobe Acrobat(有償版) | 電子署名を付与する機能が必要なため、閲覧のみの「Acrobat Reader」では作成できません。 |
| 申請用ソフト | 法務省「登記・供託オンライン申請システム」の申請者用総合ソフトなど | 法務省のウェブサイトから無料でダウンロードできます。 Java実行環境のインストールも必要になる場合があります。 | |
電子定款の作成手順
必要なものが揃ったら、いよいよ作成に取り掛かります。
以下のステップに沿って進めましょう。
- 定款内容の作成(Wordなど)
まずは、これまでの章で解説した記載事項を盛り込み、Wordやテキストエディタで定款の原案を作成します。 - PDFファイルへの変換
作成した定款の原案をPDF形式で保存します。Wordなどのソフトに搭載されている「PDFとして保存」機能を使えば簡単です。 - 電子署名の付与
ここが最も重要な工程です。ICカードリーダライタにマイナンバーカードをセットし、Adobe Acrobatを使ってPDFファイルに電子署名を行います。定款に記載されている社員(出資者)全員分の電子署名が必要ですので、ご注意ください。 - 登記申請システムでの手続き
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」にアクセスし、申請者情報を登録します。その後、設立登記の申請書を作成し、電子署名を付与した定款のPDFファイルを添付して送信します。 - 登録免許税の納付
申請が受理されると、納付情報が通知されます。インターネットバンキングなどを利用して、登録免許税(合同会社は最低6万円)を電子納付すれば、手続きは完了です。
電子定款作成でつまずきやすいポイント
ご自身で電子定款を作成する際、多くの方が戸惑うポイントがいくつかあります。
事前に知っておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
- パソコンの環境構築エラー
ICカードリーダライタのドライバが正しくインストールされていない、Javaのバージョンが古い、ブラウザのセキュリティ設定が厳しいなど、PC環境が原因で先に進めなくなるケースが最も多いです。作業を始める前に、法務省のウェブサイトで推奨環境を必ず確認し、一つずつ設定を見直しましょう。 - 電子署名の方法がわからない
Adobe Acrobatの操作に慣れていないと、どこから電子署名を行えばよいか迷うことがあります。また、社員が複数いる場合、全員のマイナンバーカードとICカードリーダライタを準備し、順番に署名作業を行う必要があります。一人のパソコンで全員分の署名を行うか、PDFファイルを回覧して各自で署名してもらうか、事前に段取りを決めておくとスムーズです。 - 登記・供託オンライン申請システムの操作
公的なシステムのため、操作画面が直感的でないと感じる方も少なくありません。入力項目が多く、専門用語も出てくるため、マニュアルをよく読みながら慎重に進める必要があります。特に、申請書様式と添付書類の組み合わせを間違えないように注意が必要です。
これらのポイントで解決しない場合は、無理せず専門家である司法書士に相談することも選択肢の一つです。
費用はかかりますが、時間と手間を大幅に節約できます。
合同会社の定款作成に関するよくある疑問を解決

定款の記載項目や作成方法がわかっても、いざ作業を進めると「テンプレートはどこにある?」「ハンコはどこに押せばいい?」といった細かな疑問が出てくるものです。この章では、合同会社の定款作成でつまずきがちなポイントや、よくある質問について、Q&A形式でわかりやすく解説します。
定款のテンプレートはどこでダウンロードできる?
合同会社の定款は、一からすべてを自作する必要はありません。
信頼できる機関が提供するテンプレート(ひな形)を活用することで、効率的かつ正確に作成を進めることができます。
主に、以下の場所から入手可能です。
法務局のウェブサイト
法務局では、商業・法人登記の申請書様式として、合同会社設立登記申請書の記入例の中に定款の記載例を掲載しています。
最もシンプルで基本的な内容ですが、公的な機関が提供しているため信頼性は非常に高いと言えるでしょう。
まずはこの記載例をベースに、自社の状況に合わせて内容を修正・追加していくのがおすすめです。
日本公証人連合会のウェブサイト
株式会社の場合は定款認証が必要なため、日本公証人連合会のウェブサイトに詳細な定款の記載例やテンプレートが用意されています。
合同会社は定款認証が不要ですが、記載項目の考え方など参考になる部分が多くあります。
特に、事業目的の書き方や任意的記載事項を充実させたい場合に役立ちます。
専門家(司法書士・行政書士など)のウェブサイト
多くの司法書士事務所や行政書士事務所が、ウェブサイト上で無料の定款テンプレートをWord形式などで配布しています。
これらは実務に即した内容になっていることが多いですが、事務所独自の条項が含まれている場合もあるため、ダウンロードしたテンプレートをそのまま使うのではなく、必ず自社の実情に合わせて内容を精査・修正するようにしてください。
定款の製本と押印の方法は?
紙で定款を作成した場合、法務局へ提出する謄本(写し)と会社で保管する原本について、適切な製本と押印が必要です。
特に押印には重要なルールがありますので、しっかり確認しておきましょう。
定款の製本方法
作成した定款をA4用紙に印刷し、順番通りに揃えます。そして、左側をホッチキスで2箇所ほど留めるのが一般的です。
さらに、ホッチキスの芯を隠すように背表紙に製本テープを貼ると、より丁寧でしっかりとした仕上がりになります。
押印(捺印)のルール
製本した定款には、社員全員が以下のルールに従って押印します。
- 署名と押印: 定款の最終ページ、末尾の「以上、合同会社〇〇を設立のため、社員が署名(または記名)押印する。」といった文言の後に、社員全員が署名(または記名)し、個人の実印を押印します。
- 契印(けいいん): 定款が複数ページにわたる場合、ページの差し替えや抜き取りを防ぐために「契印」が必要です。すべてのページを見開きの状態にし、その綴じ目にまたがるように社員全員が実印で押印します。これにより、定款全体が一体のものであることを証明します。
なお、電子定款で作成する場合は、紙への印刷、製本、押印は一切不要です。
代わりに、作成したPDFファイルに社員全員の電子署名を行います。
定款作成は司法書士に依頼すべき?
定款作成を自分で行うか、司法書士などの専門家に依頼するかは、多くの方が悩むポイントです。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合わせて判断しましょう。
| 自分で作成する場合 | 司法書士に依頼する場合 | |
|---|---|---|
| メリット | 費用を大幅に抑えられる(専門家への報酬が不要)会社の根本規則を自ら作ることで理解が深まる | 法的に不備のない正確な定款を迅速に作成できる電子定款に対応でき、収入印紙代4万円が節約できる許認可や将来の事業展開を見据えたアドバイスがもらえる設立登記まで一括で依頼でき、手間と時間を節約できる |
| デメリット | 作成に時間と手間がかかる法的な知識が必要で、不備があると無効になるリスクがある電子定款の作成には専用ソフトや機器が必要 | 報酬(手数料)として数万円程度の費用がかかる |
結論として、費用を少しでも抑えたい、時間をかけてでも自分で手続きを完結させたいという方はご自身での作成が向いています。
一方で、本業の準備に集中したい、法的なリスクを避けたい、手続きの手間を省きたいという方は司法書士への依頼がおすすめです。
特に電子定款を利用すれば、司法書士への報酬を支払っても、自分で紙の定款を作成するより総費用が安くなるケースも少なくありません。
定款を紛失した場合の対処法
会社の重要なルールを定めた定款は、厳重に保管すべき書類です。
しかし、万が一紛失してしまった場合でも、対処法はありますので落ち着いて対応しましょう。
「原始定款」は再発行できない
まず知っておくべきことは、会社設立時に作成した「原始定款」そのものは、世界に一つしかなく再発行はできないということです。
原始定款とは、設立登記の際に法務局へ提出した、一番最初の定款のことを指します。
原始定款の「写し(謄本)」を入手する
原始定款そのものは再発行できませんが、その「写し(謄本)」であれば入手できる可能性があります。
合同会社の場合、設立登記を行った法務局に原始定款が保管されています。
この保管期間内(登記完了から約10年間が目安)であれば、法務局で「定款の謄本」を請求することで、設立時の定款の写しを入手することが可能です。
請求には、登記事項証明書の取得など、所定の手続きが必要になります。
定款を「復元」する
法務局での保管期間が過ぎており謄本が入手できない場合は、定款を「復元」する必要があります。
会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得し、そこに記載されている商号、目的、本店所在地などの情報や、過去の議事録、社員の記憶などをもとに、現在の内容に沿った定款を改めて作成します。
作成した定款の末尾に「以上は、当会社の現行定款と相違ないことを証明する。」といった文言と日付、会社名、代表社員名を記載し、会社実印を押印することで、対外的に有効な定款として利用できます。
このような事態を避けるためにも、設立時に作成した原始定款はPDFデータとしても保存し、クラウドストレージなどで厳重に保管しておくことを強く推奨します。
定款完成後の手続き 設立登記から保管まで
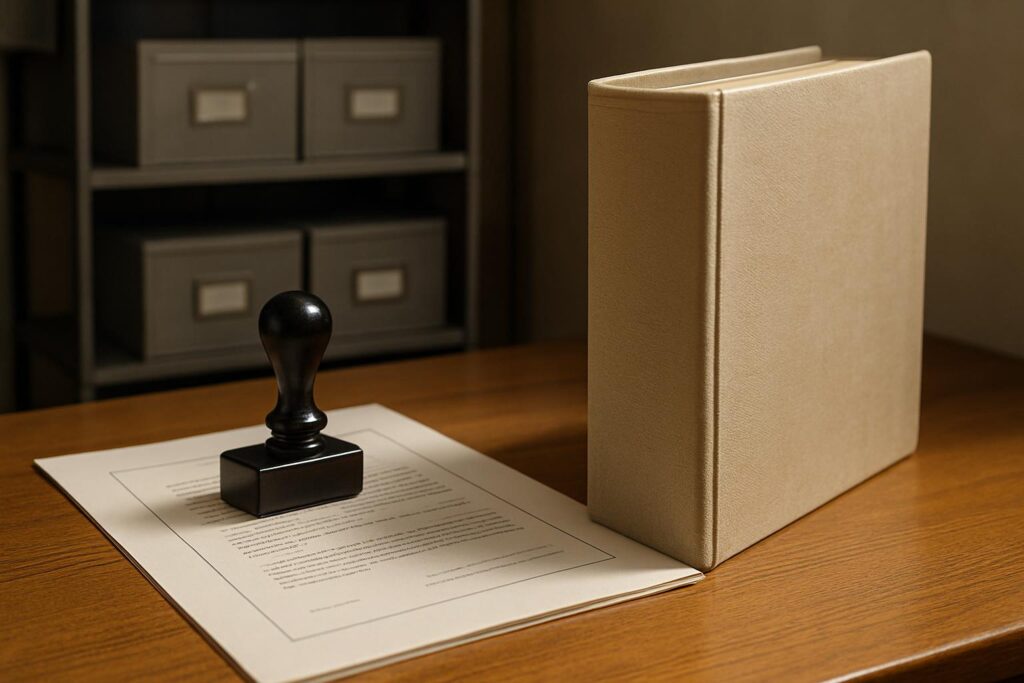
認証済みの定款が手元に準備できても、それだけでは合同会社として法的に認められ、事業を開始することはできません。
定款作成はあくまで設立準備の一環です。定款が完成した後に待っているのは、会社設立の最終手続きである「設立登記申請」です。
この登記申請が法務局に受理されて初めて、合同会社は法人格を取得します。
ここでは、定款完成後から会社設立完了までの具体的な手続きと、会社の憲法ともいえる定款の正しい保管方法について詳しく解説します。
法務局への設立登記申請
設立登記申請は、会社の基本情報を登記簿に登録し、社会に公的に存在を証明するための重要な手続きです。
この申請をもって、合同会社の設立が完了します。
登記申請の期限と申請先
合同会社の設立登記は、出資金(資本金)の払込みがあった日から2週間以内に行わなければならないと法律で定められています。
期限を過ぎてしまうと過料(罰金)の対象となる可能性があるため、計画的に進めましょう。
申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
設立登記に必要な書類一覧
設立登記の申請には、定款の他にも複数の書類が必要です。
不備があると再提出となり、設立日が遅れてしまうため、抜け漏れなく準備しましょう。
一般的に必要となる書類は以下の通りです。
| 書類名 | 概要と注意点 |
|---|---|
| 合同会社設立登記申請書 | 法務局のウェブサイトから書式をダウンロードできます。 登記すべき事項を記載し、登録免許税分の収入印紙を貼付します。 |
| 定款 | 公証役場での認証が不要なため、作成した定款を提出します。 電子定款の場合はCD-Rなどに保存して提出するか、オンラインで申請します。 |
| 代表社員の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内の原本が必要です。 業務執行社員が複数いる場合でも、代表社員のものだけで問題ありません。 |
| 払込証明書 | 出資金が振り込まれたことを証明する書類です。 代表社員個人の銀行口座の通帳コピーと、会社名義で作成した証明書を合綴して作成します。 |
| 本店所在地決定書 | 定款に「東京都新宿区」のように最小行政区画までしか記載していない場合に、具体的な地番を決定したことを証明する書類です。 |
| 社員の就任承諾書 | 代表社員や業務執行社員が就任を承諾したことを証明する書類です。 定款の記載内容によっては不要な場合もあります。 |
| 印鑑届書 | 会社の実印(代表者印)を法務局に登録するための書類です。 今後の重要書類への押印に必要となります。 |
登録免許税について
合同会社の設立登記には、登録免許税という税金がかかります。
税額は「資本金の額 × 0.7%」で計算されますが、この計算額が6万円に満たない場合は、一律で6万円となります。
例えば、資本金が300万円の場合、300万円×0.7%=21,000円ですが、最低額の6万円が適用されます。
この登録免許税は、収入印紙を購入し、申請書に貼付して納付します。
原始定款の正しい保管方法
法務局への登記申請が無事に完了し、会社が設立された後も、定款は非常に重要な書類として保管し続けなければなりません。
設立時に作成した最初の定款のことを「原始定款」と呼びます。
原始定款の重要性と保管義務
原始定款は、その会社の根本規則を定めた最も基本となる書類です。
会社法により、合同会社は会社が存続する限り、原始定款を本店に備え置く義務があります。
この原始定款は、金融機関での法人口座開設、融資の申し込み、補助金や助成金の申請、許認可の取得など、会社の運営における様々な重要局面で提出を求められます。
紛失してしまうと、事業運営に大きな支障をきたす可能性があるため、厳重な管理が不可欠です。
紙の定款と電子定款の保管方法
定款の種類によって、適切な保管方法が異なります。
紙の定款の場合
製本・押印された紙の定款は、物理的な書類です。
そのため、紛失、汚損、火災や水濡れによる毀損のリスクが常に伴います。鍵のかかるキャビネットや金庫など、安全な場所に保管しましょう。
また、万が一に備え、スキャンしてPDFデータとしてバックアップを取っておくことを強く推奨します。
ただし、データ化したものはあくまで「写し」であり、原本の重要性は変わりません。
電子定款の場合
電子定款は、電子署名が付与されたPDFファイルそのものが原本となります。
物理的な劣化や紛失のリスクはありませんが、代わりにデータ消失のリスクに備える必要があります。
パソコン本体だけでなく、クラウドストレージや外付けハードディスクなど、複数の場所にバックアップを保存しておくことが極めて重要です。
USBメモリでの保管は手軽ですが、紛失や故障のリスクが高いため、メインの保管方法としては避けた方が賢明です。
なお、電子定款を印刷したものは「謄本(写し)」の扱いとなり、原本そのものではない点に注意が必要です。
まとめ
本記事では、合同会社の定款作成について、基本知識から具体的な書き方の見本、費用を抑える電子定款の作成方法まで、網羅的に解説しました。
定款は「会社の憲法」とも呼ばれるほど重要な書類ですが、一つひとつの項目を正しく理解すれば、ご自身で作成することも十分に可能です。
定款作成で最も重要なポイントは、会社の根幹をなす「絶対的記載事項」を漏れなく正確に記載することです。
また、作成費用に関しては、紙の定款で必要となる収入印紙代4万円が不要になるため、コストを抑えたいのであれば電子定款での作成が最適な選択肢と言えるでしょう。
ご自身での作成に不安がある場合や、本業に集中したい場合は、司法書士などの専門家に依頼することも検討してください。
定款が無事に完成したら、次のステップである法務局への設立登記に進み、いよいよ事業のスタートです。
この記事を参考に、スムーズな合同会社設立を実現してください。



