起業する際、個人事業主から始めるべきか、いきなり法人化すべきかは多くの起業家が悩むポイントです。
結論から言うと、いきなり法人化には節税や社会的信用など、事業を加速させる大きなメリットがあります。
本記事では、税理士が5つのメリットと後悔しないための注意点を徹底解説。
あなたが最適な選択をするための判断基準から、会社設立でやるべきことまで網羅的に紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
いきなり法人化すべき?多くの起業家が抱える悩み
「自分の事業を始めたい!」その熱い想いを胸に起業を決意したとき、多くの人が最初に直面するのが「個人事業主としてスタートするか、それとも、いきなり法人化するか」という大きな選択です。
特に、まだ売上の見通しが立っていない段階では、「まずは手軽な個人事業主から始めて、事業が軌道に乗ったら法人成りを検討しよう」と考えるのが一般的かもしれません。
しかし、その「一般的」な選択が、あなたのビジネスにとって本当に最適解なのでしょうか。
実は、事業内容や将来のビジョンによっては、最初から法人を設立する「いきなり法人化」の方が、圧倒的に多くのメリットを享受できるケースが存在します。
一方で、そのメリットだけを見て安易に判断すると、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性も否定できません。
起業家が直面する「いきなり法人化」への不安や疑問
実際に起業を考えられているあなたは、今、このような不安や疑問を抱えていないでしょうか?
- 「売上が立つか分からないのに、設立費用や維持コストをかけて法人化するのはリスクが高すぎるのでは?」
- 「個人事業主なら手続きが簡単そうだけど、法人は定款認証や登記など、やることが多くて本業に集中できなくなりそう…」
- 「法人の方が節税できると聞くけど、それは本当?逆に赤字だと税金の負担が重くなるんじゃないの?」
- 「社会的信用が高いと言われても、具体的にどんな場面で有利になるのかイメージが湧かない」
- 「周りのフリーランス仲間はみんな個人事業主。自分だけ法人化して浮いてしまわないか不安…」
これらの悩みは、起業を目指すすべての人が一度は通る道です。
そして、その悩みの根源には、個人事業主と法人の根本的な違いに対する理解が不可欠です。
まずは両者の特徴を比較し、全体像を掴むことから始めましょう。
一目でわかる!個人事業主と法人の基本的な違い
なぜ「いきなり法人化」を悩むのか。
それは、個人事業主と法人で、手続き、費用、税金、そして社会的責任に至るまで、様々なルールが異なるからです。
以下の表で、その主な違いを確認してみましょう。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社の例) |
|---|---|---|
| 開業・設立手続き | 税務署に開業届を提出するだけで、手続きは比較的簡単。 | 定款の作成・認証、法務局への設立登記など、複雑で専門的な手続きが必要。 |
| 設立費用 | 原則0円。 | 定款認証手数料や登録免許税などで、最低でも約20万円~25万円程度の費用がかかる。 |
| 税金の種類 | 所得税、住民税、個人事業税、消費税など。所得が増えるほど税率が高くなる累進課税。 | 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税など。利益に対して一定の税率が課される。 |
| 社会的信用 | 法人に比べて一般的に低いと見なされることがある。 | 登記情報が公開されており、取引先や金融機関からの信用を得やすい。 |
| 責任の範囲 | 無限責任。事業上の負債は、個人の全財産で返済する義務を負う。 | 有限責任。出資者は、原則として自分が出資した金額の範囲内でのみ責任を負う。 |
| 赤字の繰越 | 青色申告の場合、損失を最大3年間繰り越せる。 | 損失(欠損金)を最大10年間繰り越せる。 |
このように、個人事業主の手軽さと法人の信用の高さには、それぞれ裏腹な側面があります。
この記事では、こうした基本的な違いを踏まえながら、あなたが抱える「いきなり法人化すべきか」という悩みを解消し、ご自身の事業にとって最善の道筋を見つけるための具体的なヒントを、税理士の視点から詳しく解説していきます。
結論 いきなり法人化には大きなメリットがある

「事業を始めるなら、まずは個人事業主からスタートするのが一般的」そう考えている方は多いかもしれません。
確かに、手軽に始められる個人事業主は魅力的な選択肢です。
しかし、事業計画や将来のビジョンによっては、最初から法人を設立する「いきなり法人化」が、ビジネスの成長を加速させる最適な戦略となるケースも少なくありません。
個人事業主にはない法人ならではの恩恵は、想像以上に多岐にわたります。
特に、節税、社会的信用、資金調達の面では、スタートダッシュで大きな差がつく可能性があります。
ここでは、あなたの事業の可能性を最大限に引き出す「いきなり法人化」の5つの大きなメリットを具体的に解説します。
メリット1 節税対策の選択肢が圧倒的に多い
法人化がもたらす最大のメリットの一つが、節税効果の高さです。
個人事業主と法人では適用される税制が根本的に異なり、利益が大きくなるほどその差は顕著になります。
まず、税率構造が異なります。個人事業主の所得税は、利益が大きくなるほど税率も高くなる「累進課税」で、最大45%(住民税と合わせると約55%)に達します。
一方、法人税は基本的に一定の税率です。そのため、年間の所得(利益)が800万円〜900万円を超えるあたりから、法人の方が税負担を抑えられるケースが多くなります。
さらに、法人では経費として認められる範囲が格段に広がります。
- 役員報酬:自分自身への給与を「役員報酬」として経費にできます。受け取った側では給与所得控除が適用されるため、所得を圧縮する効果があります。
- 役員社宅:自宅を法人が借り上げて役員社宅とすることで、家賃の一部を経費として計上できます。
- 生命保険料:個人では生命保険料控除に上限がありますが、法人契約の生命保険であれば、保険の種類によって支払保険料の全額または一部を損金(経費)に算入できます。
- 出張手当(日当):出張旅費規程を整備すれば、役員や従業員に非課税の出張手当を支給でき、会社側では経費として計上可能です。
加えて、資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として設立から最大2年間、消費税の納税が免除されるという大きなメリットもあります。(インボイス制度の登録状況により変動します)
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 適用される税金 | 所得税(累進課税:5%〜45%) | 法人税(概ね15%〜23.2%) |
| 自分への給与 | 経費にできない(事業主勘定) | 役員報酬として経費にできる |
| 生命保険料 | 所得控除(上限あり) | 損金算入(保険商品による) |
| 退職金 | 原則なし(小規模企業共済など) | 役員退職金として準備・経費計上可能 |
メリット2 社会的信用度が高くビジネスチャンスが広がる
ビジネスの世界では「信用」が何よりも重要です。
法人格を持つことは、その信用の獲得において絶大な効果を発揮します。
まず、取引先からの見方が大きく変わります。大企業や金融機関の中には、コンプライアンスや与信管理の観点から「法人でなければ取引しない」という方針を掲げているところも少なくありません。
個人事業主というだけで、大きなビジネスチャンスを逃してしまう可能性があるのです。
法人登記されている会社は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば誰でもその実態を確認できるため、取引相手に安心感を与えます。
また、事業に必要な許認可を取得する際にも、法人格が有利に働く、あるいは必須となる場合があります。
例えば、建設業許可や人材派遣業許可など、一定の財産的基礎が求められる許認可では、資本金制度のある法人の方が要件を満たしやすい傾向にあります。
「株式会社〇〇」という看板は、単なる名称以上の価値を持ちます。
顧客やパートナーに対して、事業への真剣な姿勢や継続性、組織としての安定性を示す強力なブランディングツールとなるのです。
メリット3 資金調達や採用活動で有利になる
事業の成長に不可欠な「資金」と「人材」。この両面においても、法人化は大きなアドバンテージをもたらします。
資金調達
金融機関は融資の審査において、事業の透明性や財務状況の信頼性を重視します。
法人は会計処理が法律で厳格に定められており、決算書の信頼性が個人事業主よりも高いと評価されます。
そのため、日本政策金融公庫や民間金融機関からの融資審査において、法人の方が有利に進みやすい傾向があります。
特に、個人保証に依存しないプロパー融資など、より好条件での資金調達を目指すなら法人格は不可欠と言えるでしょう。
さらに、株式会社であれば、第三者からの出資(増資)による資金調達も可能になり、事業拡大の選択肢が大きく広がります。
採用活動
優秀な人材を確保することは、事業成功の鍵です。
求職者の多くは、安定性や将来性を求めて就職先を探します。
その際、「個人商店」よりも「会社組織」である法人の方に魅力を感じるのが一般的です。
また、法人には社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。
福利厚生が整備されているという安心感は、求職者にとって大きな判断材料となり、応募者の質の向上や採用競争力の強化に直結します。
メリット4 赤字の繰越期間が長い
起業初期は、設備投資や広告宣伝費などがかさみ、赤字(欠損金)になることも珍しくありません。
この赤字を翌年以降に繰り越し、将来発生する黒字と相殺して税負担を軽減できる制度を「繰越欠損金の控除」といいます。
この赤字を繰り越せる期間が、個人事業主と法人で大きく異なります。
| 区分 | 繰越可能期間 |
|---|---|
| 個人事業主(青色申告) | 3年間 |
| 法人 | 10年間(※) |
※2018年4月1日以降に開始した事業年度で生じた欠損金の場合
ご覧の通り、法人は個人事業主の3倍以上も長い10年間、赤字を繰り越すことができます。
創業初期の投資が数年後に実を結ぶようなビジネスモデルの場合、この長期の繰越期間は将来のキャッシュフローに絶大な効果をもたらします。
事業が軌道に乗って利益が出始めた頃に、過去の赤字を使って納税額を抑えられるのは、経営戦略上、非常に大きなメリットです。
メリット5 事業承継やM&Aがしやすい
事業の出口戦略や将来の継続性まで見据えた場合、法人化のメリットはさらに際立ちます。
個人事業の場合、事業主本人が亡くなると、事業用の資産はすべて個人の相続財産となり、事業用の銀行口座も凍結されてしまいます。
事業を後継者に引き継ぐには、複雑な相続手続きや資産の名義変更が必要となり、事業が一時的にストップしてしまうリスクがあります。
一方、法人は事業主個人とは別人格です。代表者が変わっても会社そのものは存続します。事業承継は、会社の株式を後継者に譲渡または相続するだけでスムーズに行うことができ、事業の継続性を保ちやすいのです。
また、M&A(企業の合併・買収)による事業売却を検討する際も、法人の方が圧倒的に有利です。
個人事業の売却(事業譲渡)は、資産や契約を個別に移転する必要があり手続きが煩雑ですが、株式会社であれば「株式譲渡」という比較的シンプルな手法で会社そのものを売却できます。
これにより、創業者利益(キャピタルゲイン)を得て、新たな挑戦に進むといった選択肢も現実的になります。
後悔しないために知るべき いきなり法人化の注意点
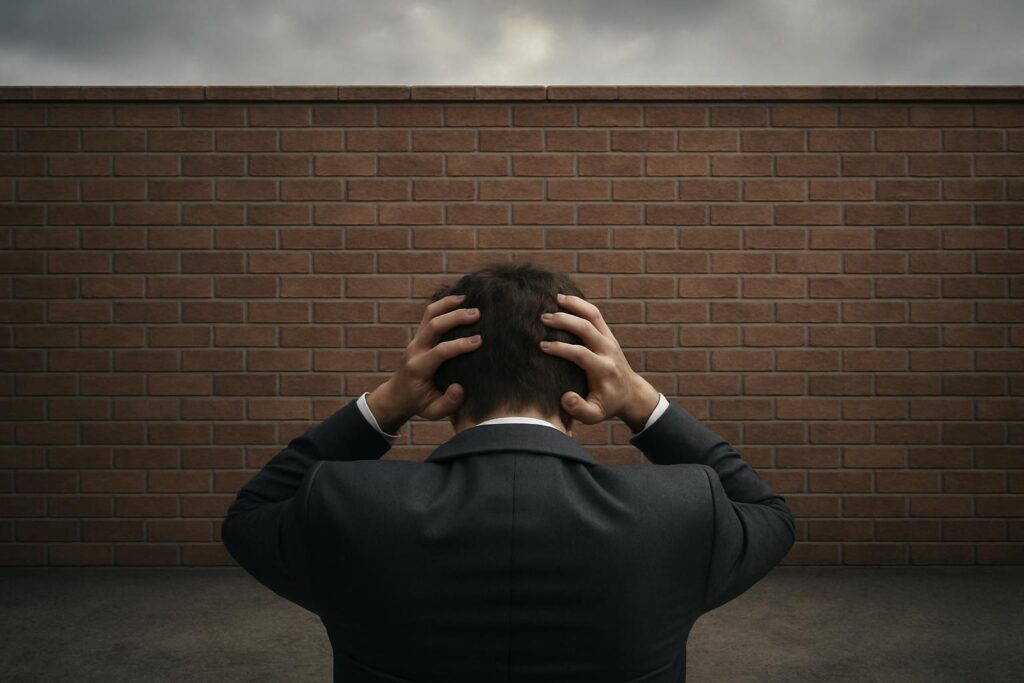
「いきなり法人化」には節税や信用力向上といった華やかなメリットがある一方で、個人事業主にはないデメリットや負担も存在します。
メリットだけに目を奪われて安易に法人化を進めると、「こんなはずではなかった」と後悔するケースも少なくありません。
ここでは、法人化を決断する前に必ず知っておくべき4つの注意点を、具体的な費用や手続きに触れながら詳しく解説します。
設立時の費用と手続きの負担
個人事業主の場合、税務署に「開業届」を提出するだけで事業を開始でき、費用は一切かかりません。
しかし、法人を設立するには、法律で定められた手続きを踏む必要があり、相応の費用と時間がかかります。
具体的にどれくらいの費用がかかるのか、最も一般的な株式会社と合同会社を例に比較してみましょう。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款用収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | 電子定款の場合は不要 |
| 定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 0円 | 公証役場に支払う手数料 |
| 登録免許税 | 最低150,000円 | 最低60,000円 | 資本金の額×0.7% |
| 合計(紙定款) | 約220,000円~ | 約100,000円~ | – |
| 合計(電子定款) | 約180,000円~ | 約60,000円~ | – |
このように、最も費用を抑えられる合同会社の電子定款でも約6万円、株式会社の場合は約18万円以上の実費が必要です。
さらに、これらの手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途5万円から10万円程度の報酬が発生します。
事業を始める前の段階で、この初期コストを負担できるかどうかが最初の関門となります。
社会保険への強制加入と保険料負担
個人事業主との最も大きな違いの一つが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務です。
個人事業主の場合、常時雇用する従業員が5人未満であれば社会保険への加入は任意ですが、法人は社長が1人であっても社会保険への加入が法律で義務付けられています。
社会保険料は、役員報酬(給与)の金額に応じて決まり、その保険料を会社と個人で半分ずつ負担(労使折半)します。
これは、個人事業主時代に加入していた国民健康保険や国民年金とは大きく異なる点です。
例えば、役員報酬を月額30万円に設定した場合、社会保険料の総額は約9万円となり、会社と個人がそれぞれ約4.5万円ずつを負担することになります。
個人事業主時代よりも手取り額が減る可能性があるだけでなく、会社にとっても大きな固定費となることを理解しておく必要があります。
将来の年金額が増えるというメリットはありますが、目先のキャッシュフローを圧迫する要因になり得るため、慎重な資金計画が不可欠です。
会計や税務申告の複雑化
法人になると、お金の管理や税金の計算が格段に複雑になります。
個人事業主の確定申告(青色申告など)とは比較にならないほど、専門的な知識が求められます。
法人は、正規の簿記の原則(複式簿記)に従って会計帳簿を作成し、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税などの申告書を作成・提出しなければなりません。
これらの書類は非常に複雑で、会計や税務の知識がない方が自力で完璧に作成するのは極めて困難です。
そのため、ほとんどの法人が税理士と顧問契約を結んでおり、その顧問料が毎月発生します。
顧問料は会社の規模や業務内容によって異なりますが、年間で数十万円のコスト増となるのが一般的です。
また、法人には「法人住民税の均等割」という税金があります。
これは、事業が赤字であっても、法人が存在するだけで課税される税金で、資本金の額や従業員数に応じて、最低でも年間7万円程度を納付しなければなりません。
利益が出ていない時期でも必ず発生するコストとして認識しておく必要があります。
廃業する際の手続きが煩雑
事業を始める際には考えにくいかもしれませんが、「辞めるときのコスト」も法人化の大きな注意点です。
個人事業主であれば、税務署に「廃業届」を提出するだけで済みますが、法人の場合はそう簡単にはいきません。
法人を正式にたたむ(廃業する)には、「解散」と「清算」という2段階の法的手続きが必要です。
具体的には、以下のような煩雑なステップを踏まなければなりません。
- 株主総会での解散決議
- 法務局への解散登記・清算人選任登記
- 官報での解散公告(債権者保護手続き)
- 税務署などへの解散届の提出
- 解散時の決算申告(解散事業年度の確定申告)
- 会社の財産の換価、債権の取り立て、債務の弁済
- 残余財産の株主への分配
- 株主総会での決算報告書の承認
- 法務局への清算結了登記
- 税務署などへの清算結了届の提出
これらの手続きをすべて完了するには、数ヶ月の期間と、登記費用や官報公告費用などで最低でも10万円以上、司法書士や税理士に依頼すれば総額で数十万円の費用がかかります。
「うまくいかなかったからすぐに辞めたい」と思っても、個人事業主のように簡単にはいかないのが法人の実態です。
この「出口」の難しさも、いきなり法人化を検討する上で重要な判断材料となります。
【ケース別】いきなり法人化の判断基準を税理士が解説

「いきなり法人化」が最適な選択肢となるかどうかは、あなたの事業内容や将来のビジョンによって大きく異なります。
ここでは、代表的な3つの業種を例に、税理士の視点から具体的な判断基準を詳しく解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な選択をするための参考にしてください。
ケース1 ITエンジニア・Webデザイナーなどのフリーランス
ITエンジニアやWebデザイナー、コンサルタントといった、主に自身のスキルや知識を提供して対価を得るフリーランスの場合、初期投資が比較的少なく、一人で事業を始めやすいのが特徴です。
そのため、法人化のタイミングは「売上・利益」と「取引先との関係性」が大きな判断材料となります。
いきなり法人化を検討すべきケース
- 年間所得が800万円を超える見込みがある: 個人事業主の所得税は累進課税のため、所得が増えるほど税率が高くなります。課税所得が800万円~900万円を超えると、法人税の実効税率の方が低くなる可能性が高く、節税メリットが大きくなります。役員報酬の設定や経費(損金)にできる範囲の広さを活かすことで、手元に残る資金を最大化できます。
- 大手企業との直接契約を目指している: 大手企業の中には、コンプライアンスや与信管理の観点から、個人事業主とは契約せず、法人とのみ取引を行う「法人縛り」を設けている場合があります。法人格を持つことで、こうしたビジネスチャンスを逃さず、事業拡大の足がかりを掴むことができます。
- チームでの事業展開を計画している: 将来的に他のエンジニアやデザイナーを雇用し、チームで大規模なプロジェクトを受注したいと考えているなら、いきなり法人化が有利です。社会的信用度が高い法人の方が、優秀な人材の採用や協力会社との連携がスムーズに進みます。
個人事業主からのスタートがおすすめのケース
- 売上の見通しが不透明: 独立直後で、まだ安定した収入が見込めない場合は、設立費用や維持コスト(社会保険料、税理士費用など)が負担になる可能性があります。まずは個人事業主としてスタートし、事業が軌道に乗ってから法人化(法人成り)を検討するのが堅実です。
- 事務手続きの負担を避けたい: 法人化すると、会計処理や税務申告が複雑になり、社会保険の手続きも発生します。本業に集中したい、スモールスタートを切りたいという方は、まずは手続きがシンプルな個人事業主が良いでしょう。
| 比較項目 | 法人(株式会社・合同会社) | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 税金 | 法人税(税率が比較的一定)。役員報酬で給与所得控除が使える。 | 所得税(累進課税)。所得が増えるほど税率が上がる。 |
| 社会的信用 | 高い。大手企業との取引や融資で有利。 | 法人に比べて低いと見なされる場合がある。 |
| 経費の範囲 | 役員報酬、退職金、生命保険料など、経費にできる範囲が広い。 | 事業に関連する費用のみ。法人に比べると範囲が狭い。 |
| 設立・維持コスト | 設立費用(約6万円~25万円)や社会保険料の負担がある。 | 開業届の提出のみで費用はかからない。維持コストも低い。 |
ケース2 飲食店や小売店を開業する場合
店舗を構える飲食店や小売店は、物件取得費や内装工事費、設備投資など、開業時に多額の初期費用が必要となる業種です。
そのため、「資金調達」と「事業規模」が法人化を判断する上で重要な鍵となります。
いきなり法人化を検討すべきケース
- 多額の創業融資を必要とする: 日本政策金融公庫や制度融資などを利用して、数百万~数千万円単位の融資を受けたい場合、いきなり法人化が断然有利です。個人事業主よりも法人の方が事業計画の信頼性が高いと判断され、融資の審査に通りやすく、希望額を満額借り入れできる可能性も高まります。
- 将来的に多店舗展開を目指している: 1店舗目が軌道に乗ったら、2店舗、3店舗と事業を拡大していきたいという明確なビジョンがあるなら、最初から法人としてスタートすることをおすすめします。法人格は、追加融資や不動産契約、人材採用など、事業拡大のあらゆる局面で有利に働きます。
- 複数人で共同経営する: 友人や知人と共同で出資し、お店を始める場合は、法人設立が必須と言えます。株式会社や合同会社であれば、出資比率や役員の役割、利益の分配方法などを定款で明確に定めることができ、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
個人事業主からのスタートがおすすめのケース
- 自己資金の範囲内で小規模に始める: 間借り営業やキッチンカー、自宅の一部を改装した小規模な店舗など、初期投資を抑えて一人で始める場合は、個人事業主の方が手軽です。
- 赤字期間が長引く可能性がある: 開業当初は売上が安定せず、赤字が続くことも考えられます。法人の場合、赤字でも法人住民税の均等割(最低でも年間7万円程度)が発生しますが、個人事業主であれば赤字の場合の税負担はありません。
ケース3 建設業や人材派遣業を始める場合
建設業や人材派遣業など、特定の許認可が必要な事業や、取引先からの信用が事業継続に直結する業種では、いきなり法人化がほぼ必須の選択となるケースが多くあります。
いきなり法人化を強く推奨するケース
- 建設業許可が必要な工事を請け負う: 1件の請負代金が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を行うためには、建設業許可が必要です。この許可を取得するには、経営能力や財産的基礎などの要件を満たす必要があり、資本金を設定できる法人の方が、個人事業主よりも要件をクリアしやすいという明確なメリットがあります。
- 元請け企業や官公庁の仕事を受注したい: 大手のゼネコンやハウスメーカーなどの元請け企業は、下請け業者に対して法人であることを取引の条件とするのが一般的です。また、公共事業の入札に参加する場合も、法人格が求められることがほとんどです。これらの仕事を視野に入れるなら、法人設立はスタートラインと言えます。
- 労働者派遣事業の許可を取得する: 人材派遣業を営むためには、厚生労働大臣の許可が必要ですが、その資産要件(基準資産額2,000万円以上など)は非常に厳格です。これらの要件を満たすためには、法人を設立し、適切な資本金を設定することが現実的な選択肢となります。
- 万が一の際のリスクを限定したい: 建設業は、工事中の事故など、事業に伴うリスクが比較的高い業種です。個人事業主は無限責任であり、事業上の損害賠償責任を個人の全財産で負う必要があります。一方、株式会社や合同会社は有限責任であるため、経営者の責任は原則として出資額の範囲内に限定され、個人の資産を守ることができます。
個人事業主からスタートできる限定的なケース
- 許可が不要な軽微な工事のみを請け負う: 500万円未満の工事のみを請け負う一人親方として独立する場合であれば、個人事業主としてスタートすることも可能です。ただし、将来的に事業を拡大し、大きな工事を請け負いたいと考えたタイミングで、法人化を検討する必要が出てくるでしょう。
いきなり法人化を決めたらやるべきことリスト

「いきなり法人化」を決断したら、次はいよいよ具体的な設立準備に入ります。
個人事業主の開業とは異なり、法人の設立には法律で定められた手続きが必要です。
ここでつまずかないために、やるべきことをリストアップし、一つひとつのポイントを丁寧に解説します。
後悔しない会社設立のために、ぜひ参考にしてください。
株式会社と合同会社のどちらを選ぶか
法人化するにあたり、まず決めなければならないのが「会社形態」です。
日本の会社のほとんどは「株式会社」または「合同会社」のいずれかです。
それぞれに特徴があり、あなたの事業計画や将来のビジョンによって最適な選択は異なります。
両者の違いを理解し、慎重に選びましょう。
主な違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用(法定費用) | 約20万円~(定款認証5万円、登録免許税15万円~) | 約6万円~(登録免許税6万円~) |
| 出資者(社員)の名称 | 株主 | 社員(業務執行社員) |
| 出資者の責任 | 有限責任(出資額の範囲内) | 有限責任(出資額の範囲内) |
| 意思決定機関 | 株主総会 | 原則として社員全員の同意 |
| 社会的信用度 | 高い傾向にある | 株式会社に比べると低い場合がある |
| 利益の配分 | 出資比率(株式数)に応じて配当 | 定款で自由に決められる |
| 役員の任期 | 原則2年(最長10年まで伸長可)。任期ごとに登記が必要。 | 任期なし。登記の更新は不要。 |
外部からの資金調達(出資)や将来的な上場(IPO)を目指す場合は、株式会社一択です。
社会的信用度が高く、株式を発行して資金を集める仕組みが整っているためです。
一方で、設立費用を抑え、迅速な意思決定でスピーディーに事業を進めたい場合は、合同会社が適しています。
Apple JapanやGoogleなど、有名企業も合同会社の形態をとっており、信用度が著しく低いわけではありません。
ご自身の事業規模や将来設計に合わせて最適な形態を選びましょう。
資本金はいくらに設定すべきか
現在の会社法では、資本金1円から会社を設立できます。
しかし、安易に資本金を低く設定するのはおすすめできません。
資本金は「会社の体力」を示す重要な指標であり、事業を円滑に進めるための元手となるお金です。
資本金を決める際には、以下の3つの観点から検討しましょう。
1. 当面の運転資金
設立後すぐに売上が立つとは限りません。
売上が安定するまでの数ヶ月間、事業を継続するための運転資金を資本金として用意するのが基本です。
具体的には、最低でも3ヶ月~6ヶ月分の運転資金(事務所家賃、人件費、仕入費、広告宣伝費など)を目安にすると安心です。
2. 社会的信用度
資本金の額は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載され、誰でも閲覧できます。
取引先や金融機関があなたの会社と取引をするか、融資をするかを判断する際、資本金の額は重要な判断材料の一つになります。
資本金が極端に少ないと、「経営体力がない会社」と見なされ、融資が受けにくくなったり、大企業との取引が難しくなったりする可能性があります。
また、建設業など一部の許認可が必要な業種では、一定額以上の資本金が許可の要件となっている場合もあるため、事前の確認が必須です。
3. 消費税の免税事業者
節税の観点から非常に重要なポイントです。
資本金を1,000万円未満に設定して会社を設立すると、原則として設立1期目と2期目の消費税の納税が免除されます。
これは「いきなり法人化」の大きなメリットの一つです。特別な理由がない限り、資本金は1,000万円未満に設定することをおすすめします。(※特定期間の課税売上高など、他の要件によっては免税事業者になれない場合もあります。)
事業目的の決め方と注意点
会社の「事業目的」は、定款に必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」です。
これは、その会社がどのような事業を行うのかを内外に示すものであり、ここに記載されていない事業は原則として行えません。
事業目的は、以下のポイントを押さえて慎重に決めましょう。
- 明確性・具体性:誰が読んでも事業内容が理解できるよう、具体的かつ明確な言葉で記載します。「コンサルティング業」だけでなく、「経営コンサルティング業」「ITコンサルティング業」のように具体的に書くのが望ましいです。
- 適法性・営利性:当然ながら、法律に違反する事業や、公序良俗に反する事業を目的とすることはできません。また、株式会社や合同会社は営利法人であるため、ボランティア活動などの非営利な活動は事業目的に含められません。
- 将来性:現時点で計画している事業だけでなく、将来的に行う可能性のある事業も記載しておくことが重要です。後から事業目的を追加するには、株主総会(または社員総会)の決議を経て、法務局で変更登記を行う必要があり、手間と費用(登録免許税3万円)がかかります。例えば、Web制作事業を始めるなら、「インターネット広告代理店業」「各種イベントの企画及び運営」なども加えておくと、事業拡大の際にスムーズです。
- 許認可との関連:許認可が必要な事業(建設業、飲食業、古物商、人材派遣業など)を行う場合、事業目的に特定の文言が入っていないと許可が下りないことがあります。事前に管轄の行政庁に確認し、必要な文言を正確に記載するようにしましょう。
最後に、「上記各号に附帯又は関連する一切の事業」という一文を加えておくと、事業目的の範囲を広く解釈できるようになり、柔軟な事業運営が可能になります。
信頼できる税理士の選び方
法人を設立すると、個人事業主とは比較にならないほど会計や税務申告が複雑になります。
日々の記帳から決算申告、節税対策まで、専門家である税理士のサポートは不可欠です。
しかし、税理士なら誰でも良いというわけではありません。
信頼でき、あなたの事業の成長を共に考えてくれるパートナーを見つけることが成功の鍵となります。
信頼できる税理士を選ぶためのチェックポイントは以下の通りです。
- 法人税務の実績と経験:個人の確定申告だけでなく、法人の設立支援や決算申告の経験が豊富かを確認しましょう。
- 業界への理解度:あなたの事業(IT、飲食、建設、Web制作など)に関する知識や実績がある税理士を選ぶと、業界特有の会計処理や節税策について的確なアドバイスが期待できます。
- コミュニケーションのしやすさ:専門用語ばかりで説明が分かりにくい、質問しづらい雰囲気がある、といった税理士では意味がありません。あなたの目線に立って分かりやすく説明してくれ、気軽に相談できる相性の良さは非常に重要です。レスポンスの速さも確認しましょう。
- 明確な料金体系:顧問料や決算料に何が含まれているのか、追加で費用が発生するケースはあるのかなど、契約前に料金体系を明確に説明してくれるかを確認します。
- 積極的な節税提案:単に言われた通りに申告書を作成するだけでなく、最新の税制改正を踏まえ、あなたの会社に合った節税策や資金繰りの改善策を積極的に提案してくれるかが、良い税理士を見極める大きなポイントです。
税理士を探すには、税理士紹介サイトを利用したり、商工会議所や金融機関に相談したりする方法があります。
契約前には必ず複数の税理士と面談し、上記のポイントをチェックして、心から信頼できるパートナーを選びましょう。
まとめ
本記事では、いきなり法人化のメリットと注意点を解説しました。
個人事業主と比べて節税の選択肢が格段に増え、社会的信用が高まる点は大きな魅力です。
一方で、設立費用や社会保険料の負担増といったデメリットも無視できません。
ご自身の事業規模や将来の展望を考慮し、最適なタイミングを見極めることが成功の鍵となります。
最終的な判断に迷う場合は、信頼できる税理士などの専門家に相談し、後悔のない選択をしましょう。



