「とりあえず会社を作りたい」と考えている方へ。
その決断の前に、ぜひ本記事をお読みください。
勢いだけの法人化は、税金や社会保険料などの負担で後悔する落とし穴も。
この記事では、会社設立で失敗しないための判断基準から、株式会社と合同会社の比較、最短3日で終える手続き、設立後の費用まで網羅的に解説します。
あなたに最適な会社設立の答えが、ここにあります。
ちょっと待って「とりあえず会社を作る」で後悔しないための基礎知識
「よし、会社を作ろう!」その決意は素晴らしいものです。
しかし、「とりあえず」という軽い気持ちで会社を設立すると、後で思わぬ負担や後悔につながるケースが少なくありません。
この章では、勢いで法人化して失敗しないために、最低限知っておくべき基礎知識を解説します。
まずは立ち止まって、本当に今がベストな選択なのかを一緒に考えていきましょう。
安易な法人化の落とし穴とは
会社設立はゴールではなく、スタートです。安易な法人化には、見過ごされがちなデメリットが潜んでいます。
具体的にどのような「落とし穴」があるのか、事前に把握しておきましょう。
- 赤字でも発生するコストの存在
会社は利益が出ていなくても、毎年必ず支払わなければならない税金があります。それが法人住民税の「均等割」です。資本金や従業員数に応じて決まり、たとえ事業が赤字であっても最低でも年間約7万円の支払い義務が生じます。個人事業主にはない、この固定コストは経営の重荷になる可能性があります。 - 社会保険への強制加入と負担増
法人化すると、社長一人であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられます。保険料は会社と個人で折半しますが、国民健康保険や国民年金に比べて、トータルの負担額が増えるケースがほとんどです。従業員を雇用すれば、その分の会社負担も発生します。 - 煩雑な事務手続きと管理コスト
個人事業主の確定申告に比べ、法人の決算申告は非常に複雑です。会計帳簿の作成基準も厳格になり、専門知識がなければ自力で行うのは困難でしょう。そのため、多くの会社が税理士と顧問契約を結びますが、当然ながらその費用(顧問料)が発生します。他にも、役員変更や本店移転の際には登記手続きが必要になるなど、維持・運営していくための事務的・金銭的コストは個人事業主の比ではありません。 - 簡単にはやめられない
個人事業主であれば、廃業届を税務署に提出するだけで事業をやめることができます。しかし、会社をたたむ(解散・清算する)には、法務局での登記手続きや官報公告など、複雑な手順を踏まなければなりません。会社の清算には数十万円の費用と数ヶ月の期間がかかるため、「とりあえず作ったけど、うまくいかないからやめる」ということが簡単にはできないのです。
個人事業主との違いを理解する
法人化を検討する上で、個人事業主との違いを正しく理解することは不可欠です。
税金、責任、信用の観点から、それぞれの特徴を比較してみましょう。
どちらの形態がご自身の事業フェーズに適しているかを見極める判断材料にしてください。
| 項目 | 法人(株式会社・合同会社) | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 設立手続き | 定款認証や登記申請が必要。費用と時間がかかる(株式会社で約20万円~、合同会社で約6万円~)。 | 税務署に開業届を提出するだけ。費用はかからない。 |
| 税金 | 利益に対して「法人税」などが課される。税率は一定(所得800万円以下は軽減税率あり)。赤字は最大10年間繰越可能。 | 利益(所得)に対して「所得税」が課される。所得が増えるほど税率が高くなる累進課税。赤字は最大3年間繰越可能。 |
| 経費の範囲 | 役員報酬として給与を支払うことで、経営者自身の給与も経費にできる(給与所得控除が適用)。生命保険料なども条件次第で経費計上可能。 | 事業に関わる費用のみ経費となる。事業主自身への給与という概念はない。 |
| 社会的信用 | 登記情報が公開されており、一般的に信用度が高い。金融機関からの融資や大手企業との取引で有利になる傾向がある。 | 法人に比べると信用度が低いと見なされる場合がある。 |
| 責任の範囲 | 有限責任。出資額の範囲内でのみ責任を負う。個人の財産まで差し押さえられることはない(経営者が連帯保証人になっている場合を除く)。 | 無限責任。事業上の負債はすべて個人の財産で返済する義務がある。 |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金保険への加入が強制。 | 国民健康保険・国民年金に加入。従業員5人未満の場合は任意加入。 |
本当に今が設立のベストタイミングか
では、あなたにとって会社設立のタイミングは「今」なのでしょうか。
以下のポイントを参考に、ご自身の状況を客観的にチェックしてみましょう。
メリットがデメリットを上回るタイミングこそが、最適な設立時期と言えます。
法人化を検討すべきタイミングの目安
- 課税所得が800万円を超えそうだ
個人事業主の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる累進課税です。一方、法人税の税率はほぼ一定です。一般的に、税金だけを考えた場合、課税所得が800万円~900万円を超えると、個人の所得税率が法人税率を上回り、法人化した方が節税メリットが大きくなると言われています。これは法人化を検討する最も代表的な指標の一つです。 - 大きな融資や資金調達を計画している
金融機関は、会計が明確で社会的信用度の高い法人の方を融資対象として評価しやすい傾向にあります。また、外部から出資を募る「増資」という資金調達方法は法人のみ可能な手段です。事業拡大のためにまとまった資金が必要になった時は、法人化の大きなチャンスです。 - 法人でなければ契約できない取引先がある
企業によっては、コンプライアンスや与信管理の観点から、取引相手を法人のみに限定している場合があります。獲得したい大きな案件や、取引を希望する企業が法人格を求めているのであれば、それは事業を飛躍させるための重要な設立タイミングと言えるでしょう。 - 消費税の納税義務が発生しそうだ
個人事業主として課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後から消費税の課税事業者となります。このタイミングで法人化(法人成り)すると、資本金1,000万円未満などの要件を満たせば、設立から最大2年間、消費税の納税が免除される可能性があります。(※インボイス制度の登録を行う場合は課税事業者となります)
これらの項目に一つも当てはまらない場合、まだ「とりあえず」の段階かもしれません。
焦って法人化するのではなく、まずは個人事業主として事業を成長させ、上記のタイミングが訪れるのを待つというのも賢明な戦略です。
株式会社VS合同会社「とりあえず会社を作る」ならどっち?
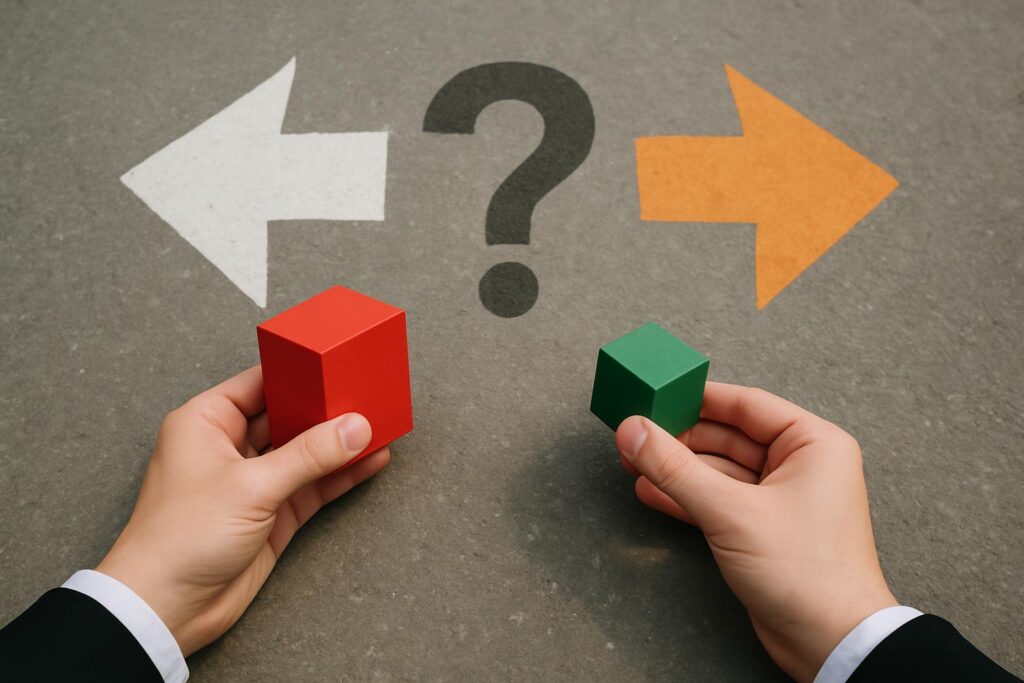
「とりあえず会社を作りたい」と考えたとき、多くの人が最初にぶつかるのが「株式会社」と「合同会社」のどちらを選ぶかという問題です。
どちらも法人格を持つ会社ですが、設立費用や手続き、運営の自由度などに大きな違いがあります。
安易に選んでしまうと、後から「こんなはずではなかった」と後悔しかねません。
あなたの事業計画や将来のビジョンに最適な会社形態を選ぶために、それぞれの特徴を具体的な項目で徹底比較していきましょう。
設立費用の比較
会社設立において、まず気になるのが初期費用です。
「とりあえず」という動機であれば、できる限りコストを抑えたいと考えるのが自然でしょう。
株式会社と合同会社の設立費用には明確な差があります。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 最低150,000円 | 最低60,000円 | 資本金の0.7%。最低額に満たない場合は最低額を納付。 |
| 定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 0円 | 公証役場で定款の認証を受けるための手数料。合同会社は不要。 |
| 定款に貼る収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | 電子定款を利用すれば、どちらも0円になり節約可能。 |
| 合計費用(紙定款) | 約220,000円~ | 約100,000円~ | 合同会社の方が12万円以上安い。 |
| 合計費用(電子定款) | 約180,000円~ | 約60,000円~ | 電子定款にするとさらに費用を抑えられる。 |
表を見れば一目瞭然ですが、設立費用を最優先で考えるなら、合同会社が圧倒的に有利です。
特に、公証役場での定款認証が不要である点が大きく、最低でも12万円以上の差が生まれます。
電子定款を活用すれば、その差はさらに広がります。
スピーディーかつ低コストで法人格を手に入れたい方にとって、合同会社は非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
手続きの手間とスピードの比較
設立にかかる費用だけでなく、手続きの煩雑さや設立までのスピードも重要な比較ポイントです。
特に本業が忙しい中で会社設立を進める場合、手続きはできるだけシンプルな方が望ましいでしょう。
株式会社の設立手続きで最も特徴的なのが、公証役場での「定款認証」です。
作成した定款が法的に問題ないか、公証人によるチェックと認証を受ける必要があり、このプロセスに時間と手間がかかります。
一方、合同会社は定款の作成は必要ですが、公証役場での認証手続きは一切不要です。
定款を作成したら、そのまま法務局へ登記申請ができます。この認証プロセスの有無が、設立までの期間を大きく左右します。
一般的に、株式会社の設立には準備から完了まで2〜3週間程度かかるのに対し、合同会社は準備が整っていれば最短3日〜1週間程度での設立も可能です。
とにかく早く事業をスタートさせたい、手続きに時間をかけたくないというスピード重視の方には合同会社が適しています。
社会的信用度と運営の自由度の比較
コストやスピードだけでなく、設立後の事業運営に関わる「社会的信用度」と「運営の自由度」も考慮すべき重要な要素です。
この2点は、株式会社と合同会社の性格を最もよく表しています。
社会的信用度
一般的に、「株式会社」の方が知名度が高く、社会的信用度も高いと認識される傾向にあります。
これは、厳格な会社法に則って運営されているイメージや、歴史的な背景が影響しています。
そのため、大手企業との取引(BtoB)や金融機関からの融資、優秀な人材の採用といった面で、株式会社の方が有利に働く可能性があります。
将来的に外部から多額の資金調達を考えている場合や、会社のブランドイメージを重視するなら、株式会社を選ぶメリットは大きいでしょう。
ただし、近年ではApple JapanやGoogleなど、世界的な大企業も日本法人を合同会社で設立している例が増え、合同会社の認知度も向上しています。
事業内容や実績がしっかりしていれば、合同会社だからという理由だけで信用が大きく損なわれるケースは少なくなってきています。
運営の自由度
会社の運営ルールに関しては、合同会社に大きなアドバンテージがあります。
株式会社は、所有者である「株主」と、経営を行う「取締役」が分離しており、最高意思決定機関として株主総会が存在します。
また、役員には任期(最長10年)があり、毎年の決算公告も義務付けられています。
対して合同会社は、出資者である「社員」がそのまま経営を行う「所有と経営の一致」が原則です。
これにより、迅速な意思決定が可能で、運営に関するルールを定款で柔軟に設計できます。
例えば、役員の任期はなく、決算公告の義務もありません。
さらに、利益の配分も出資額の比率に関わらず、貢献度などに応じて自由に決めることが可能です。
この自由度の高さは、小規模で機動的な経営を目指す場合に大きなメリットとなります。
それぞれの会社形態が向いているケース
これまでの比較を踏まえ、あなたがどちらの会社形態を選ぶべきか、具体的なケース別に整理しました。
ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
株式会社が向いているケース
- 将来的に、ベンチャーキャピタルなど外部からの出資を受けて事業を拡大したい、株式上場(IPO)を目指している。
- 会社の知名度やブランドイメージを重視し、幅広い層から人材を採用したい。
- 取引先が大手企業中心であり、社会的信用度が特に重要になるBtoBビジネスを展開する。
- 複数の出資者がおり、それぞれの役割に応じて「所有(株主)」と「経営(取締役)」を明確に分離したい。
合同会社が向いているケース
- とにかく初期費用と設立の手間を最小限に抑え、スピーディーに法人格を取得したい。(まさに「とりあえず会社を作る」ケース)
- 個人事業主からの法人成り(マイクロ法人)で、経営者は自分一人、または家族だけで運営する。
- 消費者向けのサービス(BtoC)や、フリーランス活動の法人化など、スモールビジネスから始めたい。
- 出資者間の合意のもと、利益配分や権限などを柔軟に決め、自由度の高い経営を行いたい。
結論として、「とりあえず会社を作る」という動機であれば、多くの場合、設立・運営コストが低く、手続きが簡単な合同会社からスタートするのが合理的です。
事業が軌道に乗り、さらなる成長を目指す段階で、必要に応じて株式会社へ組織変更することも可能です。
まずは合同会社で法人としての第一歩を踏み出し、事業の成長に合わせて会社の形を最適化していくという戦略も有効でしょう。
会社設立の全手順 最短3日コース

「とりあえず会社を作りたい」と思っても、何から手をつけて良いかわからない方も多いでしょう。
しかし、ポイントを押さえれば、会社設立は驚くほどスピーディーに進められます。
この章では、電子定款とオンライン申請を活用し、最短3日で会社を設立するための具体的な全手順を、準備編・書類作成編・申請編の3つのステップに分けてわかりやすく解説します。
準備編 設立前に決めるべきこと
会社設立は、登記申請書を法務局に提出する前の「準備」が9割です。
ここで会社の骨格となる基本事項をしっかり決めておくことで、後の手続きがスムーズに進みます。
焦らず、一つひとつ着実に決定していきましょう。
会社の基本情報(商号・目的・所在地など)
まず、会社の憲法ともいえる「定款」に記載する、最も重要な基本情報を決定します。
これらは登記される情報であり、会社の顔となる部分です。
| 決定事項 | 決定する内容と注意点 |
|---|---|
| 商号(会社名) | 会社の名前です。使用できる文字(漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字など)にはルールがあります。同一の所在地で同一の商号は登記できないため、法務局のオンライン登記情報検索サービスなどで類似商号の調査を事前に行いましょう。名前の前か後ろに「株式会社」または「合同会社」を必ず入れます。 |
| 事業目的 | その会社がどのような事業を行うかを具体的に記載します。適法性・営利性・明確性が求められます。将来的に行う可能性のある事業も複数記載しておくのが一般的です。特に、許認可が必要な事業を行う場合は、指定された文言を正確に記載しないと許可が下りないため、行政機関のウェブサイトなどで事前に確認が必要です。 |
| 本店所在地 | 会社の住所です。自宅、賃貸オフィス、バーチャルオフィスなどが選択肢となります。賃貸物件を本店所在地にする場合は、契約書で事業利用や法人登記が可能か必ず確認してください。 |
| 資本金の額 | 会社の元手となる資金です。1円から設立可能ですが、会社の信用度や初期の運転資金に直結するため、事業計画に基づいた適切な金額を設定することが重要です。一般的には「初期費用+3ヶ月から6ヶ月程度の運転資金」が目安とされます。 |
| 発起人・役員構成 | 発起人(出資者)と役員(取締役などの経営者)を誰にするかを決めます。個人事業主からの法人成りであれば、自分一人が発起人兼代表取締役となるケースがほとんどです。複数人で設立する場合は、それぞれの役割と出資比率を明確にしておきましょう。 |
| 事業年度(決算期) | 会社の会計期間の区切りとなる決算月を決定します。自由に設定できますが、繁忙期を避けたり、消費税の免税期間を最大限活用するために設立日からなるべく離れた月に設定したりと、戦略的に決めることをおすすめします。 |
必要な印鑑の準備
法人として活動するためには、専用の印鑑が不可欠です。
一般的に「会社設立印鑑3点セット」として販売されており、登記申請前に準備しておく必要があります。
| 印鑑の種類 | 主な用途 |
|---|---|
| 会社実印(代表者印) | 法務局に登録する最も重要な印鑑です。会社の意思決定を証明するもので、登記申請、不動産取引、重要な契約書などに使用します。一般的に丸い形状で、外枠に会社名、内枠に「代表取締役印」などと彫刻されます。 |
| 銀行印 | 法人口座の開設や、手形・小切手の振り出しなど、銀行との取引で使用する印鑑です。財産を守るため、会社実印とは別の印鑑を用意するのが一般的です。 |
| 角印(社印) | 会社の認印として、請求書や領収書、見積書など、日常的な業務で発行する書類に押印します。法的な効力はありませんが、会社が発行した書類であることを示す役割があります。 |
これらの印鑑は、印鑑専門店やオンラインショップで注文できます。
最短即日発送に対応しているサービスもあるため、急いでいる場合は活用しましょう。
資本金の準備
定款で定めた資本金を、実際に準備します。
この時点ではまだ法人口座は存在しないため、発起人(出資者)個人の銀行口座に、各発起人が出資額を振り込む形で準備します。
発起人が一人の場合は、自身の別口座から振り込むか、一度引き出して再度預け入れるなどして、出資金の入金履歴が通帳に明確に残るようにしてください。
この通帳のコピーが、後述する「払込証明書」の添付資料となります。
書類作成編 定款と登記書類
準備編で決定した内容に基づき、法務局へ提出する公式な書類を作成していきます。
特に「定款」は会社の根本規則となるため、慎重に作成しましょう。
定款の作成方法
定款とは、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたもので、「会社の憲法」とも呼ばれます。
記載事項には、必ず記載が必要な「絶対的記載事項」、記載しないと効力が生じない「相対的記載事項」、任意で定められる「任意的記載事項」があります。
作成方法には「紙の定款」と「電子定款」の2種類がありますが、費用とスピードを重視するなら「電子定款」一択です。
| 電子定款 | 紙の定款 | |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 不要(0円) | 40,000円 |
| 必要なもの | パソコン、PDF作成ソフト、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ | 紙、プリンター |
| メリット | コストを大幅に削減できる。データなので保管や共有が容易。 | 特別な機材が不要で、誰でも作成しやすい。 |
株式会社の場合、作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。
合同会社の場合は公証役場での認証は不要です。
日本公証人連合会のウェブサイトなどにある定款のひな形を参考に、自社の状況に合わせて作成しましょう。
登記申請に必要な書類一覧
定款の準備が整ったら、法務局に提出するその他の登記書類を作成します。
必要な書類は会社形態(株式会社か合同会社か)や機関設計によって異なります。
ここでは、最も一般的な株式会社(発起設立・取締役会非設置)のケースを例に挙げます。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙(収入印紙を貼付)
- 定款(公証人の認証を受けたもの)
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 印鑑証明書(取締役全員分)
- 資本金の払込証明書
- 印鑑届書
- 登記すべき事項を記録したCD-Rなど(オンライン申請の場合は不要)
これらの書類の多くは、法務局のウェブサイトでテンプレートや記載例が公開されています。
一つひとつ確認しながら、漏れなく準備を進めましょう。
申請編 法務局への登記申請から設立完了まで
すべての書類が揃ったら、いよいよ最終ステップの登記申請です。
申請方法によってもスピードが変わってきます。
資本金の払込証明書の作成
登記申請において、資本金が確かに払い込まれたことを証明する「払込証明書」は非常に重要です。
以下の手順で作成します。
- 資本金を振り込んだ発起人個人の通帳を用意します。
- 通帳の「表紙」「1ページ目(支店名や口座番号が記載されているページ)」「資本金の振込が記帳されたページ」の3点をコピーします。
- A4用紙に「払込証明書」として、商号、払込総額、日付、本店所在地、代表取締役の氏名を記載し、会社実印(代表者印)を押印します。
- 作成した払込証明書と、上記3点の通帳コピーをまとめてホチキスで留め、各ページの繋ぎ目に会社実印で割印をします。
ネット銀行などで通帳がない場合は、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人、振込履歴がわかるページのスクリーンショットを印刷したもので代用できます。
オンライン申請と窓口申請の違い
法務局への登記申請には、オンラインで完結させる方法と、直接窓口に書類を持参する方法があります。
| 申請方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| オンライン申請 | 法務局に行く必要がなく、24時間いつでも申請可能。審査が比較的早い傾向にある。 | 専用ソフトのインストールやPCの事前設定が必要。マイナンバーカードとICカードリーダライタが必須。 |
| 窓口申請 | 書類の不備などをその場で相談できる安心感がある。特別なPC環境は不要。 | 法務局の開庁時間(平日8:30~17:15)に行く必要がある。時間と交通費がかかる。 |
「最短3日」というスピード設立を目指すのであれば、移動時間や待ち時間のないオンライン申請が必須の選択肢となります。
申請内容に不備がなければ、申請日から約1週間~10日で登記が完了します。登記が完了した日が、あなたの会社の「設立日」となります。
完了後は、法務局で会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取得できるようになり、いよいよ法人としての活動がスタートします。
【費用一覧】会社設立から運営までのトータルコスト

「とりあえず会社を作る」という考えで進めると、想定外の費用に驚くことが少なくありません。
会社のコストは、設立時に一度だけかかる「初期費用」と、会社を維持するために継続的に発生する「ランニングコスト」の2つに大別して考える必要があります。
ここでは、株式会社と合同会社それぞれのケースで、具体的にどれくらいの費用がかかるのかを徹底的に解説します。
しっかりとした資金計画を立て、後悔のない法人化を目指しましょう。
会社設立時にかかる初期費用
会社設立の初期費用は、設立する会社形態(株式会社か合同会社か)や、手続きの方法(電子定款か紙の定款か)によって大きく変動します。
ここでは、法務局への登記や定款作成に関わる法定費用と、専門家に依頼した場合の報酬について詳しく見ていきましょう。
登録免許税
登録免許税は、会社の設立登記を法務局に申請する際に納める国税です。
この税額は、資本金の額と会社形態によって決まりますが、最低額が定められています。
- 株式会社の場合:資本金の0.7%(最低15万円)
- 合同会社の場合:資本金の0.7%(最低6万円)
例えば、資本金が1,000万円の場合、株式会社なら7万円ですが最低額の15万円が適用されます。
合同会社なら7万円がそのまま登録免許税額となります。
「とりあえず会社を作る」場合、多くは資本金を低めに設定するため、この最低額を支払うケースがほとんどです。
定款認証手数料と印紙代
定款(ていかん)は会社のルールを定めた重要な書類です。
株式会社の場合は公証役場での認証が必要ですが、合同会社では不要です。
また、定款を紙で作成するか、電子データで作成する(電子定款)かによって、4万円の収入印紙代の有無が変わるため、非常に重要なポイントです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 約5万円 | 不要 |
| 定款の謄本手数料 | 約2,000円(1ページ250円) | 不要 |
| 収入印紙代(紙の定款) | 4万円 | 4万円 |
| 収入印紙代(電子定款) | 0円 | 0円 |
ご覧の通り、株式会社・合同会社ともに電子定款を利用すれば4万円の収入印紙代が不要になり、大幅にコストを削減できます。
ただし、電子定款の作成には専用のICカードリーダーライタやソフトウェアが必要になるため、手続きの手間とコストを天秤にかける必要があります。
司法書士など専門家への報酬
会社設立の手続きは複雑なため、司法書士や行政書士などの専門家に代行を依頼することも可能です。
その場合、法定費用とは別に専門家への報酬が発生します。
報酬の相場は依頼する業務範囲によって異なりますが、一般的には5万円〜15万円程度です。
一見すると追加の出費に思えますが、多くの専門家は電子定款に対応しているため、自分で紙の定款で設立するよりも、専門家に依頼した方がトータルコストが安くなるケースも少なくありません。
時間と手間を節約し、確実に手続きを進めたい場合には有力な選択肢となります。
会社設立後にかかるランニングコスト
会社は設立して終わりではありません。事業を運営していくためには、継続的なコスト(ランニングコスト)が発生します。
特に、たとえ事業が赤字であっても支払わなければならない費用があるため、事前にしっかりと把握しておくことが極めて重要です。
法人税・法人住民税・法人事業税
法人が納める主要な税金には「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3つがあります。
法人税と法人事業税は会社の利益(所得)に対して課税されるため、赤字の場合は基本的に発生しません。
しかし、注意すべきは「法人住民税」です。
法人住民税は、利益に応じて課税される「法人税割」と、会社の規模に応じて定額で課税される「均等割」で構成されています。
この「均等割」は、会社の利益が赤字であっても資本金や従業員数に応じて最低でも年間約7万円を必ず支払う義務があります。
個人事業主にはない、法人ならではの固定コストと言えるでしょう。
社会保険料
法人を設立すると、たとえ社長一人だけの会社であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています。
個人事業主時代の国民健康保険や国民年金とは異なり、保険料は会社と役員(従業員)が半分ずつ負担(労使折半)します。
保険料は役員報酬の金額に応じて決まりますが、一般的に個人事業主の国民健康保険料などと比較して負担額が増えるケースが多く、会社のキャッシュフローに大きな影響を与えます。
役員報酬を決める際には、社会保険料の負担額もシミュレーションしておくことが不可欠です。
税理士顧問料
法人の会計処理や税務申告は、個人事業主の確定申告よりも格段に複雑になります。
そのため、多くの会社が税理士と顧問契約を結んでいます。
税理士に依頼すれば、正確な税務申告はもちろん、節税対策や資金繰りのアドバイスなど、経営をサポートしてもらうことができます。
顧問料の相場は会社の規模や取引量によって変動しますが、目安としては以下の通りです。
- 月額顧問料:2万円〜5万円程度
- 決算申告料:10万円〜20万円程度(月額顧問料の4〜6ヶ月分が目安)
年間で30万円以上のコストになりますが、本業に集中し、経営の安定性を高めるための重要な投資と捉えることができます。
とりあえず会社を作った後の必須手続き
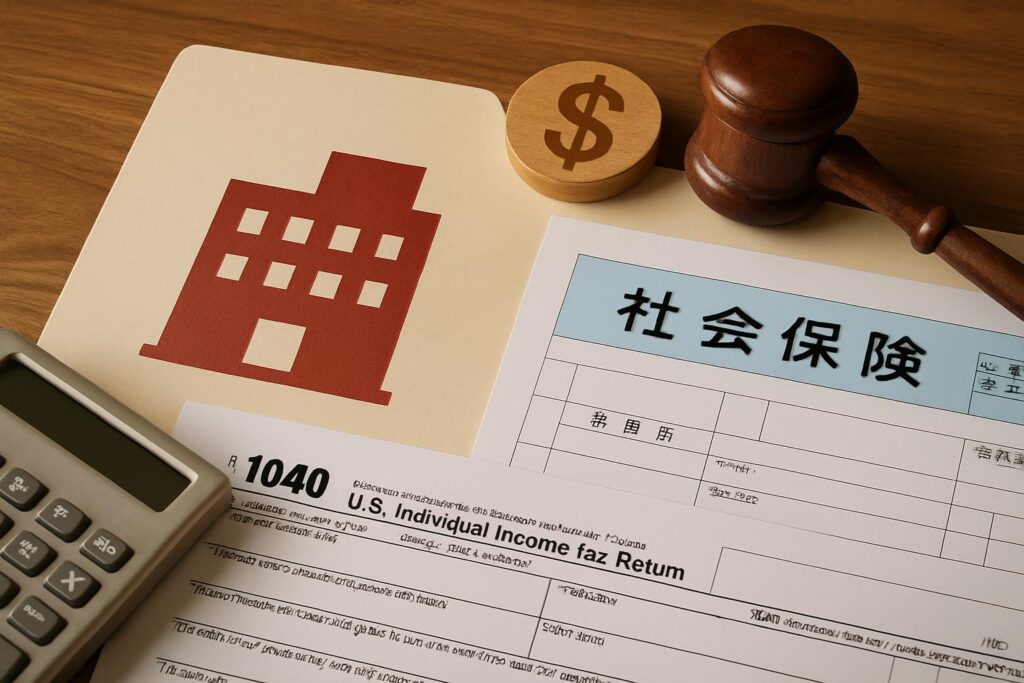
会社の設立登記が完了し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できたら、一安心…ではありません。
事業を本格的にスタートさせる前に、税金や社会保険に関する重要な手続きが数多く待ち構えています。
これらの手続きは提出期限が定められており、怠ると税制上の優遇措置が受けられなくなったり、後々ペナルティが発生したりする可能性があります。
ここでは、会社設立後に必ず行うべき手続きを網羅的に解説します。
税金関連の手続き
会社を設立したら、まず国税(税務署)と地方税(都道府県税事務所、市町村役場)に関する届出が必要です。
特に「青色申告の承認申請書」は、提出期限を過ぎるとその事業年度での適用が受けられなくなり、節税メリットを逃すことになるため注意しましょう。
主な手続きは以下の通りです。
| 提出書類名 | 提出先 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署 | 設立後2ヶ月以内 | 会社の基本情報を税務署に知らせるための書類です。定款のコピーなどを添付します。 |
| 法人設立届出書 | 都道府県税事務所・市町村役場 | 都道府県・市町村により異なる(設立後15日〜2ヶ月以内など) | 法人住民税や法人事業税の納税のために必要です。提出先が2ヶ所ある点に注意してください。 |
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立後3ヶ月を経過した日と、最初の事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで | 欠損金の繰越控除など、多くの節税メリットがあります。設立初年度から適用を受けるには期限内の提出が必須です。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 給与支払事務所を設置した日から1ヶ月以内 | 役員報酬や従業員への給与を支払う場合に提出します。社長1人の会社でも役員報酬を支払うなら必要です。 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 特例を受けたい月の前月末日まで | 給与を支払う従業員が常時10人未満の場合、源泉所得税の納付を毎月から年2回(7月と1月)にまとめられる制度です。資金繰りの負担を軽減できます。 |
これらの手続きは、国税は「e-Tax」、地方税は「eLTAX」というシステムを利用して、オンラインで申請することも可能です。
移動時間や待ち時間を削減できるため、積極的に活用を検討しましょう。
社会保険・労働保険関連の手続き
法人を設立すると、たとえ社長1人の会社であっても社会保険への加入が法律で義務付けられています。
個人事業主からの法人成りで最も大きな変化の一つであり、コストにも影響するため、必ず手続きを行いましょう。
従業員を雇用する場合は、さらに労働保険の手続きも必要になります。
| 保険の種類 | 主な提出書類 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険(社会保険) | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届、被保険者資格取得届 | 管轄の年金事務所 | 事実発生(設立)から5日以内 |
| 労災保険 | 保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書 | 管轄の労働基準監督署 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険 | 保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届 | 管轄のハローワーク | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、役員や従業員の国籍・年齢・労働時間などに関わらず、法人の代表者であれば加入義務があります。
役員報酬から社会保険料が天引きされることになりますので、資金計画にも忘れずに織り込んでおきましょう。
一方、労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員を1人でも雇用した場合に加入手続きが必要となります。
労災保険はすべての労働者が対象ですが、雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上などの加入要件を満たす従業員が対象です。
許認可の申請(必要な場合)
行う事業の内容によっては、事業を開始する前に国や地方公共団体から「許認可」を得る必要があります。
許認可が必要な事業を無許可で営業した場合、罰金や営業停止命令といった厳しい行政処分の対象となるため、自社の事業に許認可が必要かどうかを設立前に必ず確認しておくことが重要です。
許認可が必要な事業の代表例には、以下のようなものがあります。
- 建設業:建設業許可
- 飲食業:飲食店営業許可
- リサイクルショップなどの中古品売買:古物商許可
- 不動産業:宅地建物取引業免許
- 運送業:一般貨物自動車運送事業許可
- 人材派遣業:労働者派遣事業許可
- 酒類の販売:酒類販売業免許
これらの許認可は、申請から取得までに数週間から数ヶ月かかるケースも少なくありません。
また、申請には専門的な知識や書類作成が求められるため、スムーズに事業を開始するためにも、必要であれば行政書士などの専門家への相談も視野に入れると良いでしょう。
まとめ
「とりあえず会社を作る」という安易な考えは、設立後の税金や社会保険料の負担といった思わぬ落とし穴に繋がります。
本記事で解説した個人事業主との違い、株式会社と合同会社の選択基準、設立から運営までの費用を理解すれば、後悔のない判断が可能です。
最短3日で設立は可能ですが、まずはご自身の事業計画と照らし合わせ、最適なタイミングと形態を見極めることが成功への第一歩です。



